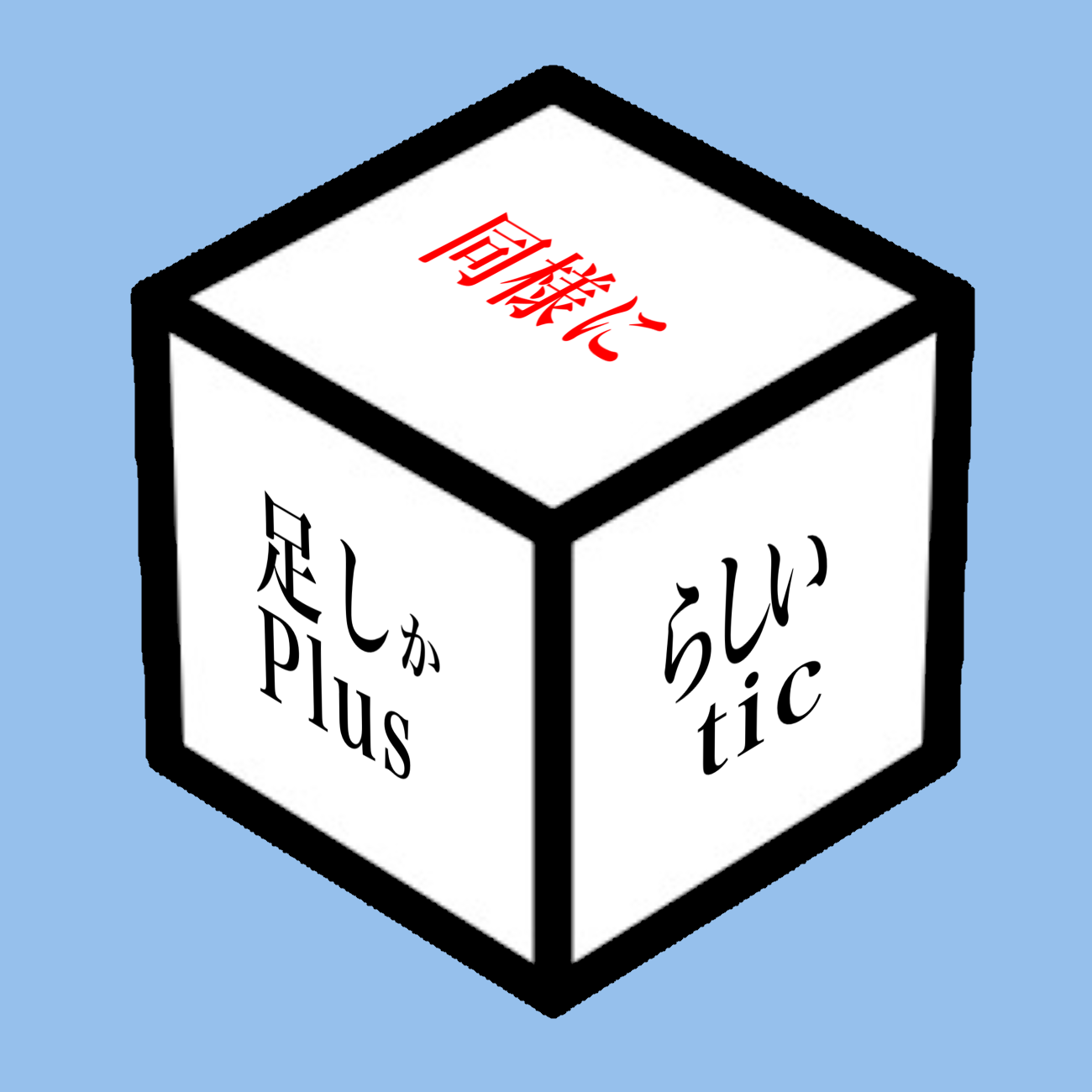相加相乗平均の不等式の間に
はじめに読んでほしい
この記事は初学者が書いています。間違いや不備があるかも知れません。見つけたら教えて頂けると嬉しいです。
またアドバイスが有れば是非、コメントしてくれると有難いです。
追記:これについて先に取り上げてるの ありま した。多分、こことは別の証明方法?英語分からない。
本題
証明したい不等式はこれです。
$x_1…,x_n>0$の$k$次の基本対称対称式を$S_k$と書いたとき、以下が成り立つ。
$$ \sqrt[k]{\frac{S_k}{ { n \choose k } }}≧\sqrt[l]{\frac{S_l}{ { n \choose l } }}\quad(1≦k< l≦n)$$
各$l,k$について等号条件は、$x_1…=x_n$となること。
$k$次の基本対称式とは$\sum_{1≦r_1…< r_k≦n}x_{r_k}…x_{r_k}$のコトで、 対称式の基本定理 や 解と係数の関係 でよく出てきます。
$k=1,l=n$のときは$S_1=\sum x_i,S_n=x_1…x_n$なので、よくよく知られている相加相乗平均の不等式です。つまりこれは相加相乗平均の不等式の一般化になるわけです(この証明に相加相乗平均の不等式を使うのでコレから相加相乗平均の不等式を示すのは循環論法になってしまいます)。相加相乗平均の不等式の証明は
こちら
に。
$\sqrt[k]{\frac{S_k}{ { n \choose k } }}$は平均のような性質を持っています(実際$k=1,n$の時は相加平均と相乗平均)。
次に必要な補題を上げます。
$f(x)$を複素数係数多項式とする。$f’(x)$の零点集合は$f(x)$の零点集合の凸包に含まれる。
証明は
こちら
を参照のコト(そんなに難しくない)。
この定理は全ての多項式の零点がある凸集合(上半平面や実数直線)に含まれるとき、その導関数の零点もその凸集合に含まれることを言ってくれます。不等式の証明にはこの定理が重要、或いはコレを使うと簡単になります。
それともう一つ簡単な補題を上げます。
$n≧3$と実数$a$と実数係数多項式$f(x)$に対して$\frac{f’(x)}{n}={(x+a)^{n-1}}$が成り立ち$f(x)$の零点が全て実数ならば$f(x)={(x+a)^{n}}$と書ける。
$f’(x)=n(x+a)^{n-1}$を積分することで定数$c$を用いて$f(x)={(x+a)^{n}}+c$と書ける。$c=0$を示せばよい。
$c>0$であるなら$y=\frac{x+a}{\sqrt[n]{c}}$と置ける。$y^{n}+1=0$の解を考えたとき$y=e^{\frac{iπ}{n}}$は解であるが実数でない。
$c<0$のとき$c’=-c>0$と置いて$y=\frac{x+a}{\sqrt[n]{c’}}$と置ける。$y^{n}-1=0$の解を考えたとき、$y=e^{\frac{2iπ}{n}}$は解ではあるが$n≧3$であれば実数ではない。
証明がまどろっこしいですね。証明で不十分な所があるかも知れないです。
ではいよいよ冒頭の定理を証明していきます。
$1≦k< l≦n$に対して不等式と統合条件が成り立つことを$\mathrm{P}(n,l,k)$で表すこととする。証明の方針は、
(1) $\mathrm{P}(n,n,k)$を示す
(2) $l< n$に対して$\mathrm{P}(n-1,l,k)$なら$\mathrm{P}(n,l,k)$を示す
(1)と(2)によって全ての$1≦k< l≦n$に対して証明が尽くされる(帰納法の変種)。
(1) $\mathrm{P}(n,n,k)$を示す
相加相乗平均の不等式を用いて
$\sqrt[k]{\frac{S_k}{ { n \choose k } }}=\sqrt[k]{\frac{\sum_{1≦r_1…< r_k≦n}x_{r_1}…x_{r_k}}{ { n \choose k } }}≧\sqrt[k]{\sqrt[{n \choose k}]{(x_1…x_n)^{n-1 \choose k-1}}}=\sqrt[n{n-1 \choose k-1}]{(x_1…x_k)^{n-1 \choose k-1}}=\sqrt[n]{x_1…x_n}=\sqrt[n]{S_n}$
統合条件は、相加相乗平均の不等式の統合条件より$x_{r_1}…x_{r_k}$の値が${1≦r_1…< r_k≦n}$の取り方に寄らないことが分かるので$x_1…=x_n$が言える。
よって$\mathrm{P}(n,n,k)$
(2) $l< n$に対して$\mathrm{P}(n-1,l,k)$なら$\mathrm{P}(n,l,k)$を示す
$f(x)=(x+x_1)…(x+x_n)$としたとき、$S_k=\frac{f^{(n-k)}(0)}{(n-k)\mathrm{!}}$となる。
$g(x)=\frac{f’(x)}{n}$としたとき、最高次係数が$1$でありガウス・ルーカスの定理より全ての零点は負な実数である。よって$y_1…,y_{n-1}≧0$を用いて$g(x)=(x+y_1)…(x+y_{n-1})$と書ける。
$y_1…,y_{n-1}$の$n-1$変数の$k$次の基本対称式を$S’_k$と書いたとき、$S’_k=\frac{g^{(n-1-k)}(0)}{(n-1-k)\mathrm{!}}$となる。よって
$\sqrt[k]{\frac{S_k}{ { n \choose k } }}=\sqrt[k]{\frac{f^{(n-k)}(0)}{(n-k)\mathrm{!} { n \choose k } }}=\sqrt[k]{\frac{ng^{(n-1-k)}(0)}{(n-k)\mathrm{!} { n \choose k } }}=\sqrt[k]{\frac{g^{(n-1-k)}(0)}{(n-1-k)\mathrm{!} { n-1 \choose k } }}=\sqrt[k]{\frac{S’_k}{{ n-1 \choose k } }}$が言える。同様に$\sqrt[l]{\frac{S’_l}{ { n-1 \choose l } }}=\sqrt[l]{\frac{S_l}{ { n \choose l } }}$も成り立つ。
帰納法の仮定より$ \sqrt[k]{\frac{S’_k}{ { n-1 \choose k } }}≧\sqrt[l]{\frac{S’_l}{ { n-1 \choose l } }}$が言えるので$ \sqrt[k]{\frac{S_k}{ { n \choose k } }}=\sqrt[k]{\frac{S’_k}{ { n-1 \choose k } }}≧\sqrt[l]{\frac{S’_l}{ { n-1 \choose l } }}=\sqrt[l]{\frac{S_l}{ { n \choose l } }}$
統合条件は、$ \sqrt[k]{\frac{S_k}{ { n \choose k } }}=\sqrt[l]{\frac{S_l}{ { n \choose l } }}$なら$\sqrt[k]{\frac{S’_k}{ { n-1 \choose k } }}=\sqrt[l]{\frac{S’_l}{ { n-1 \choose l } }}$が言えるので、帰納法の仮定より$y_1…=y_{n-1}$が言えて$g(x)=(x+y_1)…(x+y_{n-1})=(x+y_1)^{n-1}$が言えて$f(x)$が全ての解を実数に持ち$g(x)=\frac{f’(x)}{n}$あり、$n>l>k≧1$より$n≧3$であるので、補題3より$f(x)=(x+y_1)^n$がいえる。よって$y_1=x_1…=x_n$が言える。
よって$\mathrm{P}(n,k,l)$
証明できました。私はガウス・ルーカスの定理を初めて使いました。
自分中では証明方法はコレしか思い付きませんでしたが、他の証明方法でモット分かりやすいものが有れば是非是非教えてほしいです(反語じゃないヨ)。
これを裏っ返すことで調和平均みたいな平均も作れて、これにも不等式を作ることができます。
本題じゃない方
上の定理からの発展について考えました。ただ私は力不足で力尽きたのでココに供養しておきます。
あはよくば誰かに解決して欲しい(他力本願)。
算術幾何平均のn項版
算術幾何平均とは$a,b≧0$に対して$a_0=a,b_0=b$からはじめて$a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2},b_{n+1}=\sqrt{a_nb_n}$と定めた数列の極限として定まる平均です。2つのこの数列が同じ極限を持つことは、二変数の相加相乗平均の不等式より分かります。
相加相乗平均の間の不等式を考えようとしていたのは算術幾何平均を$n$項に拡張しようということを考えていたからです。算術幾何平均を二変数と同様に定めたいならば、$n$変数から定まる$n$個の平均とそこに定まる不等式が必要です。
$n$個の平均と不等式自体は、相加相乗平均の不等式を一定の$n$分割をすることで容易に作ることはできますが、そこに妥当性や自然性があるのかが疑問でした(若しかしたらあるのかも知れませんが)。
この記事で相加相乗平均の間に作った不等式はマアマア自然な拡張になっていると思います。
$x_1…,x_n≧0$に対して$S_k(x_1…,x_n)$を$k$次基本対称式を表すものとする。
$x_k^{(0)}$からはじめて$x_k^{(m+1)}=\sqrt[k]{\frac{S_k(x^{(m)}_1…,x^{(m)}_n)}{ { n \choose k } }}$と定めた数列の極限を$x_1…,x_n$の算術幾何平均という。これは$k$に寄らずに定める。
定義のwell-defined性は今回の不等式を用いて
コレ
と大体同じように証明できます。
ところで$2$変数の算術幾何平均は積分を用いて表すことができます。
$M(a,b)$で$a,b$の算術幾何平均を表すものとする。
$$M(a,b)= \frac{π}{2}/\int_{0}^{\frac{π}{2}}\frac{dθ}{\sqrt{a^2\cos^2θ+b^2\sin^2θ}} $$
分母に積分が入ってるので若干見にくい気もしますが、フワフワな極限をキッチリした積分で表すことができるのは魅力的です。
さて、上で定義した$n$変数の算術幾何平均にもこのようなキッチリした表示があるのでしょうか。私には分かりませんでした。
重さ付き平均への拡張
通常の相加相乗平均の不等式には単純な一般化があります。
$x_1…,x_n,λ_1…,λ_n≧0$で$λ_1…+λ_n=1$が成り立つとき$λ_1x_1…+λ_nx_n≧x_1^{λ_1}…x_n^{λ_n}$が言える。
$\frac{1}{n}=λ_1…=λ_n$のとき、これは相加相乗平均の不等式に一致します。
証明はイェンセンの不等式を用いる方法もありますが、相加相乗平均の不等式の変数を増やしていって近似して不等式を証明する方法があります(せせこましいですが)。
この後者の方法で相加相乗平均の間に出てきた平均の変数を増やしていって重さ付きにすることができます。
ただこの近似の方法というには一意ではなく、変数を増やすごとに$k$も増やすか増やさないか、増やすにしてもどれぐらいで増やしていくのかという所で唯一には定りません。重さ付き相加相乗平均の不等式は$k$の増やし加減の上限と加減を簡潔に示したものになります。
重さ付きの平均に具体的な表示があるかどうかが分かれば嬉しいのですが、私は力不足でした。
終わりに
読んでくれてありがとうございます。間違いや変えた方がいいような所は教えてくれると嬉しいです。