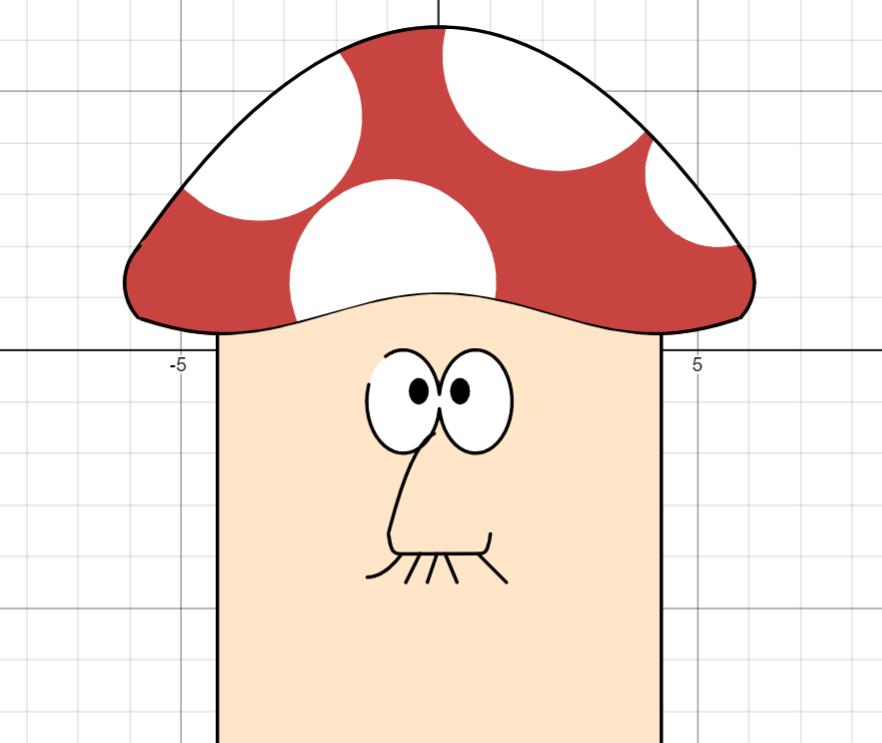蛇の補題 with 位相
あけましておめでとうございます(激遅)
今年(2025)は巳年(へびどし)ということで、蛇の補題を証明していきたいと思います!
...が、普通の蛇の補題はみなさんご存じですよね...なので今回は位相群における蛇の補題を証明していきたいと思います!
$\bullet$像と逆像の性質と計算
$\bullet$アーベル群上の蛇の補題とその証明
$\bullet$商位相と部分位相の性質
準備
今回は位相が入ったアーベル群にも蛇の補題が成り立つことを示していきたいと思います。
その前に蛇の補題を述べるのに使う対象の定義の準備から入りたいと思います
$M,M'$を可換な位相群とし、$f:M\to M'$を連続準同型写像とする。
$(1)\text{Ker}^*f$を$\text{Ker}f$に$M$の部分位相を入れたものとする
$(2)\text{Coker}^*f$を$M'\to\text{CoKer}f$の商位相とする
つまり、例えば(1)というのは$\mathcal O_{\text{Ker}f}:=\{U\cap\text{Ker} f|U\in\mathcal O_M\}$で$\text{Ker}^*f:=(\text{Ker}f,\mathcal O_{\text{Ker}f})$ということです
$f:M\to M'$を連続準同型写像とする
$(1)$核の包含写像を$i_f:\text{Ker}^*f\to M$とする
$(2)$余核への商写像を$\pi_f:M'\to\text{Coker}^*f$とする
$M,M',M''$を可換な位相群とする。
$$\xymatrix{M\ar[r]^{f}&M'\ar[r]^{g}&M''}$$
が$f,g$が連続な準同型写像で、$\text{Im}\ f=\text{Ker}\ g$となるとき$M'$で完全と呼ぶ
また全ての$M^{\bullet}$で完全な時、完全列と呼ぶ
$\text{Im}f$と$\text{Ker}f$の位相が同相である必要はありません
あくまで群として$\text{Im}\ f=\text{Ker}\ g$であればOKです
本題
$A,B,C,A',B',C'$を可換な位相群とし
$$\xymatrix{&A\ar[r]^{f}\ar[d]^{a}&B\ar[r]^{g}\ar[d]^{b}&C\ar[d]^{c}\ar[r]&0\\0\ar[r]&A'\ar[r]^{f'}&B'\ar[r]^{g'}&C'}$$
が上の行と下の行が完全で可換図式になり$f'$を閉写像 $g$を開写像 図式の全ての写像を連続とする。このとき蛇の補題により誘導される長完全列
$$\xymatrix{{\text{Ker}^*a}\ar[r]^{d_1}&{\text{Ker}^*b}\ar[r]^{d_2}&{\text{Ker}^*c}\ar[r]^{\delta}&{\text{Coker}^*a}\ar[r]^{q_1}&{\text{Coker}^*b}\ar[r]^{q_2}&{\text{Coker}^*c}}$$
は全て連続写像になる
$d_1,d_2$を$(\text i)、q_1,q_2$を$(\text {ii})、\delta$を$(\text{iii})$で証明します
$(\text i)$
$\text{Ker}^*b$は部分位相なので$d_1$が連続であることと$i_b\circ d_1$が連続であることは同値。また$i_b\circ d_1=f\circ i_a$であり$f,i_a$は連続なので$d_1$は連続。$d_2$も同様に示せる
$(\text{ii})$
$\text{Coker}^*a$は商位相なので$q_1$が連続であることと$q_1\circ\pi_a$が連続であることは同値。また$q_1\circ\pi_a=\pi_b\circ f'$で$f',\text{coker}\ a$は連続なので$q_1$は連続。$q_2$も同様に示せる
$(\text{iii})$
$\delta$の構成から$x\in\text{Ker}^*c$に対して$\pi_a(f'^{-1}(b(g^{-1}(i_c(\{x\})))))=\{{\delta(x)}\}$なので$0\in U\subset\text{Coker}\ a$とすると
$\delta^{-1}(U)$
($\delta$の構成と逆像の定義より)
$=\{x\in\text{Ker}\ c|\pi_a(f'^{-1}(b(g^{-1}(i_c(\{x\})))))\subset U\}$
($\pi_a(\pi_a^{-1}(X))\subset X$と$X\subset\pi_a^{-1}(\pi_a(X))$より)
$=\{x\in\text{Ker}\ c|f'^{-1}(b(g^{-1}(i_c(\{x\}))))\subset \pi_a^{-1}(U)\}$
($f'$の単射性と$b(g^{-1}(i_c(\{x\})))\subset\text{Im}\ f'$より)
$=\{x\in\text{Ker}\ c|b(g^{-1}(i_c(\{x\})))\subset f'(\pi_a^{-1}(U))\}$
($X\subset b^{-1}(b(X))$と$b(b^{-1}(X))\subset X$より)
$=\{x\in\text{Ker}\ c|g^{-1}(i_c(\{x\}))\subset b^{-1}(f'(\pi_a^{-1}(U)))\}$
($g$の全射性と$\text{Ker}\ g= \text{Im}\ f\subset b^{-1}(f'(\pi_a^{-1}(\{0\}))$より)
$=\{x\in\text{Ker}\ c|i_c(\{x\})\subset g(b^{-1}(f'(\pi_a^{-1}(U))))\}$
($X\subset i_c^{-1}(i_c(X))$と$i_c(i_c^{-1}(X))\subset X$より)
$=\{x\in\text{Ker}\ c|\{x\}\subset i_c^{-1}(g(b^{-1}(f'(\pi_a^{-1}(U)))))\}$
(像と逆像の定義より)
$=i_c^{-1}(g(b^{-1}(f'(\\\pi_a^{-1}(U)))))$
となる
$\delta$は位相群上の準同型写像なので連続性は$0$を含む開集合の逆像が開集合である事を示せばよい
$U\subset\text{Coker}^*a$を$0$を含む開集合とすると$\pi_a^{-1}(U)$は開集合なので$A'\backslash\pi_a^{-1}(U)$は閉集合。$f'$は閉写像なので
$f'(A'\backslash\pi_a^{-1}(U))$
は閉集合であり$f'$は単射でもあるので
$f'(A')\backslash f'(\pi_a^{-1}(U))$
も閉集合。また$b$も連続なので
$b^{-1}(f'(A')\backslash f'(\pi_a^{-1}(U)))$
$=b^{-1}(f'(A'))\backslash b^{-1}(f'(\pi_a^{-1}(U)))$
は閉集合。また$b^{-1}(f'(\pi_a^{-1}(U)))\subset b^{-1}(f'(A'))$なので
$B\backslash(b^{-1}(f'(A'))\backslash b^{-1}(f'(\pi_a^{-1}(U))))$
$=(B\backslash b^{-1}(f'(A')))\cup b^{-1}(f'(\pi_a^{-1}(U)))$
は開集合である。また$g$は開写像より
$g((B\backslash b^{-1}(f'(A')))\cup b^{-1}(f'(\pi_a^{-1}(U))))$
$=g(B\backslash b^{-1}(f'(A')))\cup g(b^{-1}(f'(\pi_a^{-1}(U))))$
は開集合となり$i_c$の連続性から
$i_c^{-1}(g(B\backslash b^{-1}(f'(A'))))\cup i_c^{-1}(g(b^{-1}(f'(\pi_a^{-1}(U)))))$
$=i_c^{-1}(g(B\backslash b^{-1}(f'(A'))))\cup\delta^{-1}(U)$
は開集合となる。
$x\in g^{-1}(B\backslash b^{-1}(f'(A')))$を取ると$g$は全射よりある$y\in B\backslash b^{-1}(f'(A'))$が存在して$g(y)=x$なので
$b(y)\in b(B\backslash b^{-1}(f'(A')))=\text{Im b}\backslash f'(A')\subset B'\backslash f'(A')$
となりB'は完全より
$f'(A')=\text{Im}\ f'=\text{Ker}\ g'=g'^{-1}(\{0\})$
なので
$c(x)=c(g(y))=g'(b(y))\in g'(B'\backslash \ g'^{-1}(\{0\}))=g(B')\backslash \{0\}\subset C'\backslash \{0\}$
よって$c(x)\neq 0$なので$x\notin\text{Ker c}$とわかり
$g^{-1}(B\backslash b^{-1}(f'(A')))\cap \text{Ker c}=\varnothing$
であるから
$i_c^{-1}(g(B\backslash b^{-1}(f'(A'))))\cup\delta^{-1}(U)$
$=(g(B\backslash b^{-1}(f'(A')))\cap \text{Ker c})\cup\delta^{-1}(U)$
$=\delta^{-1}(U)$
は開集合であることがわかり、$\delta$は連続
おまけ
上の証明で使った、定理とか行間の証明を載せておきます
$X,Y,Z$を位相空間とし、$i:Y→Z$を埋め込み写像、$f:X→Y$を写像とすると以下が成り立つ
$f$が連続⇔$i\circ f$が連続
$X,Y,Z$を位相空間とし、$\pi:X→Y$を商写像、$f:Y→Z$を写像とすると以下が成り立つ
$f$が連続⇔$f\circ\pi$が連続
$f:X→Y$を写像とし、$U_1,U_2\subset X\ ,\ V_1,V_2\subset Y$とすると、像逆像について以下が成り立つ
$\bullet f(U_1\cup U_2)=f(U_1)\cup f(U_2)$
$\bullet f(U_1\cap U_2)\subset f(U_1)\cap f(U_2)$
$\bullet f^{-1}(V_1\cup V_2)=f^{-1}(V_1)\cup f^{-1}(V_2)$
$\bullet f^{-1}(V_1\cap V_2)=f^{-1}(V_1)\cap f^{-1}(V_2)$
$\bullet U_1\subset f^{-1}(f(U_1))$ (単射なら統合が成立)
$\bullet f(f^{-1}(U_1))\subset U_1$ (全射なら統合が成立)
$\bullet f^{-1}(V_1\backslash V_2)=f^{-1}(V_1)\backslash f^{-1}(V_2)$
$\bullet f(U_1\backslash f^{-1}(V_1))=f(U_1)\backslash V_1$
$A,B,C,A',B',C'$をアーベル群とし
$$\xymatrix{&A\ar[r]^{f}\ar[d]^{a}&B\ar[r]^{g}\ar[d]^{b}&C\ar[d]^{c}\ar[r]&0\\0\ar[r]&A'\ar[r]^{f'}&B'\ar[r]^{g'}&C'}$$
が上の行と下の行が完全列になるような可換図式とする。このとき長完全列
$$\xymatrix{{\text{Ker}\ a}\ar[r]^{d_1}&{\text{Ker}\ b}\ar[r]^{d_2}&{\text{Ker}\ c}\ar[r]^{\delta}&{\text{Coker}\ a}\ar[r]^{q_1}&{\text{Coker}\ b}\ar[r]^{q_2}&{\text{Coker}\ c}}$$
が誘導され完全列になる
$(1)\ b(g^{-1}(i_c(\{x\})))\subset\text{Im}\ f'$
$(2)\ \text{Im}\ f\subset b^{-1}(f'(\pi_a^{-1}(\{0\}))$
$(3)\ H$が$B$の部分群$\land\ S\subset B\land\ \text{Ker}\ g\subset H\ \Rightarrow g^{-1}(g(SH))=SH$
$(1)$
蛇の補題の証明を参照してください()
$(2)$
$x\in\text{Im}\ f$とすると、ある$t\in A$が存在して、$f(t)=x$となる。$\pi_a(a(t))=0$なので
$a(t)\in\pi_a^{-1}(\{0\})$となり$f'(a(t))\in f'(\pi_a^{-1}(\{0\}))$で図式の可換性から
$b(f(t))\in f'(\pi_a^{-1}(\{0\}))$よって$x=f(t)\in b^{-1}(f'(\pi_a^{-1}(\{0\})))$
$(3)$
$g^{-1}(g(SH))=SH\text{Ker}\ g=SH$
おわりに
ご拝読いただきありがとうございました!
元々新年に乗せるつもりでしたが証明が埋まらずこんなにかかってしまいました。(振り返ると、大まかな方針自体はシンプルだったのでもっと早く出したかったです...)
証明を見るとわかるのですが、実は全く群の交換法則を使っていないので蛇の補題が成り立つ代数系であれば同じ議論が回せます!
是非とも証明に挑戦してみてください
来年は午年(うまどし)なので「次は馬に関する記事を書こうかなぁ」と思って調べたら、馬蹄形写像(力学系のお話)と競馬(主に確立のお話)しかヒットせず絶望したので、来年はもう干支の記事を書きません()
もし他に馬に関する命題があった場合は教えていただけると喜びます!
あらためましてご拝読ありがとうございました!
今年もよろしくお願いします(激遅)