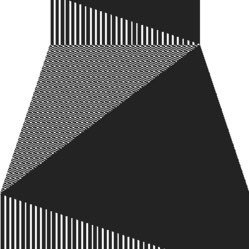無限集合メモ1
Kunenの集合論2章が永遠にわかんない。ほぼ写してるだけですんません。
0. 共終数と正則基数
なんとなく、Kunen2章で基数の正則性がめちゃくちゃ重要になりそうな気がしたので、1章に書いてある内容だがざっくりまとめる。
定義
共終数
順序数$\alpha$について、$\alpha$の共終数とは、$\alpha$の非有界な部分集合の順序型のうち最小のものである。
正則基数
極限順序数$\kappa$が正則であるとは、$\kappa$の共終数が$\kappa$であること、すなわち$\kappa$の非有界部分集合の順序型が必ず$\kappa$となることである。
性質
任意の極限順序数$\alpha$について、$\alpha$の共終数の共終数と、$\alpha$の共終数は等しい。特に、$\alpha$の共終数は正則である。
証明
順序数$\alpha$の共終数の共終数$\textrm{cf}(\textrm{cf}(\alpha))$は、$\textrm{cf}(\alpha)$の非有界な部分集合の順序型のうち最小のものである。よって、$\textrm{cf}(\alpha)$の非有界な部分集合のうち順序型が$\textrm{cf}(\textrm{cf}(\alpha))$となるもの$A$が存在する。
同様に、$\alpha$の非有界な部分集合のうち順序型が$\textrm{cf}(\alpha)$となるもの$B$が存在する。
ここで、$\textrm{cf}(\alpha)$から$B$への一意な順序同型$f$によって得られる$A$の像$f[A]$は$\alpha$の部分集合となる。$B$は$\alpha$の非有界部分集合なので、任意の$\xi < \alpha$について、$\xi < \beta$を満たす$B$の元$\beta$が存在する。
また、$f^{-1}(\beta) < \textrm{cf}(\alpha)$なので、$A$は$\textrm{cf}(\alpha)$の非有界部分集合であることから、$f^{-1}(\beta) < \gamma$を満たす$A$の元$\gamma$が存在する。
$f$は順序同型なので、$\xi < \beta < f(\gamma)$である。$\gamma$は$\alpha$の任意に取った元であり、$f(\gamma) \in f[A]$なので、$f[A]$は$\alpha$上非有界である。$f[A]$の順序型は$A$の順序型、すなわち$\textrm{cf}(\textrm{cf}(\alpha))$である。
$\alpha$には順序型$\textrm{cf}(\textrm{cf}(\alpha))$の非有界部分集合が存在することがわかったので、共終数の定義から$\textrm{cf}(\textrm{cf}(\alpha)) \le \textrm{cf}(\alpha)$である。
また、$\textrm{cf}(\alpha) \le \textrm{cf}(\textrm{cf}(\alpha))$でもあるので、結局$\textrm{cf}(\textrm{cf}(\alpha)) = \textrm{cf}(\alpha)$となる。□
任意の極限順序数$\alpha$について、$\alpha$の共終数は$\alpha$の濃度以下である。特に、$\alpha$が正則ならば$\alpha$は基数である。
証明
$\alpha$の濃度$|\alpha|$から$\alpha$への全単射$f$を1つ固定する。$|\alpha|$から$\alpha+1$への写像$F$を、以下のように$|\alpha|$上の超限再帰で定義する。
$\sup\{F(\xi) \mid \xi < \gamma\} < \alpha$ならば、$F(\gamma) := \max \{f(\gamma),\sup\{F(\xi) \mid \xi < \gamma\}+1\}$である。
$\sup\{F(\xi) \mid \xi < \gamma\} \ge \alpha$ならば、$F(\gamma) := \alpha$である。
明らかに、任意の$\beta<\gamma<|\alpha|$について、$F(\beta) < \alpha$ならば$F(\beta) < F(\gamma)$である。また、常に$f(\beta) \ge F(\beta)$が成り立つ。
$\sup\{F(\xi) \mid \xi < \gamma\} \ge \alpha$となる$\gamma < |\alpha|$が存在する場合、そのうち最小のものを$\rho$とおき、$F$の$\rho$への制限$F_\rho$について考える。
$F_\rho$は狭義単調増加であるため、$F_\rho[\rho]$の順序型は$\rho$である。また、$F_\rho[\rho] = F[\rho] = \sup\{F(\xi) \mid \xi < \rho\} \ge \alpha$なので、$F_\rho[\rho]$は$\alpha$上で非有界である。
任意の$\xi < \rho$について、$\sup\{F(\xi) \mid \xi < \gamma\} < \alpha$なので定義から$F(\xi) < \alpha$であり、従って$F_\rho[\rho] \subseteq \alpha$である。
以上により、$\alpha$の非有界で順序型が$\rho$($|\alpha|$未満)な部分集合が得られたので、$\textrm{cf}(\alpha) \le \rho < |\alpha|$である。
$\sup\{F(\xi) \mid \xi < \gamma\} \ge \alpha$となる$\gamma < |\alpha|$が存在しない場合、$F$は狭義単調増加なので、$F[|\alpha|]$の順序型は$|\alpha|$である。また、仮定から明らかに$F[|\alpha|] \subseteq \alpha$である。
また、任意の$\xi < \alpha$について$\xi = f(f^{-1}(\xi)) \le F(f^{-1}(\xi)) < F(f^{-1}(\xi)+1)$であり、$F(f^{-1}(\xi)+1) \in F[|\alpha|]$なので、$F[|\alpha|]$は$\alpha$の非有界部分集合である。
以上により、$\alpha$の非有界で順序型が$|\alpha|$な部分集合が得られたので、$\textrm{cf}(\alpha) \le \rho = |\alpha|$である。
いずれにせよ$\textrm{cf}(\alpha) \le \rho \le |\alpha|$である。□
$\alpha$が正則である場合、$\alpha = \textrm{cf}(\alpha) \le |\alpha| \le \alpha$なので$|\alpha| = \alpha$となり、$\alpha$は基数となる。
後続基数は正則基数である。
証明
$\kappa$の後続基数$\kappa^+$に対して、順序型が$\textrm{cf}(\kappa^+)$である、非有界な部分集合$S$を1つ取る。また、$\textrm{cf}(\kappa^+)$から$S$への順序同型を$f$とおく。$\kappa^+$は、$\{f(\xi)\setminus (\bigcup_{\zeta < \xi} f(\zeta)) \mid \xi < \textrm{cf}(\kappa^+)\}$のような分割が存在する。分割した各$f(\xi)\setminus (\bigcup_{\zeta < \xi} f(\zeta))$は濃度が高々$\kappa$である。よって、$\kappa^+ \le |\kappa \times \textrm{cf}(\kappa^+)|$が成り立つ。
もし$\textrm{cf}(\kappa^+) < \kappa^+$であるとすると、$\textrm{cf}(\kappa^+) \le \kappa$なので$\kappa^+ \le |\kappa \times \textrm{cf}(\kappa^+)| \le |\kappa \times \kappa| = \kappa$となり矛盾する。
従って、$\textrm{cf}(\kappa^+) = \kappa^+$であり、$\kappa^+$は正則基数である。□
極限基数は正則なのか?という問いは少し難しい。大抵の場合極限基数は($\omega$を除き)正則ではない。更に言えば、正則な極限基数は弱到達不能基数とよばれており、これの存在は$ZFC$の無矛盾性を導ける。
この事実とゲーデルの不完全性定理などから、($ZFC$が無矛盾なら)$ZFC$から弱到達不能基数の存在が示せないことがわかる。
鳩の巣原理と共終数
共終数は正則であり、正則ならば基数なので、極限順序数の共終数は結局のところ基数である。
共終数を基数として見ると、実は組み合わせ論っぽい性質が出てくる。
「$m(n-1)+1$個の元をもつ有限集合を$m$個に分割すると、そのうち少なくとも1つは$n$個の元をもつ」という、鳩の巣原理の名で知られる定理があるが、共終数はこれの無限集合版のようなものを扱う際に自然に出てくる。
無限基数$\pi,\kappa(\kappa \le \pi)$に対して、$\kappa < \textrm{cf}(\pi)$であることと、$\pi$を$\kappa$個に分割するとそのうち少なくとも1つは$\pi$個の元をもつことは同値である。
証明
$\kappa < \textrm{cf}(\pi)$であるとする。任意の$\pi$の$\kappa$個の分割$\{A_\xi\}_{\xi < \kappa}$から、直和順序集合が得られる。これを$(A,\prec)$とおく。もちろん、$A$は(直和の定義の流儀によって$\pi$と等しかったり異なったりするが、)$\pi$との間に全単射が存在する。すなわち$|A|=\pi$である。
もし各$\xi < \kappa$について$|A_\xi| < \pi$であるとすると、$A_\xi$の順序型も$\pi$未満であり、また$\kappa < \textrm{cf}(\pi)$より濃度$\kappa$以下な$\pi$の部分集合$\{\textrm{type}(A_\xi) \mid \xi < \kappa\}$は$\kappa$の有界集合である。ここで上限を$\sigma$とおく。
$(A,\prec)$は順序型が$\sigma$以下な整列集合の$\kappa$個の直和による順序集合であったため、順序型は$\sigma \times \kappa$以下であり、特に$\sigma,\kappa < \pi$なので$\sigma \times \kappa < \pi$である。これは$|A| = \pi$であることに矛盾する。
従って、$|A_\xi| = \pi$を満たす$\xi < \kappa$が存在する。□
逆に$\kappa \ge \textrm{cf}(\pi)$であるとする。まず、順序型が$\textrm{cf}(\pi)$であるような$\pi$の非有界部分集合$S$が存在する。
$\textrm{cf}(\pi)$から$S$への一意な順序同型を$f$とおくと、$\{f(\xi)\setminus (\bigcup_{\zeta < \xi} f(\zeta)) \mid \xi < \textrm{cf}(\pi)\}$は$\pi$の分割である。各$f(\xi)\setminus (\bigcup_{\zeta < \xi} f(\zeta))$は$f(\xi)$の部分集合であり、$f(\xi) < \pi$であること、$\pi$が基数であることから、$\{f(\xi)\setminus (\bigcup_{\zeta < \xi} f(\zeta)) \mid \xi < \textrm{cf}(\pi)\}$は$\pi$の$\textrm{cf}(\pi)$個の分割であり、それぞれは$\pi$未満個しか元をもたない。
仮定の$\kappa \ge \textrm{cf}(\pi)$により、分割$\{f(\xi)\setminus (\bigcup_{\zeta < \xi} f(\zeta)) \mid \xi < \textrm{cf}(\pi)\}$から更に$\kappa$個の異なる一元集合を付け足したりしてやることで、$\pi$の$\kappa$個の分割であり、それぞれは$\pi$未満個しか元をもたないものを得られる。□
ということで、基数$\pi$の共終数とは、「濃度$\pi$の集合を濃度$\pi$未満に分割したとき、取りうる分割数のうち最小のもの」と定義することもできる。
また、ここから$\kappa$が正則基数であるとは、「濃度$\kappa$の集合を分割した場合、分割数、あるいは分割した集合のうちいずれかの濃度が$\kappa$となる」ということと同値になる。
多分この性質が組み合わせ論的にとても嬉しいんじゃないかな...。
デカい集合を、性質の近いやつらが同じグループに属するようにあんまりデカくない個数に分割して、そのうち1つは元々から大きさが変わらないから、「デカい集合からデカくて性質の良い集合が必ず取れる」みたいな保証がされる嬉しさ。
1. ほとんど交わらない集合族、向日葵(交わりが一定の集合族)
組み合わせ論の最も簡単な例として、集合の分割を扱った。集合の分割とは、結局のところ異なる2つの集合が互いに交わらないような集合族である。
この概念の拡張のうち、1節では2種類を扱っている。(厳密な話をすると前者は拡張ではないけど、交わり方を指定するタイプの集合族なので結構近いものなんじゃないかな...。)
ほとんど交わらない集合族
$\kappa$を無限基数とする。$\kappa$の部分集合の族$A$が、濃度$\kappa$の集合しか持たず、更に任意の異なる2つの集合$x,y \in A(x \neq y)$について$|x \cap y| < \kappa$を満たすとき、$A$は$\kappa$のほとんど交わらない集合族であるという。
通常の交わらない集合族は、異なる2集合の共通部分$x \cap y$が空、つまり濃度が$0$でなければならなかった。今回は集合族に属する各集合の濃度が全体集合$\kappa$と等しい代わりに、$x \cap y$の濃度は$\kappa$未満であればよい。
$\kappa$の分割(交わらない集合族)は、濃度が高々$\kappa$である。
では、ほとんど交わらない集合族ならどうなのか?というのが気になってくる。少なくとも、$\kappa \times \kappa$から$\kappa$への全単射を使えば$\kappa$を$\kappa$個の濃度$\kappa$の集合に分割できるので、これは濃度$\kappa$なほとんど交わらない集合族である。
$A$が$\kappa$のほとんど交わらない集合族であり、なおかつどんな濃度$\kappa$な部分集合$x\subseteq \kappa$についても$A \cup \{x\}$が$\kappa$のほとんど交わらない集合族にならないとき、$A$は$\kappa$の極大なほとんど交わらない集合族、あるいはm.a.d.集合族であるという。
$\kappa$を正則基数として、$A$を$\kappa$のほとんど交わらない集合族であり、$|A| = \kappa$であるとする。このとき、$A$は極大ではない。
証明
具体的に$|x| = \kappa$を満たす$x \subseteq \kappa$を持ってきて、$A \cup \{x\}$がほとんど交わらない集合族となることを示せばいい。仮定より$\kappa$から$A$への全単射が存在する。そのうち1つを$f$とする。
各$\xi,\zeta < \kappa$について、$\zeta < \xi$ならば$f(\xi) \neq f(\zeta)$であり、$f(\xi),f(\zeta)$は$\kappa$のほとんど交わらない集合族$A$に属するので$|f(\xi) \cap f(\zeta)| < \kappa$である。
各$\xi < \kappa$について、$f(\xi) \cap (\bigcup_{\zeta < \xi} f(\zeta)) = \bigcup_{\zeta < \xi}(f(\xi) \cap f(\zeta))$である。各$f(\xi)\cap f(\zeta)$の濃度が$\kappa$未満であり、それら$\xi(<\kappa)$個の和を取っただけなので、もしこれが濃度$\kappa$となると$\kappa$の正則性と矛盾する。従って$f(\xi) \cap (\bigcup_{\zeta < \xi} f(\zeta))$の濃度は$\kappa$未満である。
特に、$f(\xi) \in A$より$f(\xi)$の濃度は$\kappa$なので、濃度の比較によって$f(\xi) \setminus (\bigcup_{\zeta < \xi} f(\zeta))$は常に空でないことがわかる。
ここで、$x := \{\min(f(\xi) \setminus (\bigcup_{\zeta < \xi} f(\zeta))) \mid \xi < \kappa\}$とおく。
各$\alpha,\beta < \kappa$について、$\alpha < \beta$ならば、$\min(f(\alpha) \setminus (\bigcup_{\zeta < \alpha} f(\zeta))) \in f(\alpha)$だが$\min(f(\beta) \setminus (\bigcup_{\zeta < \beta} f(\zeta))) \in f(\alpha)$なので$\min(f(\alpha) \setminus (\bigcup_{\zeta < \alpha} f(\zeta))) \neq \min(f(\beta) \setminus (\bigcup_{\zeta < \beta} f(\zeta)))$である。これにより、$x$の濃度が$\kappa$であることがわかる。
また、任意の$\alpha < \kappa$について、$f(\alpha) \cap x \subseteq \{\min(f(\xi) \setminus (\bigcup_{\zeta < \xi} f(\zeta))) \mid \xi \le \alpha\}$なので、$f(\alpha) \cap x$の濃度は$\alpha$の濃度以下であり、すなわち$\kappa$未満である。
以上により、$A \cup \{x\}$がほとんど交わらない集合族であるため、$A$は極大でない。□
$\kappa$が正則基数のときは、まず濃度$\kappa$のほとんど交わらない集合族を取ってきて、そこからこの定理と超限再帰で濃度が$\kappa^+$になるまで元を1つずつ付け足すことで、濃度が$\kappa^+$以上のほとんど交わらない集合族が得られる。
ところで、$\kappa$の部分集合の族の中で濃度が最大のものは、$\kappa$の冪集合$P(\kappa)$であり、濃度は$2^\kappa$である。一般連続体仮説などがなければ、$\kappa^+$と$2^\kappa$が等しいかはわからないので、「濃度が$2^\kappa$であるような$\kappa$のほとんど交わらない集合族が存在するのか?」という疑問はまだ解消されていない。
実は、$\kappa$にある条件を課せば、($\kappa$が正則基数でなくとも)濃度が$2^\kappa$であるような$\kappa$のほとんど交わらない集合族が得られる。それを今から示していく。
(条件を欠くと$ZFC$から独立らしく、また$\omega_1$すらその条件を満たすことも$ZFC$から独立らしいので、実際のところ$ZFC$からはほとんど何も言えないのだが。)
$\kappa$を無限基数とし、「$\kappa$の有界部分集合全体の濃度が$\kappa$である」とする。このとき、$\kappa$のほとんど交わらない集合族で、濃度が$2^\kappa$であるものが存在する。
証明
まず、$\kappa$の有界な部分集合全体を$I$とおく。$\kappa$と$I$は濃度が等しいので、$I$の濃度$2^\kappa$なほとんど交わらない部分集合さえ作ってしまえばいい。$\kappa$の濃度$\kappa$な部分集合は$2^\kappa$個存在する。この集合を$U$とおく。$U$から$P(I)$への写像$A$を、$A_x := \{x \cap \xi \mid \xi < \kappa\}$として定義する。
$A_x$に属する各集合$x \cap \xi$は$\xi < \kappa$なので$\kappa$の有界部分集合であり、$I$に属する。よって$A_x \subseteq I$なので値域は問題ない。
任意の$x \in U$について、各$\xi,\zeta \in x$に対し、$\xi < \zeta$ならば$\xi \notin x \cap \xi$で$\xi \in x \cap \zeta$なので$x \cap \xi \neq x \cap \zeta$となる。よって$A_x$には$x$の元と同じ個数だけ集合が入っている。$U$の定義から$|A_x| = |x| = \kappa$である。
また、$A$は単射である。任意の$x,y \in U$について、$\bigcup A_x = x,\ \bigcup A_y = y$なので、$A_x = A_y$ならば$x = y$となるからである。
これにより、集合族$\mathcal A := \{A_x \mid x \in U\}$は濃度が$U$と等しい、つまり$2^\kappa$であることがわかる。更にこれは$I$の濃度$\kappa$な部分集合の族である。
あとは、$\mathcal A$の異なる2元の交叉の濃度が$\kappa$未満であることを示せば、$I$の濃度$2^\kappa$なほとんど交わらない集合族となるので証明完了である。
任意の$x,y \in U$について、$x \neq y$ならば$x$か$y$のどちらかちょうど一方に属する順序数が存在するので、そのうち最小のものを$\mu$とおく。どちらでも問題ないが、今回は$\mu$が$x$に属していて$y$に属していないとする。
$A_y = \{y \cap \xi \mid \xi < \kappa\}$であり、$\mu \notin y$なので、$A_y$は$\mu$が属する集合を元にもたない。対して$A_x = \{x \cap \xi \mid \xi < \kappa\}$であるが、$x \cap \xi$に$\mu$が属さないためには$\mu \notin \xi$、つまり$\xi \le \mu$でなければならない。
従って、$A_x \cap A_y \subseteq \{x \cap \xi \mid \xi \le \mu\}$であり、この濃度は高々$\mu+1$なので$\kappa$未満である。
これで、$\mathcal A$の異なる2元の交叉の濃度が$\kappa$未満であることが示された。
$\mathcal A$は$I$の濃度$2^\kappa$なほとんど交わらない集合族である。□
向日葵
集合族が交わらないとは、異なる2つの元の共通部分が必ず空集合となることであった。ここから、異なる2つの元の共通部分が(空集合とは限らないが)いつでも等しい、という形に拡張できる。
集合族$A$に対してある集合$r$が存在して、属する任意の異なる2つの集合$x,y \in A(x \neq y)$について、$x \cap y = r$が成り立つとき、$A$は向日葵であるという。
(Kunenでは「交わりが一定の集合族」や「$\Delta$-システム」と呼ばれていた。最も一般的な呼び方は$\Delta$-システムだが、筆者の好みにより今回は向日葵と呼ばせてもらう。)
向日葵$A$の濃度が$2$以上であるとき、$r$は一意に定まる。(というか濃度が$2$以下の向日葵は面白くないので普通は考えない。)このとき$r$を$A$の根と呼ぶ。また$x \in A$のとき、$r \subseteq x$が成り立つ。$x \setminus r$を$A$における$x$の花弁とよぶ。
向日葵は、大きいものを作ろうと思えばいくらでも作れる。どちらかといえば、興味としては「集合族$A$があったとして、その部分$S \subseteq A$で向日葵となるものは作れるか?」という問いがある。
簡単な例として、濃度が$2$の集合族は全て向日葵である。なので濃度が$2$以上の集合族からは必ず部分として濃度が$2$の向日葵が取れてしまう。
しかし、一般の集合族から部分として濃度$3$以上の向日葵が取れるとは限らない。その中で、ある程度性質の良い集合族からは比較的大きい向日葵を部分として取れる、というのが次の定理である。
$\kappa$を非可算正則基数とする。
- $n$を自然数とする。$\mathcal A$が$|\mathcal A| = \kappa$を満たす$\kappa$の$n$元部分集合の族であるとする。このとき、$\mathcal S \subseteq \mathcal A$かつ$|\mathcal S| = \kappa$を満たす向日葵$\mathcal S$が存在する。
- $\mathcal A$が$|\mathcal A| = \kappa$を満たす$\kappa$の有限部分集合の族であるとする。このとき、$\mathcal S \subseteq \mathcal A$かつ$|\mathcal S| = \kappa$を満たす向日葵$\mathcal S$が存在する。
- $\mathcal A$が$|\mathcal A| = \kappa$を満たす有限集合の族であるとする。このとき、$\mathcal S \subseteq \mathcal A$かつ$|\mathcal S| = \kappa$を満たす向日葵$\mathcal S$が存在する。
証明
1.$n = 0$のとき、$\mathcal A \subseteq \{\emptyset\}$となるので$|\mathcal A| = \kappa$となることはない。
$n = 1$のとき、任意の異なる2集合$x,y \in \mathcal A(x \neq y)$について、$x,y$は$1$元集合なので$x \cap y = \emptyset$である。つまり、そもそも$\mathcal A$自身が$\emptyset$を根とする濃度$\kappa$の向日葵である。
以降は$n$についての帰納法によって示す。
まずは、各$\xi < \kappa$について、$\mathcal A_\xi$を$\{x \in \mathcal A \mid \min x = \xi\}$とおく。$|\mathcal A_\xi| = \kappa$となる$\xi < \kappa$が存在するかどうかで場合分けしよう。
そのような$\xi$が存在する場合、$\alpha$をそのうちの1つとして固定する。$\mathcal A_\alpha$に属する集合はそれぞれ$\alpha$を最小元とする$n$元集合なので、$\mathcal A' := \{x \setminus \{\alpha\} \mid x \in \mathcal A_\alpha\}$とすれば$\mathcal A'$は$\kappa$の$n-1$元部分集合の族であり、$|\mathcal A'| = \kappa$である。
帰納法の仮定から、$\mathcal S' \subseteq \mathcal A'$かつ$|\mathcal S'| = \kappa$を満たす向日葵$\mathcal S'$が存在する。この向日葵の根を$r$とおく。
ここで、$\mathcal S := \{x \cup \{\alpha\} \mid x \in \mathcal S'\}$とすると、$\mathcal S \subseteq \mathcal A_\alpha \subseteq \mathcal A$であり、更に$|\mathcal S| = |\mathcal S'| = \kappa$である。また、任意の$x,y \in \mathcal S$について、$x \neq y$ならば$x \setminus \{\alpha\} \neq y \setminus \{\alpha\}$なので$x \cap y = (x \setminus \{\alpha\} \cap y \setminus \{\alpha\}) \cup \{\alpha\} = r \cup \{\alpha\}$となる。
つまり、$\mathcal S$は$r \cup \{\alpha\}$を根とする向日葵である。定理の条件に合う具体的な向日葵の存在が示せた。
$|\mathcal A_\xi| = \kappa$となる$\xi < \kappa$が存在しない場合、今度は$\kappa$の正則性により(濃度$\kappa$未満の集合のみに分割するなら分割数は$\kappa$個にしなければならないので、)$\mathcal A_\xi \neq \emptyset$となる$\xi < \kappa$は$\kappa$個(つまり非有界に)存在する。
ここで、$\kappa$から$\mathcal A$への写像$f$を以下のように超限再帰的に定める。
$f(\xi)$は、$\sup_{\zeta < \xi}(\max f(\zeta))$より最小元が大きい$\mathcal A$の元とする。(超限回取るには選択公理が必要である。一応選択公理なしで取る方法もあるがめんどいのでやめとく。)
$\sup_{\zeta < \xi}(\max f(\zeta))$は、$\kappa$未満の順序数の$\kappa$未満個の上限なので、$\kappa$の正則性からこれは$\kappa$未満である。$\mathcal A_\mu \neq \emptyset$となる$\mu < \kappa$は非有界なので、$\sup_{\zeta < \xi}(\max f(\zeta))$より最小元が大きい$\mathcal A$の元が必ず取れることに注意せよ。
任意の$\alpha,\beta < \kappa$について、$\alpha < \beta$であるとすると、定義から$f(\alpha)$の最大元より$f(\beta)$の最小元の方が大きいので$f(\alpha) \cap f(\beta) = \emptyset$である。
以上により、$\{f(\xi) \mid \xi < \kappa\}$は$\mathcal A$の部分であり、交わらない集合族(根が$\emptyset$な向日葵)である。明らかに$f$は単射なので、$|\{f(\xi) \mid \xi < \kappa\}| = \kappa$である。$\{f(\xi) \mid \xi < \kappa\}$は定理の条件に合う向日葵である。
どちらの場合も、帰納法の仮定から条件に合う向日葵の存在が示せた。帰納法により、任意の自然数$n$について、$\mathcal A$が$|\mathcal A| = \kappa$を満たす$\kappa$の$n$元部分集合の族であるならば、$\mathcal S \subseteq \mathcal A$かつ$|\mathcal S| = \kappa$を満たす向日葵$\mathcal S$が存在する。□
2.
集合族$\mathcal A$を高々可算個に分割する。具体的には、$\mathcal A$に属する$n$元集合全体を$\mathcal A_n$として分割$\{\mathcal A_n\}_{n < \omega}$を得る。$\kappa$は非可算なので$\omega < \kappa$であり、正則なので濃度$\kappa$の集合を$\omega$個に分割すると少なくとも1つは濃度が$\kappa$となる。
$|\mathcal A_n| = \kappa$を満たす$n$のうち最小のものを$m$とおく。1. より、$\mathcal S \subseteq \mathcal A_m( \subseteq \mathcal A)$かつ$|\mathcal S| = \kappa$を満たす向日葵$\mathcal S$が存在する。□
3.
集合族$\mathcal A$が$\kappa$の部分集合であるとは限らないが、$\bigcup \mathcal A$は有限集合の$\kappa$個の和なので濃度が高々$\kappa$である。つまり$\bigcup \mathcal A$から$\kappa$への単射が存在するので、それを元に$\mathcal A$を$\kappa$の有限部分集合に変換できる。
2. によりそこから濃度$\kappa$な部分向日葵が得られるので、あとは単射によって引き戻せば$\mathcal A$の部分であり濃度$\kappa$な向日葵が得られる。□
今回は有限部分集合の族のみを考えたが、一般に濃度が一定の基数未満な集合の族から大きい向日葵が取れるかという問いが考えられる。ある程度の仮定は必要だが、同様の定理が成り立つ。上の定理は下の定理で$\kappa = \omega$とした場合にすぎない。
$\kappa$を無限基数、$\theta$を正則基数とし、$\kappa < \theta$であり、更に「任意の$\alpha < \theta$について、$\alpha$の濃度$\kappa$未満な部分集合は$\theta$個より少ない」が成り立つとする。
このとき、任意の$\theta$の部分集合族$\mathcal A$について、$|\mathcal A| = \theta$かつ任意の$x \in \mathcal A$について$|x| < \kappa$ならば、$\mathcal S \subseteq \mathcal A$かつ$|\mathcal B| = \theta$を満たす向日葵$\mathcal S$が存在する。
証明
まず、集合族$\mathcal A$を$\kappa$以下の個数に分割する。具体的に言えば、$\mathcal A_\xi$を$\mathcal A$に属する集合のうち順序型が$\xi$のものとすることで、$\{\mathcal A_\xi \mid \xi < \kappa\}$のように分割する。高々$\kappa(< \theta)$個の分割なので、$\theta$の正則性によりいずれかの$\xi < \kappa$について$|\mathcal A_\xi| = \theta$である。このうち最小の(でなくてもいいので1つ固定した)ものを$\rho$とおく。
もし$\mathcal A_\rho$に属する任意の集合が、ある$\alpha < \kappa$を上界にもつ場合、$\mathcal A_\rho$は$\alpha$の濃度$\kappa$未満な部分集合しか元に持たないので、仮定より$|\mathcal A_\rho| < \theta$となってしまい矛盾する。
よって、$\mathcal A_\rho$の各集合の共通上界は存在しない。特に、$\bigcup\mathcal A_\rho$は$\theta$で非有界である。
各$x \in \mathcal A_\rho$と$\xi < \rho$について、$x(\xi)$を$\mathcal x$の$\xi$番目の元とする。
各$\xi < \rho$について$\{x(\xi) \mid x \in \mathcal A_\rho\}$が有界(濃度が$\theta$未満)であるとすると、$\{\{x(\xi) \mid x \in \mathcal A_\rho\} \mid \xi < \rho\}$は濃度$\theta$な集合$\bigcup \mathcal A_\rho$の、分割した集合の各濃度も分割数も$\theta$未満な分割となってしまう。
これは$\theta$の正則性に矛盾するので、$\{x(\xi) \mid x \in \mathcal A_\rho\}$が非有界となる$\xi < \rho$が存在する。そのような順序数を$\xi_0$とおく。
逆に言えば、任意の$\xi < \xi_0$について$\{x(\xi) \mid x \in \mathcal A_\rho\}$は$\theta$で有界である。これらの$\xi_0 (< \theta)$個の和$\{x(\xi) \mid x \in \mathcal A_\rho \land \xi < \xi_0\}$も$\theta$で有界である。$\alpha_0 := \sup\{x(\xi) \mid x \in \mathcal A_\rho \land \xi < \xi_0\}+1$とおく。
さて、ざっくりお気持ちを言うと、$\mathcal A_\rho$に属する各集合は、$\xi_0$番目以上の元、つまり$\alpha_0$以上の元のうち最小のものをいくらでも大きくできる(ように$\alpha_0$や$\xi_0$を定義した)。
なので、まずは$\alpha_0$以上の元が交わらないように$\theta$個の$\mathcal A_\rho$を取ってこよう。
そのようにして得たものは$\alpha_0$未満の範囲で交わりが一定ではないが、そこから$\theta$の正則性でうまく間引く。
$\mathcal A_\rho$の元の列$\{x_\gamma\}_{\gamma < \theta}$を、以下のように超限再帰によって定義する。
$x_\gamma$は、$x_\gamma(\xi_0)$が$\alpha_0$よりも$\sup\{x_\zeta(\xi) \mid \zeta < \gamma \land \xi < \rho\}$よりも大きいものとして取る。(超限回取るためには素朴にやると選択公理が必要である。)
$\mathcal A_\rho$に属する集合は、$\xi_0$番目をいくらでも大きく取れることは確認済みであり、$\theta$の高々濃度が$|\gamma \times \rho| < \theta$の部分集合の上界$\sup\{x_\zeta(\xi) \mid \zeta < \gamma \land \xi < \rho\}$より大きく取ることも可能である。よってこの超限再帰は問題なく行える。
さて、任意の$\xi,\zeta < \theta$について、$\xi < \zeta$なので、$\sup x_\xi < x_\zeta(\xi_0)$なので、$x_\xi \cap x_\zeta$は$x_\zeta(\xi_0)$未満の元しか持たない。特に、$\alpha_0$未満の元しか持たない。
ここで$\mathcal A' := \{x_\xi \mid \xi < \theta\}$とおくと、$|\mathcal A'| = \theta$であり、$\mathcal A' \subseteq \mathcal A$である。また、$\mathcal A'$に属する任意の集合$x$について、$x \cap \alpha_0$は$\alpha_0$の濃度$\kappa$未満な部分集合となるので、$\{x \cap \alpha_0 \mid x \in \mathcal A'\}$の濃度は定理の仮定から$\theta$未満である。
更に、$\mathcal A'$の異なる2元の交叉は$\alpha_0$の部分集合である。
$\mathcal A'$に属する集合を$\alpha_0$との交叉によって分類することで、$\mathcal A'$を$\theta$未満個に分割できるので、$\theta$の正則性からこのうち濃度が$\theta$であるものが存在する。これを$\mathcal S$とおく。
$\mathcal S$の異なる2元$x,y \in \mathcal S$の交叉は常に$\alpha_0$の部分集合だが、$\mathcal S$は属する集合と$\alpha_0$の交叉が全て一致するように取ったので、$x \cap y = x \cap \alpha_0 = y \cap \alpha_0$である。つまり、交叉は常に一定なので、$\mathcal S$は向日葵である。
$|\mathcal S| = \theta$であり、$\mathcal S \subseteq \mathcal A' \subseteq \mathcal A_\rho \subseteq \mathcal A$なので、$\mathcal S$は定理の条件を満たす向日葵である。□
ここからすぐに、$\mathcal A$が$\theta$の部分集合族であるという条件は外せる。
とはいえ、「任意の$\alpha < \theta$について、$\alpha$の濃度$\kappa$未満な部分集合は$\theta$個より少ない」という言明自体が$ZFC$で真偽判定しづらく、$\kappa = \omega$のときぐらいしかまともに扱えないっぽい。
可算鎖条件
位相空間や前順序集合についての、モデル理論的に重要な性質として「可算鎖条件」というものがある。
前順序集合は2節でやるので、今回は1節に出てくる位相空間の可算鎖条件について述べる。
とても余談
厳密には反鎖の可算性についての条件なので、可算反鎖条件と呼ぶべきらしい。
newton beadsも元々はanti newton beadsが略されたものである。こちらは鎖の物理的な現象についてなのでシンパシーを感じる。
他にも発達障害を発達と略したり、否定語を省略することは結構あるが、マジで混乱するのでやめてほしい。
通常の鎖の可算性を述べたくなったらどうするんだ。
位相空間が可算鎖条件(c.c.c.)を満たすとは、互いに交わらない開集合の族は、濃度が高々可算であることである。
互いに交わらない開基の族の濃度が高々可算である、とも言い換えられる。
位相空間の有名な性質として、可分というものがある。これは、高々可算濃度な稠密部分集合が存在することである。可分空間の例として、実数$\mathbb R$やその有限個の直積、あるいは台集合がそもそも可算であるような空間である。(それぞれ、$\mathbb Q$やその有限個の直積、全体集合が可算な稠密部分集合となる。)
c.c.c.空間の具体例は、以下の定理からすぐわかる。
位相空間$(X,\mathcal O)$が可分であれば、c.c.c.を満たす。
証明
まず、可分なので$(X,\mathcal O)$の可算な稠密部分集合$D$が取れる。空でない開集合は必ず稠密部分集合と交わりをもつことに注意しよう。交わりのない開集合族$\mathcal O' \subseteq \mathcal O$は、各$O \in \mathcal O'$について$x \in O \cap D$が存在する。
ここで、$\mathcal O'$から$D$への写像$f$として、$f(O) \in O \cap D$となるものが(選択公理から)得られる。
この写像$f$は単射である。なぜなら、$O_0,O_1 \in \mathcal O'$について、$f(O_0) = f(O_1)$ならば、$f(O_0) \in O_0 \cap O_1$なので、$\mathcal O'$の異なる元は交叉が$\emptyset$となってしまうので$O_0 = O_1$となる必要があるからである。
つまり、$\mathcal O'$から$D$への単射が存在するので、$|\mathcal O'| \le |D| = \omega$である。
以上により、互いに交わらない開集合族の濃度は高々可算なので$(X,\mathcal O)$はc.c.c.を満たす。□
位相空間の性質が、直積によって保たれるかという疑問がある。
例えばコンパクト性やハウスドルフ性を持つ位相空間同士の直積は、コンパクト性やハウスドルフ性をもつ。
しかし、可分空間の直積は$2^{\aleph_0}$個までなら可分になるものの、$(2^{\aleph_0})^+$個では保たないらしい。
では、c.c.c.空間の直積はc.c.c.空間になるだろうか?これは$ZFC$から独立らしい。しかし、次が成り立つ。
位相空間の族$\{(X_i,\mathcal O_i)\}_{i \in I}$が、添字集合の任意の有限部分集合$r \subseteq I$について直積位相空間$\Pi_{i \in r}(X_i,\mathcal O_i)$がc.c.c.を満たすとする。
このとき、全体の直積位相空間$\Pi_{i \in I}(X_i,\mathcal O_i)$もc.c.c.を満たす。
証明
直積位相の定義に用いられる開基を用いて議論する。もし$\Pi_{i \in I}(X_i,\mathcal O_i)$がc.c.c.でないとすると、濃度が非可算な互いに交わらない開基の族が存在する。$\{O_\xi\}_{\xi < \omega_1}$のそのようなものの1つとする。
各$\xi < \omega_1$について、$O_\xi$はある有限集合$r_\xi \subseteq I$と$|r_\xi|$個の開集合の組$\{O_{\xi,i}\}_{i \in r_\xi}$を用いて$O_\xi = \Pi_{i \in r_\xi}O_{\xi,i} \times \Pi_{i \in I \setminus r_\xi} X_i$と表せる。
ここで、集合族$\{r_\xi \mid \xi < \omega_1\}$を考えると、これは濃度が$\omega_1$な有限集合の族なので、向日葵補題により$\mathcal S \subseteq \{r_\xi \mid \xi < \omega_1\}$かつ$|\mathcal S| = \omega_1$を満たす向日葵$\mathcal S$が存在する。
もし$r_\alpha,r_\beta \in \mathcal S$が$r_\alpha \cap r_\beta = \emptyset$を満たすとすると、$O_\alpha \cap O_\beta = \Pi_{i \in r_\alpha}O_{\alpha,i} \times \Pi_{i \in r_\beta}O_{\beta,i} \times \Pi_{i \in I \setminus (r_\alpha \cup r_\beta)} X_i \neq \emptyset$となり仮定に反する。
よって、$r_\alpha \cap r_\beta \neq \emptyset$である。つまり、$\mathcal S$の根は空でない。以降、$\mathcal S$の根を$r$とおく。$r$は有限集合である。
すると、任意の$r_\alpha,r_\beta \in \mathcal S$について、$O_\alpha \cap O_\beta = \Pi_{i \in r} (O_{\alpha,i} \cap O_{\beta,i}) \times \Pi_{i \in r_\alpha \setminus r}O_{\alpha,i} \times \Pi_{i \in r_\beta \setminus r}O_{\beta,i} \times \Pi_{i \in I \setminus (r_\alpha \cup r_\beta)} X_i$である。これが空となるためには$\Pi_{i \in r} (O_{\alpha,i} \cap O_{\beta,i}) = \Pi_{i \in r} O_{\alpha,i} \cap \Pi_{i \in r} O_{\beta,i} = \emptyset$でなければならない。
ここで、$|\{\xi < \omega_1 \mid r_\xi \in \mathcal S\}| = \omega_1$なので、$\{\Pi_{i \in r} O_{\xi,i} \mid \xi < \omega_1 \land r_\xi \in \mathcal S\}$は$\Pi_{i \in r}(X_i,\mathcal O_i)$の濃度が非可算な互いに交わらない開集合族である。
これは定理の仮定である、$\Pi_{i \in r}(X_i,\mathcal O_i)$がc.c.c.を満たすことに反する。
従って、$\Pi_{i \in I}(X_i,\mathcal O_i)$はc.c.c.を満たす。□
特に、台集合が可算な位相空間同士の有限直積はc.c.c.を満たすので、任意個の直積でもc.c.c.を満たす。特に、任意の基数$\kappa$について$\{0,1\}^\kappa$はc.c.c.を満たす。