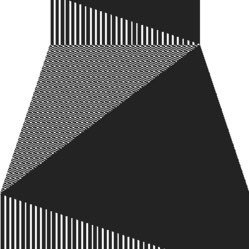無限集合メモ2
2. Martinの公理
この節ではMartinの公理を主に説明していく。Martinの公理は、小さい基数について成り立つ"ある性質"がどの基数まで成り立つか?という形で書かれている。
$ZFC$では、$\aleph_0$では成り立ち、$2^{\aleph_0}$では成り立たないことがわかっている。なので、連続体仮説から「$\aleph_0$まで成り立つ」ことが示せるが、連続体仮説が成り立たないときは$\aleph_0$から$2^{\aleph_0}$の間のどこまで成り立つかが疑問となってくる。
これが$2^{\aleph_0}$未満のどの基数でも成り立つというのがMartinの公理である。よって、Martinの公理は連続体仮説から示せて、疑問としては「連続体仮説の否定と両立するか」の部分である。
そんな感じで、連続体仮説より弱いが連続体仮説未満の基数に強い制限をかける公理、というイメージを持つとよさげかもしれない。
前順序の関連用語
集合$\mathbb P$とその上の二項関係$\le$の組$(\mathbb P,\le)$が、$\mathbb P \neq \emptyset$であり、任意の$x,y,z \in \mathbb P$について
- $x \le x$
- $x \le y \land y \le z\ \Rightarrow\ x \le z$
が成り立つとき、$(\mathbb P,\le)$を前順序集合とよぶ。更に、
- $x \le y \land y \le x\ \Rightarrow\ x = y$
が成り立つとき、$(\mathbb P,\le)$を半順序集合とよぶ。
前順序集合$(\mathbb P,\le)$、及び元$p,q \in \mathbb P$について、$p \le q$を「$p$は$q$を拡大する」と言ったりする。
部分集合$C \subseteq \mathbb P$が、任意の$p,q \in C$について$p \le q$または$q \le p$を満たすとき、$C$は$(\mathbb P,\le)$の鎖であるという。
$\mathbb P$の元$p,q \in \mathbb P$について、$r \le p$かつ$r \le q$を満たす$r \in \mathbb P$が存在するとき、$p,q$は$(\mathbb P,\le)$で両立するという。部分集合$A \subseteq \mathbb P$の任意の元$p,q \in A$について、$p,q$が両立しないとき、$A$は$(\mathbb P,\le)$の反鎖であるという。
半順序集合$(\mathbb P,\le)$が高々可算な反鎖しか持たないとき、$(\mathbb P,\le)$は可算鎖条件(c.c.c.)を満たすという。
(開集合族に集合の包含関係による順序を入れたものがc.c.c.を満たすということが、位相空間がc.c.c.を満たすということと同値となる。)
部分集合$D \subseteq \mathbb P$に対して、任意の$p \in \mathbb P$について$q \le p$を満たす$q \in D$が存在するとき、$D$は$(\mathbb P,\le)$の稠密集合であるという。
部分集合$G \subseteq \mathbb P$に対して、
- 任意の$p,q \in G$について、$r \le p$かつ$r \le q$を満たす$r \in G$が存在する
- 任意の$p \in \mathbb P$と$q \in G$について、$q \le p$ならば$p \in G$である
の2つを満たすとき、$G$は$(\mathbb P,\le)$のフィルターであるという。
ブール代数ちょろっと勉強して以降、多少は読みやすくなったものの、まだ用語の直感がさっぱり湧かないね。
Martinの公理
「
任意のc.c.c.を満たす前順序集合$(\mathbb P,\le)$について、$\mathcal D$を$(\mathbb P,\le)$の稠密部分集合の族であり、濃度が高々$\kappa$であるとする。
このとき、ある$(\mathbb P,\le)$のフィルター$G$が存在して、任意の$\mathcal D$に属する稠密集合と交わる。
」
この無限基数$\kappa$に関する命題を、$MA(\kappa)$と表す。
命題は$MA(\kappa)$は、濃度が$\kappa$以下の稠密部分集合に関する全称命題なので、$\kappa<\theta$ならば$MA(\theta) \Rightarrow MA(\kappa)$が成り立つ。
後に示すが、$ZFC$上で$MA(\omega)$が証明できて、$MA(2^\omega)$が反証できる。つまり、気になるのはその間の基数について成り立つかどうかである。
Martinの公理とは、任意の$\kappa<2^\omega$について$MA(\kappa)$が成り立つという命題である。
$MA(\kappa)$はある意味で$\kappa$の大きさを測る指標とも言えるので、Martinの公理は「連続体濃度未満の基数は指標$MA$目線で小さい」のような意味であると言える。
(とはいえ、Martinの公理が成り立つとしても$2^\omega$はかなり大きくなり得るらしいので、連続体濃度未満の基数も大きいものが存在し得る。)
$MA(\omega)$
証明
c.c.c.を満たす前順序集合$(\mathbb P,\le)$と、濃度が高々$\omega$な$(\mathbb P,\le)$の稠密部分集合の族$\mathcal D := \{D_i\}_{i < \omega}$を任意に取る。($\mathcal D$の濃度が有限なら、途中から$D_i$を全て等しくすればよい。)ここで、$\mathbb P$の元の列$\{p_i\}_{i < \omega}$を、以下のように再帰的に(選択公理を用いて)定義する。
$p_0$は$\mathbb P$の元として任意に取る。
$p_{i+1}$は、$\{p \in D_i \mid p \le p_i\}$の元として任意に取る。
各$i < \omega$について、$D_i$は稠密なので、既に定まった$p_i$に対して$p \le p_i$を満たす$D_i$の元$p$が取れる。つまり$\{p \in D_i \mid p \le p_i\}$は空でないので、この再帰的定義は問題なく行える。
さて、$G := \bigcup_{i < \omega} \{x \in \mathbb P \mid p_i \le x\}$とおく。
任意の$p \in G$と$q \in \mathbb P$について、$p \le q$とすると、$p \in \{x \in \mathbb P \mid p_i \le x\}$を満たす$i < \omega$が存在する。この$i$について、$p_i \le p$かつ$p \le q$なので$p_i \le q$であり、従って$q \in \{x \in \mathbb P \mid p_i \le x\} \subseteq G$である。
また、任意の$p,q \in G$について、先ほどと同様に$p_i \le p$となる$i < \omega$と$p_j \le q$となる$j < \omega$が存在する。定義から$\cdots \le p_2 \le p_1 \le p_0$なので、$p_{\max\{i,j\}} \le p_i \le p$かつ$p_{\max\{i,j\}} \le p_j \le q$である。また、$p_{\max\{i,j\}} \in G$である。
従って、$G$は$(\mathbb P,\le)$のフィルターである。
$G \cap D_i$の元として常に$p_{i+1}$が存在するので、任意の$D \in \mathcal D$について、$G \cap D$は空でない。つまり、$G$は$\mathcal D$に属する任意の稠密集合と交わるフィルターである。
以上により、$MA(\omega)$が成り立つ。□
$\lnot MA(2^\omega)$
証明
具体的な前順序集合として$\mathbb P$を「$\omega$の有限部分集合から$\{0,1\}$への関数(のグラフ)」として、前順序関係$p \le q$を$q \subseteq p$、つまり$q$が$p$の制限であることとして定義する。明らかにこれは前順序関係である。ここで、前順序集合$(\mathbb P,\le)$は、$\mathbb P$が可算集合$\omega \times \{0,1\}$の有限部分集合のみを元にもつなので可算となることから、c.c.c.を満たす。
$G$が$(\mathbb P,\le)$のフィルターであるとき、$\bigcup G$について考えよう。もし$(n,0),(n,1) \in \bigcup G$を満たす$n \in \omega$が存在するならば、ある$p,q \in G$について$(n,0) \in p$かつ$(n,1) \in q$となるが、すると$r \le p$かつ$r \le q$を満たす$r \in G$は存在しない。
(存在すれば$p \subseteq r$かつ$q \subseteq r$なので$(n,0),(n,1) \in r$だが、これは$r$が関数のグラフであることに反する。)
これは$G$がフィルターであることと矛盾するので、$(n,0),(n,1) \in \bigcup G$となることはない。
$\bigcup G \subseteq P(\omega \times \{0,1\})$が右一意性をもつことがわかったので、$G$がフィルターならば$\bigcup G$は定義域が$\omega$の部分集合である$\{0,1\}$への関数となる。
各$i < \omega$について、$\mathbb P$の部分集合$D_i$を、「定義域に$i$が含まれる$\mathbb P$の元全体」としよう。
このとき、任意の$p \in \mathbb P$について、$p$の定義域に$i$が含まれていたら$q := p$とし、そうでなければ$q := p \cup \{(i,0)\}$とすることで、常に$q \in D_i$かつ$q \le p$を満たす$q$が存在することになる。
つまり、$D_i$は稠密部分集合である。
各$f : \omega \to \{0,1\}$について、$\mathbb P$の部分集合$E_f$を、「$f$の制限ではない$\mathbb P$の元全体」としよう。
このとき、任意の$p \in \mathbb P$について、$p$がそもそも$f$の制限でなければ$q := p$とし、そうでなければ$p$の定義域外の最小の自然数$m$を用いて$q := p \cup \{(m,1-f(m))\}$とすることで、$q(m) = 1-f(m) \neq f(m)$となるので$q$は$f$の制限ではなく、よって$q \in D_i$かつ$q \le p$を満たす$q$が存在することになる。
つまり、$E_f$は稠密部分集合である。
もし$MA(2^\omega)$が成り立つとすると、$\{D_i \mid i < \omega\} \cup \{E_f \mid f : \omega \to \{0,1\}\}$は濃度が$2^\omega$な$(\mathbb P,\le)$の稠密部分集合の族なので、$(\mathbb P,\le)$がc.c.c.であることから$\{D_i \mid i < \omega\} \cup \{E_f \mid f : \omega \to \{0,1\}\}$に属するいずれの稠密集合とも交わる$(\mathbb P,\le)$のフィルター$G$が存在する。
さて、$\bigcup G$は$\omega$の部分集合を定義域とする$\{0,1\}$への関数であることはわかっていた。
任意の$i < \omega$について$G \cap D_i \neq \emptyset$なので、$p \in G \cap D_i$が存在する。$p \in D_i$なので、$(i,0) \in p$または$(i,1) \in p$である。($p$の定義域に$i$が含まれる。)
すると$p \subseteq \bigcup G$なので、$\bigcup G$の定義域にも$i$が含まれる。
任意の$i < \omega$について、$\bigcup G$の定義域に$i$が含まれるので、$\bigcup G$の定義域はちょうど$\omega$である。つまり、$\bigcup G$は$\omega$から$\{0,1\}$への関数である。これを$f$とおく。
$G \cap E_f \neq \emptyset$なので、$p \in G \cap E_f$が存在する。
定義から、$p$は$f$の制限ではないのだが、$p \in G$なので$p \subseteq \bigcup G = f$であり、$p$は$f$の制限である。矛盾した。
背理法により、$MA(2^\omega)$は偽である。□
ということで、$MA(\omega)$は成り立つものの$MA(2^\omega)$は成り立たない。
定理2のように構成した半順序集合の元のことを「条件」と呼ぶことがあるらしい。
なんとなくの直感だけど、半順序集合といいつつ主役はフィルター$G$であり、半順序集合に入ってる「何かのなり損ない」達を集めて束ねたフィルターを「ホンモノ」とみなしたいのだろう。
(実際、定理2では$\{0,1\}$から$\omega$への関数のなり損ない達を集めて半順序集合を作り、それらを集めたフィルターが全域関数になっていた。)
半順序集合の元(条件)は、フィルター$G$に入っていると、$G$と同一視される「ホンモノ」の性質をある程度定める。つまり、まさしく$G$(に対応するホンモノ)の条件付けをするのが半順序なのである。
注意として、このような半順序において、条件が強い方を小さい側として表す。論理学側において、命題間の「証明しやすさ」を表す順序から来てるっぽい。
稠密集合と交わるというのは、$G$が条件をもつというものより、もっと緩かったり多種多様な性質を表現できるのだろう。
という感覚をぼんやり浮かべつつ次へ進む。
ほとんど交わりをもたない集合を加える半順序
前の記事で、$\omega$のほとんど交わりをもたない部分集合の族のうち、濃度が$2^\omega$となるものが存在するとわかった。特に、ここからほとんど交わりをもたないように集合を加えていって極大にしても濃度は$2^\omega$のままなので、$\omega$の濃度$2^\omega$な極大ほとんど交わりをもたない集合族が存在する。
また、$\omega$のほとんど交わりをもたない集合族で濃度が$\omega$のものは、極大ではなく、新たに1つ$\omega$の部分集合を追加してほとんど交わりをもたないままにできる。
では、$\omega < \kappa < 2^\omega$のとき、$\omega$のほとんど交わりをもたない集合族で濃度が$\kappa$のものは、極大になり得るだろうか?
それを考えるために、$\omega$の部分集合の族$\mathcal A \subseteq P(\omega)$について、$\mathcal A$に属するいかなる集合ともほとんど交わりをもたない(交叉が有限である)集合を追加することについて考える。
そのときに有用っぽいが、以下のほとんど交わりをもたない集合を加える半順序とよばれるものである。
$\omega$の部分集合族$\mathcal A \subseteq P(\omega)$について、$\mathbb P_{\mathcal A}$を、$\omega$の有限部分集合と$\mathcal A$の有限部分集合の組全体の集合とし、
$\mathbb P_{\mathcal A}$上の二項関係$(s,F) \le_{\mathcal A} (s',F')$を「$s' \subseteq s$かつ$F' \subseteq F$かつ、任意の$x \in F'$について$x \cap s \subseteq s'$」と定義することで、組$(\mathbb P_{\mathcal A},\le_{\mathcal A})$が得られる。
任意の$(s_0,F_0),(s_1,F_1),(s_2,F_2) \in \mathbb P_{\mathcal A}$について、
- $s_0 \subseteq s_0$かつ$F_0 \subseteq F_0$かつ、任意の$x \in F_0$について$x \cap s_0 \subseteq s_0$なので、$(s_0,F_0) \le_{\mathcal A} (s_0,F_0)$
- $(s_0,F_0) \le_{\mathcal A} (s_1,F_1)$かつ$(s_1,F_1) \le_{\mathcal A} (s_2,F_2)$であるとすると、$s_2 \subseteq s_1 \subseteq s_0$かつ$F_2 \subseteq F_1 \subseteq F_0$であり、任意の$x \in F_2 \subseteq F_1$について$x \cap s_0 \subseteq s_1$かつ$x \cap s_1 \subseteq s_2$なので、$x \cap s_0 = x \cap x \cap s_0 \subseteq x \cap s_1 \subseteq s_2$である。従って$(s_0,F_0) \le_{\mathcal A} (s_2,F_2)$
- $(s_0,F_0) \le_{\mathcal A} (s_1,F_1)$かつ$(s_1,F_1) \le_{\mathcal A} (s_0,F_0)$であるとすると、$s_0 \subseteq s_1 \subseteq s_0$かつ$F_0 \subseteq F_1 \subseteq F_0$なので$(s_0,F_0) = (s_1,F_1)$
となるので$(\mathbb P_{\mathcal A},\le_{\mathcal A})$は半順序集合である。
と、このように定義した半順序について、稠密集合やらフィルターやらを考えていくわけだが、Kunenを見た感じこの半順序におけるフィルター$G$に対して、
$d_G := \bigcup\{s \mid \exists F\ ((s,F) \in G)\}$のようにして定義される$\omega$の部分集合と同一視したいようだ。
なんらかの部分集合$d \subseteq \omega$に対して、条件$(s,F)$は「$s \subseteq d$かつ、任意の$x \in F$について$x \cap d \subseteq s$」を表したいようだ。
「$(s,F)$がフィルター$G$に入ってる」と「$d_G$が条件$(s,F)$を満たす」が対応するように色々作りたくて、そのためにあのなんだかよくわからない順序$\le_{\mathcal A}$が使われている。
$(s,F) \le_{\mathcal A} (s',F')$は「$s' \subseteq s$かつ$F' \subseteq F$かつ、任意の$x \in F'$について$x \cap s \subseteq s'$」であるが、こうすると「$d_G$が条件$(s,F)$を満たすならば条件$(s',F')$も満たす」となってくれて嬉しいらしい。
お気持ちはこの辺にして、具体的な命題を示すことで性質を見ていく。
$\mathbb P_{\mathcal A}$の元$(s_0,F_0),(s_1,F_1)$が両立するのは、
「任意の$x \in F_0$について$x \cap s_1 \subseteq s_0$であり、任意の$x \in F_1$について$x \cap s_0 \subseteq s_1$である」ことと同値
成り立つ場合、$(s_0 \cup s_1,F_0 \cup F_1)$が両者の拡大となる。
証明
$(s_0,F_0),(s_1,F_1)$が両立する、つまり$(s,F) \le_{\mathcal A} (s_0,F_0)$かつ$(s,F) \le_{\mathcal A} (s_1,F_1)$を満たす$(s,F)$が存在することは、定義から「$s_0 \subseteq s$かつ$F_0 \subseteq F$かつ、任意の$x \in F_0$について$x \cap s \subseteq s_0$」かつ、「$s_1 \subseteq s$かつ$F_1 \subseteq F$かつ、任意の$x \in F_1$について$x \cap s \subseteq s_1$」を満たす$(s,F)$が存在することと同値である。
このとき、任意の$x \in F_0$について$x \cap s_1 \subseteq x \cap s \subseteq s_0$であり、同様に任意の$x \in F_1$について$x \cap s_0 \subseteq x \cap s \subseteq s_1$である。
逆に「任意の$x \in F_0$について$x \cap s_1 \subseteq s_0$であり、任意の$x \in F_1$について$x \cap s_0 \subseteq s_1$である」場合、$(s,F) := (s_0 \cup s_1, F_0 \cup F_1)$としよう。
「$s_0 \subseteq s = s_0 \cup s_1$かつ$F_0 \subseteq F = F_0 \cup F_1$かつ、任意の$x \in F_0$について$x \cap s = x \cap (s_0 \cup s_1) = (x \cap s_0) \cup (x \cap s_1) \subseteq s_0$」であり、同様に「$s_1 \subseteq s$かつ$F_1 \subseteq F$かつ、任意の$x \in F_1$について$x \cap s \subseteq s_1$」であるため、$(s_0,F_0),(s_1,F_1)$は両立する。
$(s_0 \cup s_1, F_0 \cup F_1)$は確認した通り両者の拡大である。□
$\mathbb P_{\mathcal A}$のフィルター$G$、条件$(s,F) \in G$について、$d_G := \bigcup \{t \mid \exists X ((t,X) \in G)\}$とおくと、
任意の$x \in F$について$x \cap d_G \subseteq s$となる。
証明
$x \cap d_G = x \cap \bigcup \{t \mid \exists X ((t,X) \in G)\} = \bigcup \{t \cap x \mid \exists X ((t,X) \in G)\}$なので、$x \cap d_G$を示すには、任意の$\exists X ((t,X) \in G)$を満たす$t$について$t \cap x \subseteq s$を示せばいい。そのような$t$について、$(t,X) \in G$を満たす$X$が存在する。$G$はフィルターなので、$G$の任意の2元は両立する(し、共通の拡大で$G$に属するものが存在する)。
つまり$(s,F)$と$(t,X)$は両立するわけだが、ここから補題3を使えば任意の$x \in F$について$x \cap t \subseteq s$であることがわかる。□
先ほどのお気持ちがしっかりと反映されてそうだ。
さて、フィルターについて色々言及したものの、マーティンの公理を活かすには稠密部分集合が必要である。
$\mathcal A$の元である$\omega$の部分集合$x$に対し、$D_x := \{(s,F) \mid x \in F\}$とする。
任意の$x \in \mathcal A$について、$D_x$は$(\mathbb P_{\mathcal A},\le_{\mathcal A})$の稠密な部分集合である。
証明
任意の$(s,F) \in \mathbb P_{\mathcal A}$について、明らかに$(s,F \cup \{x\}) \in D_x$である。あとは$(s,F \cup \{x\}) \le_{\mathcal A} (s,F)$であることを示せば十分である。とはいえこれも、$s \subseteq s$、$F \subseteq F \cup \{x\}$であり、任意の$y \in F$について$y \cap s \subseteq s$となるので定義から直ちに従う。□
$G$をフィルターとし、$x \in \mathbb P_{\mathcal A}$とする。$G \cap D_x \neq \emptyset$ならば、$x \cap d_G$は有限集合である。
証明
$G \cap D_x \neq \emptyset$なので、元$(s,F)$が存在する。$(s,F) \in D_x$なので、$D_x$の定義から$x \in F$である。また、$(s,F) \in G$なので、補題4から$x \cap d_G \subseteq s$である。$s$は有限集合なので、$x \cap d_G$も有限集合である。□
$(\mathbb P_{\mathcal A},\le_{\mathcal A})$はc.c.c.な半順序集合である。
証明
補題3を見るとすぐにわかるが、$(s,F),(s,F') \in \mathbb P_{\mathcal A}$は両立する。よって、$(s,F),(s',F') \in \mathbb P_{\mathcal A}$が両立しないためには$s \neq s'$でなければならない。ここで、$(\mathbb P_{\mathcal A},\le_{\mathcal A})$の反鎖を考えると、各元は両立しないので左成分がそれぞれ異なるのだが、左成分は$\omega$の有限部分集合なので高々可算種類しか存在しない。従って反鎖の濃度も高々可算である。□
補題7から$|\mathcal A| \le \kappa$であれば、$MA(\kappa)$によって、各$x \in \mathcal A$に対して(補題5により稠密な)$D_x$それぞれと交わりをもつようなフィルター$G$の存在が示せる。
こうして得たフィルター$G$は、補題6により任意の$x \in \mathcal A$について$x \cap d_G$が有限となる。
よって、元々$\mathcal A$がほとんど交わらない集合族だったら、新しく$d_G$を加えてもほとんど交わらない集合族となり、濃度$\kappa$以下である限りはほとんど交わらない集合族をどんどん大きくできる。
...果たして本当にそうだろうか?
「$\omega$のほとんど交わらない集合族」とは、いずれの異なる集合の共通部分も有限である、という条件の他に、そこに属する集合は全て無限集合でなければならない。ここで、果たして$d_G$が無限集合なのか?という問題が生まれる。
それを解決してくれるのが、次の定理である。
$\kappa < 2^\omega$を無限基数とし、$MA(\kappa)$を仮定する。$\mathcal A, \mathcal C \subseteq P(\omega)$とし、$|\mathcal A| \le \kappa,\ |\mathcal C| \le \kappa$とする。
更に、$\mathcal C$に属する$\omega$の部分集合$y \in \mathcal C$と、$\mathcal A$の有限部分集合$F \subseteq \mathcal A$について、$y\setminus \bigcup F$が常に無限集合であるとする。
このとき、$\omega$の部分集合$d \subseteq \omega$で、任意の$\mathcal A$の元との交わりが有限集合、任意の$\mathcal C$の元との交わりが無限集合、となるものが存在する。
証明
各$y \in \mathcal C,\ n < \omega$について、$E^y_n := \{(s,F) \in \mathbb P_{\mathcal A} \mid s \cap y \nsubseteq n\}$とおく。まずは$E^y_n$は稠密であることを示そう。任意の$(s,F) \in \mathbb P_{\mathcal A}$について、$F$は$\mathcal A$の有限部分集合なので、仮定より$y \setminus \bigcup F$は無限集合である。つまり、$y \setminus \bigcup F$に属する$n$より大きい元が存在する。
そのうちの1つを$m$とおき、$(s \cup \{m\},F)$について考えよう。$m \in (s \cup \{m\}) \cap y$かつ$m \notin n$なので$(s \cup \{m\}) \cap y \nsubseteq n$である。従って、$(s \cup \{m\},F) \in E^y_n$である。
更に、$s \subseteq s \cup \{m\}$かつ$F \subseteq F$かつ、任意の$x \in F$について($m \notin \bigcup F$より$m \notin x$なので)$(s \cup \{m\}) \cap x \subseteq s$であるため、$(s \cup \{m\},F) \le_{\mathcal A} (s,F)$である。
従って、$E^y_n$は稠密である。
$MA(\kappa)$が仮定されており、$\mathcal A,\mathcal C$の濃度は共に$\kappa$以下なので、稠密集合の族として$\{D_x \mid x \in \mathcal A\} \cup \{E^y_n \mid y \in \mathcal C \land n \in \omega\}$を取ると、この濃度は$\kappa$以下なのでそれら全てと交わりをもつフィルター$G$が存在する。
補題6により、各$x \in \mathcal A$について$D_x \cap G \neq \emptyset$なので、$x \cap d_G$は有限集合である。
また、各$y \in \mathcal C,\ n \in \omega$について、$(s,F) \in E_y^n \cap G$を満たす$(s,F)$が存在する。このとき$s \cap y \nsubseteq n$だが、$d_G$の定義から$s \subseteq d_G$なので、$d_G \cap y \nsubseteq n$である。特に、$d_G \cap y$は有界でないので、無限集合である。
以上により、$d_G$は$\mathcal A$の各元との交わりが有限であり、$\mathcal C$の各元との交わりが無限である。□
ここから、$\omega$のm.a.d.集合族の濃度についての定理が得られる。
$\kappa < 2^\omega$を無限基数とし、$MA(\kappa)$を仮定する。$\mathcal A \subseteq P(\omega)$とし、$\omega \le |\mathcal A| \le \kappa$とする。
このとき、$\mathcal A$が$\omega$のほとんど交わらない集合族ならば、極大ではない。
証明
$\mathcal C := \{\omega\}$とする。明らかに$|\mathcal C| \le \kappa$である。$\mathcal C$の任意に取った(としても一意になってしまうが)元$\omega \in \mathcal C$と、$\mathcal A$の任意に取った有限部分集合$F \subseteq \mathcal A$について、$\omega \setminus \bigcup F$が無限集合であることを示す。
$F$は有限集合で$\mathcal A$は無限集合なので、$\mathcal A \setminus F$は空でない。$x \in \mathcal A \setminus F$を1つ取る。
$x \in \mathcal A$であり、$\mathcal A$は$\omega$のほとんど交わらない集合族なので、$x$は無限集合である。
ところで、$x = x \cap \omega = x \cap (\bigcup F \cup (\omega \setminus \bigcup F)) = \bigcup \{x \cap y \mid y \in F\} \cup (x \cap (\omega \setminus \bigcup F))$であるが、各$y \in F$について$x \cap y$は有限集合であり、従って$\bigcup \{x \cap y \mid y \in F\}$は有限集合の有限和なので有限集合である。つまり、$x \cap (\omega \setminus \bigcup F)$は無限集合である。
以上により、$\omega \setminus \bigcup F$が無限集合であるとわかった。
ここから定理8を利用すると、各$\mathcal A$の元との交わりが有限集合であり、各$\mathcal C$の元、つまり$\omega$との交わりが無限集合であるような$\omega$の部分集合$d$が得られる。
$\mathcal A \cup \{x\}$は再び、$\omega$のほとんど交わらない集合族となる。従って$\mathcal A$は$\omega$のほとんど交わらない集合族のうち極大なものではない。□
他にも、定理8を用いることで冪集合の濃度についてある程度断定できる。
$\kappa < 2^\omega$を無限基数とし、$MA(\kappa)$を仮定する。このとき、$2^\kappa = 2^ \omega$が成り立つ。
証明
$\kappa$は無限基数なので$\omega \le \kappa$であり、よって$2^\omega \le 2^\kappa$である。あとは$2^\kappa \le 2^\omega$を示せばいい。$\omega$の有界な部分集合全体の濃度は$\omega$となる。無限集合メモ1の定理6より、$\omega$の濃度$2^\omega$なほとんど交わらない部分集合族が存在する。
特に、$\kappa < 2^\omega$なので、ここから適切に部分集合を取ることで濃度が$\kappa$なほとんど交わらない部分集合族が得られる。これを$\mathcal B$とおく。
(先ほどまでほとんど交わらない集合族の極大性について議論していたが、今回の$\mathcal B$は特に極大というわけではない。)
ここで、$\mathcal B$の部分集合$\mathcal A \subseteq \mathcal B$に対して、$\mathcal C := \mathcal B \setminus \mathcal A$として定義する。このとき$\mathcal B, \mathcal A, \mathcal C$の濃度は共に$\kappa$以下である。
任意の$y \in \mathcal C(= \mathcal B \setminus \mathcal A)$と任意の$\mathcal A$の有限部分集合$F \subseteq \mathcal A$について、定理9と全く同様にして$y \setminus \bigcup F$が無限集合となることが示される。
ここから定理8と$MA(\kappa)$により、$\omega$の部分集合$d \subseteq \omega$で、$\mathcal A$に属するどの集合とも交わりが有限で、$\mathcal C (= \mathcal B \setminus \mathcal A)$に属するどの集合とも交わりが無限であるようなものが存在する。
以上の議論によって、$\mathcal B$の部分集合$\mathcal A \subseteq \mathcal B$に対して、$\mathcal A$に属するどの集合とも交わりが有限で、$\mathcal B \setminus \mathcal A$に属するどの集合とも交わりが無限であるような$\omega$の部分集合1つを選ぶ写像$\Phi : P(\mathcal B) \to P(\omega)$の存在が示される。
任意の$\mathcal A, \mathcal A' \in P(\mathcal B)$について、$\mathcal A \neq \mathcal A'$とすると、$x \in \mathcal A \setminus \mathcal A'$(あるいは$x \in \mathcal A' \setminus \mathcal A$、こちらも同様の議論で示せるので省略)となる$x$が存在する。
$\Phi$の定義から、$\Phi(\mathcal A) \cap x$は有限集合であり、$\Phi(\mathcal A') \cap x$は無限集合であるため、$\Phi(\mathcal A) \neq \Phi(\mathcal A')$である。
従って、$\Phi$は単射である。
$P(\mathcal B)$の濃度は$2^\kappa$である。つまり、濃度$2^\kappa$の集合から濃度$2^\omega$の集合への単射が得られたので、
$2^\kappa \le 2^\omega$である。□
定理10の系として、連続体濃度の正則性が得られる。激アツ。
Martinの公理を仮定する。このとき、$2^\omega$は正則基数である。
証明
$\textrm{cf}(2^\omega) \le 2^\omega$である。あとは$\textrm{cf}(2^\omega) < 2^\omega$を否定すればいい。$\textrm{cf}(2^\omega) < 2^\omega$とする。$\kappa := \textrm{cf}(2^\omega)$とすると、Martinの公理(特に$MA(\kappa)$)と定理10より、$2^\omega = 2^\kappa$である。Konigの定理より、$\textrm{cf}(2^\omega) = \textrm{cf}(2^\kappa) > \kappa = \textrm{cf}(2^\omega)$となり矛盾する。□
もう1つ、定理8を応用して、$2^\omega$未満の濃度について性質を示せる。
$\mathbb R$の第一類集合は、定義から可算和を取っても第一類集合であるが、それより多くの和をとっても第一類になるのかという疑問が生まれる。
$\kappa < 2^\omega$を無限基数とし、$MA(\kappa)$を仮定する。このとき、$\mathbb R$の高々$\kappa$個の第一類集合の和集合は、再び第一類集合である。
証明
まず第一類集合とは、nowhere dense(閉包の内部が空集合)な集合の可算個の和で被覆される集合である。これは、内部が空な閉集合の可算個の和で被覆できる集合とも言い換えられる。第一類集合の高々$\kappa$個の和は、内部が空な閉集合の$\kappa$個の和で被覆される集合である。
つまり、内部が空な閉集合の$\kappa$個の和で表される集合は内部が空な可算個の和で表されることを示せばよい。
任意の高々濃度$\kappa$の「内部が空な閉集合」族$\{K_\alpha\}_{\alpha < \kappa}$について、ある高々可算濃度の「内部が空な閉集合」族$\{H_n\}_{n < \omega}$が存在して、$\bigcup_{\alpha < \kappa} K_\alpha \subseteq \bigcup_{n < \omega} H_n$が成り立つという主張である。
この主張を閉集合族を補集合を用いて言い換えると、(内部が空な閉集合の補集合は、稠密な開集合であるため、)任意の高々濃度$\kappa$の稠密開集合族$\{U_\alpha\}_{\alpha < \kappa}$について、ある高々可算濃度の稠密開集合族$\{V_n\}_{n < \omega}$が存在して、$\bigcap_{n < \omega} V_n \subseteq \bigcap_{\alpha < \kappa} U_\alpha$が成り立つという主張である。これを示していこう。
$\mathcal B$を、空でなく、両端が有理数であるような開区間全体とする。これは可算な$\mathbb R$の開基となる。適当に番号付けを行って、$\mathcal B := \{B_i \mid i < \omega\}$とおく。
ここから、与えられた稠密開集合族$\{U_\alpha\}_{\alpha < \kappa}$について、良い感じに部分集合$d \subseteq \omega$を選んで、$V_n = \bigcup \{B_i \mid i \in d \land i > n\}$として定義したい。ここからは良い感じの$d$を作る準備である。
自然数$j$に対して、$c_j := \{i \in \omega \mid B_i \subseteq B_j\}$とおく。$d \cap c_j$が無限集合であるならば、任意の自然数$n$に対して、$i > n$かつ$i \in d \cap c_j$(つまり$i \in d$かつ$B_i \subseteq B_j$)を満たす$i$が存在する。特に、この$i$について、$B_i \subseteq V_n \cap B_j$なので$V_n \cap B_j \neq \emptyset$である。
よって、もし任意の自然数$j \in \omega$について$c_j$が無限集合であるならば、任意の$n \in \omega$について、$V_n \cap B_j \neq \emptyset$である。$V_n$は任意の開基と交わるので稠密であり、$V_n = \bigcup \{B_i \mid i \in d \land i > n\}$は開基のみからなる和集合なので開集合である。つまり、$V_n$は稠密開集合である。
$\kappa$未満の各順序数$\alpha$について、$a_\alpha := \{i \in \omega \mid B_i \nsubseteq U_\alpha\}$とおく。$d \cap a_\alpha$が有限集合ならば、ある自然数$n$について$d \cap a_\alpha \subseteq n$となるので、任意の$i > n$について、$i \in d$ならば$i \notin a_\alpha$、つまり$B_i \subseteq U_\alpha$となる。
特に、$V_n = \bigcup \{B_i \mid i \in d \land i > n\} \subseteq U_\alpha$となる。
よって、もし任意の$\kappa$未満の順序数$\alpha$について$d \cap a_\alpha$が有限集合ならば、$\bigcap_{n < \omega} V_n \subseteq \bigcap_{\alpha < \kappa} U_\alpha$が成り立つ。
あとは、これらを実際に満たす$d \subseteq \omega$の存在を確かめられればよい。
$\omega$の部分集合族として、$\mathcal A := \{a_\alpha \mid \alpha < \kappa\},\ \mathcal C := \{c_n \mid n < \omega\}$とする。
ここで、任意の$\mathcal C$の元$c_j \in \mathcal C$、任意の$\mathcal A$の有限部分集合$F \subseteq \mathcal A$について、$\Delta := \{\alpha < \kappa \mid a_\alpha \in F\}$とおくと、$c_j \setminus \bigcup F = \{i \in \omega \mid B_i \subseteq (B_j \cap \bigcap_{\alpha \in \Delta} U_\alpha)\}$である。
$B_j \cap \bigcap_{\alpha \in \Delta} U_\alpha$は、各$U_\alpha$が稠密な開集合であることから、空でない開集合であることを帰納的に示せる。つまりある有理数$p,q \in \mathbb Q$について、$p < q$かつ$\{x \in \mathbb R \mid p < x < q\} \subseteq (B_j \cap \bigcap_{\alpha \in \Delta} U_\alpha)$を満たす。また、$p < r < q$を満たす$r \in \mathbb Q$は無限に存在し、それらは全て$\{x \in \mathbb R \mid p < x < r\} \subseteq (B_j \cap \bigcap_{\alpha \in \Delta} U_\alpha)$を満たす。
従って、$c_j \setminus \bigcup F = \{i \in \omega \mid B_i \subseteq (B_j \cap \bigcap_{\alpha \in \Delta} U_\alpha)\}$は無限集合となる。
定理8により、任意の$\mathcal A$の元との交わりが有限で、任意の$\mathcal C$の元との交わりが無限となる$d \subseteq \omega$が存在する。
ここで存在を示した$d$について$V_n = \bigcup \{B_i \mid i \in d \land i > n\}$とすれば、$\{V_n\}_{n \in \omega}$は稠密開集合の族であり、$\bigcap_{n < \omega} V_n \subseteq \bigcap_{\alpha < \kappa} U_\alpha$が成り立つ。□
ルベーグ測度と$MA(\kappa)$
ルベーグ測度は$\sigma$加法性を持っており、例えばルベーグ測度が$0$な$\mathbb R$の部分集合の可算和は、$\sigma$加法性から再びルベーグ測度が$0$となる。
ここで、ルベーグ測度が$0$な集合の$\kappa(< 2^\omega)$個の和が再びルベーグ測度$0$になるかという疑問が生まれる。
実はこれも、$MA(\kappa)$の帰結として得られる。マーティンの公理万歳!!
$\kappa < 2^\omega$を無限基数とし、$MA(\kappa)$を仮定する。このとき、ルベーグ測度が$0$な集合の高々$\kappa$個の和は再びルベーグ測度$0$となる。
証明
$\{M_\alpha\}_{\alpha < \kappa}$を、高々$\kappa$個のルベーグ測度が$0$な集合の族、$\mu$をルベーグ測度とする。任意の正の数$\varepsilon \in \mathbb R_+$に対して、$\mu(U) \le \varepsilon$かつ$\bigcup_{\alpha < \kappa} M_\alpha \subseteq U$を満たす開集合$U$の存在を示せばいい。
$\mathbb P_\varepsilon := \{p \subseteq \mathbb R \mid p \textrm{\ is\ open\ set}\ \land \mu(p) < \varepsilon\}$とし、$\mathbb P_\varepsilon$上の半順序$p \le q$を、$q \subseteq p$として定義する。(向きに注意。)
$p,q$が両立するとは、$p,q$に共通の拡大が存在することであるが、これは$\mu(p \cup q) < \varepsilon$であることに他ならない。
また、フィルターは最終的には開集合とみなしたい。正確に言うと、フィルター$G$に対して$U_G := \bigcup G$として開集合を定める。
$G$がフィルターならば、任意の$p,q \in G$に対して$r \le p$かつ$r \le q$(つまり$p \subseteq r$かつ$q \subseteq r$なので、$p \cup q \subseteq r$)を満たす$r \in G$が存在する。$r \in \mathbb P_\varepsilon$なので、$\mu(r) < \varepsilon$である。特に、$p \cup q \subseteq r$なので$\mu(p \cup q) \le \mu(r) < \varepsilon$であり、$p \cup q \in \mathbb P_\varepsilon$である。更に$r \le p \cup q$なので、$p \cup q \in G$である。従って、フィルターは2集合の和に閉じている。更に、部分集合にも閉じている。
よって、$G$は有限和集合に閉じている。また、任意の$G$の可算部分集合$A \subseteq G$について、$\mu$の$\sigma$-加法性から$\mu(\bigcup A) \le \varepsilon$となる。
$G$自体は可算ではないが、例えば区間長が$\varepsilon$未満で端点がどちらも有理数な開集合全体を$\mathcal B_\varepsilon$とすると、これは$\mathbb R$の可算な開基となる。勿論$G \cap \mathcal B_\varepsilon$も可算なので、$\bigcup(G \cap \mathcal B_\varepsilon) = \bigcup G$より$\mu(\bigcup G) \le \varepsilon$である。
$(\mathbb P_\varepsilon, \le)$がc.c.c.であることを示そう。
そのために、まず$\mathcal B$を端点がどちらも有理数である開区間全体の集合、$\mathcal C$を$\mathcal B$の元の有限和で表される集合全体とする。どちらも高々可算な集合である。
任意のルベーグ測度が有限な開集合$V$、正実数$\delta$について、$\mathcal B$は開基なのである$\mathcal B$の元の高々可算な族$\{B_i\}_{i \in \omega}$が存在して、$V = \bigcup_{i \in \omega} B_i$が成り立つ。特に、$\mu(V) = \sup_{n \in \omega} \mu(\bigcup_{i < n} B_i)$なので、$\mu(V \setminus \bigcup_{i < n} B_i) = \mu(V)-\mu(\bigcup_{i < n} B_i) < \delta$を満たす$n \in \omega$が存在する。
$\bigcup_{i < n} B_i \in \mathcal C$なので、任意のルベーグ測度有限な開集合$V$と正実数$\delta$に対して、$\mu(V \setminus C) < \delta$と$C \subseteq V$を満たす$C \in \mathcal C$が存在する。
$(\mathbb P_\varepsilon, \le)$の非可算な反鎖$\{p_\alpha\}_{\alpha < \omega_1}$が存在すると仮定して矛盾を導く。改めて確認すると、$p,q$が両立しないとは、$\mu(p \cup q) \ge \varepsilon$を満たすことである。
ここで、$\{p_\alpha\}_{\alpha < \omega_1}$は非可算なので、可算集合の可算和では表せない。特に、各正の有理数$\delta$について、$\{p_\alpha \mid \alpha < \omega_1 \land \mu(p_\alpha) \le \varepsilon-3\delta\}$が全て可算であるとすると、$\{p_\alpha \mid \alpha < \omega_1\}$が可算集合の可算和で表されてしまい矛盾する。従って、ある正の有理数$\delta$について、$\{p_\alpha \mid \alpha < \omega_1 \land \mu(p_\alpha) \le \varepsilon-3\delta\}$は可算である。以降はそのような$\delta$を固定して議論する。
任意の$\alpha < \omega_1$について、$\mu(p_\alpha \setminus C_\alpha) < \delta$かつ$C_\alpha \subseteq p_\alpha$となる$C_\alpha \in \mathcal C$が存在するので、それらを1つずつ取ることで$\mathcal C$の元の族$\{C_\alpha\}_{\alpha < \omega_1}$を得る。
任意の$p_\alpha,p_\beta \in \{p_\xi \mid \xi < \omega_1 \land \mu(p_\xi) \le \varepsilon-3\delta\}$について、$\alpha \neq \beta$ならば$p_\alpha$と$p_\beta$は両立できないので$\mu(p_\alpha \cup p_\beta) \ge \varepsilon$を満たす。また、$\mu(p_\alpha \cap p_\beta) \le \mu(p_\alpha) \le \varepsilon-3\delta$である。従って、$\mu((p_\alpha \setminus p_\beta) \cup (p_\beta \setminus p_\alpha)) = \mu(p_\alpha \cup p_\beta) - \mu(p_\alpha \cap p_\beta) \ge 3\delta$である。
また、$\mu(p_\alpha \setminus p_\beta) \le \mu(p_\alpha \setminus C_\beta) \le \mu(C_\alpha \setminus C_\beta) + \mu(p_\alpha \setminus C_\alpha) \le \mu(C_\alpha \setminus C_\beta) + \delta$であり、同様に$\mu(p_\beta \setminus p_\alpha) \le \mu(C_\beta \setminus C_\alpha)+\delta$なので、$3\delta \le \mu(C_\alpha \setminus C_\beta) + \mu(C_\beta \setminus C_\alpha) +2\delta$となり、従って$\delta \le \mu(C_\alpha \setminus C_\beta) + \mu(C_\beta \setminus C_\alpha)$である。
特に、$\mu(C_\alpha \setminus C_\beta)$か$\mu(C_\beta \setminus C_\alpha)$の少なくとも一方は正なので、$C_\alpha \setminus C_\beta \neq \emptyset$または$C_\beta \setminus C_\alpha \neq \emptyset$である。どちらにせよ、$C_\alpha \neq C_\beta$である。
今、非可算な集合$\{p_\xi \mid \xi < \omega_1 \land \mu(p_\xi) \le \varepsilon-3\delta\}$の異なる元$p_\alpha,p_\beta$について、$C_\alpha \neq C_\beta$であることが示されたが、これは$\mathcal C$が可算集合であることに矛盾する。
以上により、非可算な反鎖は存在しない。$(\mathbb P_\varepsilon, \le)$はc.c.c.である。
最初に取ったルベーグ測度が$0$な集合の族$\{M_\alpha\}_{\alpha < \kappa}$について、$D_\alpha := \{p \in \mathbb P_\varepsilon \mid M_\alpha \subseteq p\}$とする。最後にこれらが$(\mathbb P_\varepsilon, \le)$で稠密であることを示そう。
任意の$q \in \mathbb P_\varepsilon$について、$\mu(q) < \varepsilon$であり、更に$\varepsilon-\mu(q) > 0$と$\mu(M_\alpha) = 0$から、$M_\alpha \subseteq V$かつ$\mu(V) < \varepsilon-\mu(q)$を満たす開集合$V$が存在する。
このとき、$p := q \cup V$とすれば、$\mu(p) \le \mu(q) + \mu(V) < \varepsilon$なので$p \in \mathbb P_\varepsilon$であり、$M_\alpha \subseteq V \subseteq p$なので$p \in D_\alpha$であり、更に$p \subseteq q$なので$q \le p$である。
以上により、$D_\alpha$は$(\mathbb P_\varepsilon, \le)$で稠密である。
$MA(\kappa)$が仮定されているので、c.c.c.を満たす$(\mathbb P_\varepsilon, \le)$の高々濃度$\kappa$な稠密部分集合族$\{D_\alpha\}_{\alpha < \kappa}$に対し、それら全てと交わるフィルター$G$が存在する。
任意の$\alpha < \kappa$について、$D_\alpha \cap G$は空でないので元が存在する。つまり、$M_\alpha \subseteq p$を満たす$p \in G$が存在する。すると、$M_\alpha \subseteq p \subseteq \bigcup G = U_G$となる。
従って、任意の$\alpha < \kappa$について$M_\alpha \subseteq U_G$となるので、$\bigcup_{\alpha < \kappa} M_\alpha \subseteq U_G$である。
$G$は$(\mathbb P_\varepsilon, \le)$のフィルターなので、$U_G$はルベーグ測度$\varepsilon$以下の開集合である。□
位相空間論への応用
ここまで、ある意味で「小さい」$\mathbb R$の部分集合を、連続体濃度未満個だけ和を取っても、まだ「小さい」ままである。というような命題を示した。また、連続体濃度未満の濃度について、冪濃度がどうなるのかについても調べた。$\omega$の部分集合族についても調べた。
自然数の冪集合や実数は、多くの数学者が触れるので、ある程度性質が明らかになると嬉しいかもしれない。しかし、なにやら一般の半順序に反鎖やら稠密やらフィルターやらc.c.c.やら小難しい条件付けをした割には、扱う対象が$P(\omega)$や$\mathbb R$だけというのは少し味気ない。
一般論っぽい形の公理であるからには、もっと一般論っぽい定理を導いてやりたいものだ。
ということで、ここからは位相空間に対しての応用を見ていく。
以下の定理では、前提として、コンパクトハウスドルフ空間が正則空間であり、正則空間上の任意の点$x$とその開近傍$U$に対してある$x$の開近傍$V$が存在して、$\textrm{cl}(V) \subseteq U$を満たすということを用いる。
別分野の前提知識までフォローするのは流石に面倒だしMathpediaよりわかりやすい説明はできないので、この辺は各自で調べてほしい。
$\kappa < 2^\omega$を無限基数とし、$MA(\kappa)$を仮定する。$(X,\mathcal O)$を、c.c.c.を満たすコンパクトハウスドルフ空間とする。
このとき、高々濃度$\kappa$な稠密開集合族$\{U_\alpha\}_{\alpha < \kappa}$について、$\bigcap_{\alpha < \kappa} U_\alpha \neq \emptyset$である。
証明
$\mathbb P := \mathcal O \setminus \{\emptyset\}$とし、半順序集合$(\mathbb P,\subseteq)$を考える。$p,q \in \mathbb P$が$(\mathbb P,\subseteq)$で両立可能であるとは、$r \subseteq p$かつ$r \subseteq q$(つまり$r \subseteq p \cap q$)を満たす$r \in \mathbb P$が存在することである。$p \cap q \neq \emptyset$であれば$p \cap q \in \mathcal O \setminus \{\emptyset\} = \mathbb P$なので、両立可能であることは$p \cap q \neq \emptyset$と同値である。
また、$(\mathbb P,\subseteq)$のフィルター$G$に対して、$p,q \in G$ならば、$p \cap q \in G$である。
ここで閉集合族$\{\textrm{cl}(x) \mid x \in G\}$を考えると、任意の$G$の有限部分$\{p_i \mid i < n\} \subseteq G$について、帰納的に$\bigcap_{i < n} p_i \in G \subseteq \mathbb P$であることが示されるので、$\bigcap_{i < n} p_i \neq \emptyset$であり、更に$\bigcap_{i < n} \textrm{cl}(p_i) \neq \emptyset$である。つまり、閉集合族$\{\textrm{cl}(x) \mid x \in G\}$は有限交叉的である。
$(X,\mathcal O)$はコンパクト空間なので、$\bigcap \{\textrm{cl}(x) \mid x \in G\} \neq \emptyset$である。
(例のごとく、フィルターは最終的に何らかの対象とみなしたい。今回は$\bigcap \{\textrm{cl}(x) \mid x \in G\} \neq \emptyset$の1つの元とみなすのだが、今回は特にそれを強調しなくても議論が終わるので特に議論しないことにする。)
各$\alpha < \kappa$に対して、$D_\alpha := \{p \in \mathbb P \mid \textrm{cl}(p) \subseteq U_\alpha\}$と定める。
任意の$q \in \mathbb P$に対して、$U_\alpha$の稠密性から$q \cap U_\alpha \neq \emptyset$なので適当に$x \in q \cap U_\alpha$を取ると、$q \cap U_\alpha$は$x$の開近傍なので$p \subseteq \textrm{cl}(p) \subseteq q \cap U_\alpha$を満たす$x$の開近傍$p$が存在する。これは$p \in D_\alpha$を満たすので、$D_\alpha$は$(\mathbb P,\subseteq)$で稠密である。
$MA(\kappa)$により、高々濃度$\kappa$な$(\mathbb P,\subseteq)$の稠密部分集合族$\{D_\alpha\}_{\alpha < \kappa}$のいずれとも交わるフィルター$G$が存在する。
各$\alpha$に対して$p_\alpha \in G \cap D_\alpha$を満たす$p_\alpha$が存在し、$D_\alpha$の定義から$\textrm{cl}(p_\alpha) \subseteq U_\alpha$を満たす。よって、$\bigcap \{\textrm{cl}(x) \mid x \in G\} \subseteq \bigcap_{\alpha < \kappa} \textrm{cl}(p_\alpha) \subseteq \bigcap_{\alpha < \kappa} U_\alpha$であり、先ほど議論したように$\bigcap \{\textrm{cl}(x) \mid x \in G\} \neq \emptyset$なので、$\bigcap_{\alpha < \kappa} U_\alpha \neq \emptyset$である。□
実は定理14の逆も証明できるので、マーティンの公理はc.c.c.なコンパクトハウスドルフ空間の性質として言い換えられる。
こう見ると、空でない開集合全体の$\subseteq$-順序による反鎖が、互いに交わらない開集合族に対応しているので、位相空間と半順序のc.c.c.が関連づいてるのがわかる。ウレシイ。
この定理の$\kappa = \omega$でc.c.c.を満たさない場合が、いわゆるベールの範疇定理である。「では$\kappa > \omega$のときもc.c.c.を外せるのか?」という疑問が出てくるが、$\kappa = \omega_1$の時点で、順序数$\omega_1+1$に順序位相を入れた空間の$\omega$個の直積などが反例として見つかっている。
コンパクト性を局所コンパクト性に差し替えても定理14は成り立つらしい。
さて、マーティンの公理に出てくる半順序のc.c.c.性は、位相空間のc.c.c.性と密接に関わってくる。そして、実は$MA(\omega_1)$が成り立つとき、かなり面白いことが示せる。
($MA(\omega_1)$となるためには少なくとも連続体仮説$CH$は否定されないといけないことに注意しよう。)
$MA(\omega_1)$を仮定する。$(X,\mathcal O)$をc.c.c.な位相空間とし、$\{U_\alpha\}_{\alpha < \omega_1}$を非可算個の空でない開集合の族とする。
このとき、ある非可算な部分集合$A \subseteq \omega_1$が存在して、開集合族$\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$は有限交叉性をもつ。
証明
非可算個の空でない開集合の族$\{U_\alpha\}_{\alpha < \omega_1}$を用いて、各$\alpha < \omega_1$に対して$V_\alpha := \bigcup_{\alpha < \xi < \omega_1} U_\xi$とする。これらは開集合の和なのでいずれも開集合であり、任意の$\alpha < \beta < \omega_1$について、$V_\beta = \bigcup_{\beta < \xi < \omega_1} U_\xi \subseteq \bigcup_{\alpha < \xi < \omega_1} U_\xi = V_\alpha$である。従って、$\textrm{cl}(V_\beta) \subseteq \textrm{cl}(V_\alpha)$である。
ここで一度、$S \subseteq \omega_1$を、任意の$\beta < \alpha$について$\textrm{cl}(V_\alpha) \subsetneq \textrm{cl}(V_\beta)$を満たすような$\alpha < \omega_1$全体の集合とする。
もし$S$が非有界とすると、$\omega_1$は正則基数なので$S$の順序型は$\omega_1$である。従って、$S$の元を下から順に数え上げる順序同型写像$f : \omega_1 \to S$が一意に存在する。
各$\xi < \omega_1$について、$\textrm{cl}(V_{f(\xi+1)}) \subsetneq \textrm{cl}(V_{f(\xi)})$なので$\textrm{cl}(V_{f(\xi)}) \nsubseteq \textrm{cl}(V_{f(\xi+1)})$であり、特に$\textrm{cl}(V_{f(\xi+1)})$が閉集合だから$V_{f(\xi)} \nsubseteq \textrm{cl}(V_{f(\xi+1)})$となる。従って$V_{f(\xi)} \setminus \textrm{cl}(V_{f(\xi+1)}) \neq \emptyset$である。これは開集合となる。
異なる$\alpha,\beta \in \omega_1$について、もし$\alpha < \beta$ならば(順序が逆でも同様に議論せよ)$\alpha+1 \le \beta$より$f(\alpha+1) \le f(\beta)$、よって$V_{f(\beta)} \subseteq V_{f(\alpha+1)} \subseteq \textrm{cl}(V_{f(\alpha+1)})$なので、$(V_{f(\alpha)} \setminus \textrm{cl}(V_{f(\alpha+1)})) \cap (V_{f(\beta)} \setminus \textrm{cl}(V_{f(\beta+1)})) = \emptyset$である。これは、$\{V_{f(\xi)} \setminus \textrm{cl}(V_{f(\xi+1)})\}_{\xi < \omega_1}$が非可算個の互いに交わらない開集合の族であることを指すので、$(X,\mathcal O)$のc.c.c.性に反する。
以上により、$S$は有界である。
以降、$\sigma :=\sup S$とする。任意の$\alpha < \omega_1$について、超限帰納法により$\textrm{cl}(V_\sigma) \subseteq \textrm{cl}(V_\alpha)$が示せる。
ここで、$\mathbb P \:= \{p \in \mathcal O \setminus \{\emptyset\} \mid p \subseteq V_\sigma\}$とおき、半順序集合$(\mathbb P,\subseteq)$について考える。
定理14のときと同様に、$p,q \in \mathbb P$が$(\mathbb P,\subseteq)$で両立可能とは、$p \cap q \neq \emptyset$となることである。また、$G$がフィルターならば$G$は有限交叉性をもつ。
ここで、$A_G := \{\gamma < \omega_1 \mid \exists p \in G\ (p \subseteq U_\gamma)\}$とおくと、任意の$\alpha_0,\alpha_1,\cdots,\alpha_n \in A_G$について、$p_i \subseteq U_{\alpha_i}(i \le n)$を満たす$p_0,p_1,\cdots,p_n \in G$が存在し、$G$の有限交叉性から$\emptyset \neq \bigcap_{i \le n}p_i \subseteq \bigcap_{i \le n}U_{\alpha_i}$となるので、$\{U_\alpha \mid \alpha \in A_G\}$は有限交叉性を満たす。
あとは、このような$A_G$が非可算集合となるように良い感じのフィルター$G$を選んでやればいい。そのために、高々$\omega_1$個の稠密部分集合でフィルターの特徴を狭めていこう。
各$\alpha < \omega_1$について、$D_\alpha := \{p \in \mathbb P \mid \exists \xi(\alpha < \xi \land p \subseteq U_\xi)\}$と定める。
任意の$p \in \mathbb P$について、$\emptyset \neq p = p \cap V_\sigma \subseteq p \cap \textrm{cl}(V_\sigma) \subseteq p \cap \textrm{cl}(V_\alpha)$であり、$p$が開集合なので何らかの集合の閉包と交わるならばもとの集合とも交わる。従って$\bigcup_{\alpha < \xi < \omega_1}(p \cap U_\xi) = p \cap V_\alpha \neq \emptyset$である。
このとき、$p \cap U_\beta \neq \emptyset$を満たす$\alpha < \beta$が存在するが、$p \cap U_\beta \subseteq U_\beta$なので$p \cap U_\beta \in D_\alpha$であり、更に$p \cap U_\beta \subseteq p$である。従って、$D_\alpha$は$(\mathbb P,\subseteq)$の稠密部分集合である。
$MA(\omega_1)$により、高々濃度が$\omega_1$の稠密部分集合族$\{D_\alpha\}_{\alpha < \omega_1}$のいずれの元とも交わるフィルター$G$が存在する。
ここで、順序数$\alpha < \omega_1$を任意に取ると、$G \cap D_\alpha$は空でないので元$p$が存在する。$p \in D_\alpha$なので$\exists \xi(\alpha < \xi \land p \subseteq U_\xi)$である。この順序数$\xi > \alpha$について、$p \in G$と$A_G = \{\gamma < \omega_1 \mid \exists p \in G\ (p \subseteq U_\gamma)\}$より、$\xi \in A_G$である。
従って、$A_G$は$\omega_1$の非有界な部分集合なので、非可算集合である。先ほど示したように、$\{U_\alpha\}_{\alpha \in A_G}$は有限交叉性をもつ。□
ここから導かれる次の定理がとても重要である。
$MA(\omega_1)$を仮定する。c.c.c.を満たす2つの位相空間同士の直積も、再びc.c.c.を満たす。
証明
対偶を示す。位相空間$(X,\mathcal O),\ (X',\mathcal O')$について、その直積空間がc.c.c.を満たさないとする。$(X,\mathcal O)$がc.c.c.を満たさない場合は、仮定を否定するので証明完了である。
$(X,\mathcal O)$がc.c.c.を満たす場合は、直積空間がc.c.c.を満たさないので、直積空間には非可算個の互いに交わらない空でない開集合の族$\{W_\alpha\}_{\alpha < \omega_1}$が存在する。
これらは空でないため、$(X,\mathcal O),\ (X',\mathcal O')$の空でない開集合同士の直積集合をそれぞれ部分集合にもつ。各$\alpha < \omega_1$に対して、$W_\alpha \subseteq U_\alpha \times V_\alpha$となるように、$(X,\mathcal O)$の空でない開集合族$\{U_\alpha\}_{\alpha < \omega_1}$と$(X',\mathcal O')$の空でない開集合族$\{V_\alpha\}_{\alpha < \omega_1}$を選ぼう。
$(X,\mathcal O)$がc.c.c.を満たすので、$MA(\omega_1)$と補題15により、$\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$が有限交叉性を満たす非可算集合$A \subseteq \omega_1$が存在する。
任意の$\alpha,\beta \in A$について、$\alpha \neq \beta$とすると、$(U_\alpha \cap U_\beta) \times (V_\alpha \cap V_\beta) = (U_\alpha \times V_\alpha) \cap (U_\beta \times V_\beta) \subseteq W_\alpha \cap W_\beta = \emptyset$である。
ところで$\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$は有限交叉性を満たすので、$U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$である。従って、$V_\alpha \cap V_\beta = \emptyset$である。
つまり、$\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$は$(X',\mathcal O')$の非可算個の互いに交わらない開集合族となるので、$(X',\mathcal O')$はc.c.c.を満たさない。仮定の否定が示せた。□
$MA(\omega_1)$が成り立てば、この定理を帰納的に繰り返すことで、c.c.c.空間の任意有限個の直積が再びc.c.c.空間となる。
更に無限集合メモ1の定理10を組み合わせることで、任意個のc.c.c.空間の直積も再びc.c.c.空間となる。
非常に嬉しい。
マジで関係ない感想
定義を読んだ時点で、具体例とかざっくりとした挙動とかのイメージが湧くようになりたいという思想があるせいで、こういう半順序を見ては何度も引き返してきた。
でも実際に手を動かして、「ああ、こりゃ手を動かさないとわかんねえわ」となったので、みんなも無理に直感を生やそうとせずとりあえずガリガリ証明しよう。