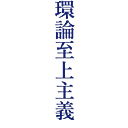【環論】一般の環に於ける有限次元性(お試し版)
一般の環に於ける有限次元性
多くの大学では初年度に体上の加群論を線型代数という科目名で教わることになる.この体上の加群論に於ける顕著な結果として必ず紹介されることの一つに「任意の体$\K$上の任意の片側$\K$-加群について$\K$-基底が存在することと,選択公理$\AC$が成り立つこととは$\ZF$上同値である」という命題と「任意の体$\K$上の任意の$\K$-加群$\M$について$\M$の$\K$-基底の濃度は一意的に定まる」という命題とがある.これにより体$\field$を固定するたびに$\K$-加群$\M$に対してその$\K$-基底の濃度を返すクラス函数$$\map{\rank{\field}{-}}{\Modcat{\K}}{\CN}$$が定義され,この定義を境にしてHamel次元$\rank{\field}{\M}$が有限な$\K$-加群に的を絞った議論を行いがちである.この「Hamel次元が有限な$\K$-加群」のことをしばしば有限次元$\K$-加群と呼ぶのであった.
線型代数で習う通り有限次元な線型空間は大変よい振舞いをするが,環論の視座に立てばその「行儀良さ」を切り取ってきて一般の環上の加群に関する命題に拡張できないだろうかと疑ってかかることは大変基本的である.これを実際に行なうためには,一般の環上の加群では同値ではないが体上の加群では有限次元性に潰れてしまうような性質群を考え,その性質を一つ一つ叮嚀に検討していくという営みが大切である.その営みの末に,体上の有限次元性の性質だと思われていた一連の結果が,立体的に浮かび上がってくるのである.
前口上とお断り
さて,風呂敷を広げすぎてしまったが,こういう問題意識の下で「体上の加群の有限次元性」は環論者によりある程度深く検討され,今では「有限次元性」は一般の環上の加群に対して定義されている.本稿ではこのあたりの話の基本的な事実を紹介する.詳しい証明については何れ某所か某サークルの機関紙あたりで書くのでご期待ください.
また,本稿は Math Advent Calender 2020 の9日目の記事として作成したのですが,あまり時間が取れず一晩で書いたため誤りも多分に含まれていると思います.少なくとも自己完結的ではないです(それゆえのお試し版です).もし誤りなどに気づかれた方はご指摘いただけると幸いです.
有限次元性
$\ring$を環とし,$\module$を左$\ring$-加群とする.このとき$\XX$が$\module$の独立部分加群系であるとは,
- $\XX$の任意の元は$\module$の部分加群である.
- $\XX$の任意の有限部分集合$\{ \N_1,\N_2,\ldots,\N_n \}$について$N_1\cap(N_2+\cdots+N_n)=\zeromod$が成立する.
を満たすことである.独立部分加群系$\XX$が与えられたとき,$\XX$の部分加群としての和$\sum\XX$は$\XX$の内部直和$\biguplus\XX$と一致することが重要である.
$\ring$を環とし,$\module$を左$\ring$-加群とする.このとき$\module$が有限次元であるとは,
- $\XX$が$\module$の独立部分加群系であるならば,$\XX$は有限集合である.
を満たすことである.特に独立部分加群系$\XX$の濃度は$\omega$まで確かめれば充分である.また独立部分加群系の定義内で述べた注意に留意すると,「加群の射$\map{f}{\bigoplus_{\alpha\in\kappa}\N_\alpha}{\module}$について,$f$がモノならば有限個の$\alpha$を除いて$\N_\alpha=\zeromod$である」と同値であり,このように記述する場合は$\kappa=\omega$まで確かめれば充分である.
$\ring$を環とし,$\module$を長さ有限加群とする.このとき加群の射$\map{f}{\bigoplus_{\alpha\in\omega}\N_\alpha}{\module}$について考えると,$f$がモノならば$(\biguplus_{i< n}\Im{f\circ\iota_i})_{n\in\omega}$は$\module$の部分加群の増大列であり,$\module$のNoether性よりこれは途中で止まる.よって有限個の$\alpha$を除いて$\N_\alpha=\zeromod$であることが分かった.
$\ring$を環とし,$\module$を長さ有限加群とする.このとき加群の射$\map{f}{\bigoplus_{\alpha\in\omega}\N_\alpha}{\module}$について考えると,$f$がモノならば$(\biguplus_{i\geq n}\Im{f\circ\iota_i})_{n\in\omega}$は$\module$の部分加群の減少列であり,$\module$のArtin性よりこれは途中で止まる.よって有限個の$\alpha$を除いて$\N_\alpha=\zeromod$であることが分かった.
$\field$を体とし,$\vectsp$を$\field$-線型空間とする.このとき$\vectsp$のHamle次元有限と$\field$-加群としての有限次元性は同値である.これは上の例からも分かる.
$\mathbb{Z}$-加群$\mathbb{Q}$について,$\N_1$,$\N_2$が非零部分加群であるならば$\N_1\cap\N_2\not=\zeromod$が成立する.実際,非零性より$\N_i$の元$n_i$を取ると,これらの分子の最小公倍数$n$は$n_i$に整数を書けることで表示できるため$n\in\N_1\cap\N_2$である.よって独立部分加群系の濃度は高々$1$であり,特に有限次元である.これはNoetherでもArtinでもない有限次元加群の例である.
これらの例に注意すると加群としての有限次元性はHamle次元の意味でのそれの一般化になっており,長さ有限性,Noether性,Artin性などの有限性に関する条件を含む概念である.
有限次元加群の基本的な性質(おはなし)
前節で有限次元加群の定義とその例を見た.このクラスの持つ性質を紹介するが,証明には幾つかの容易が必要なので詳細については某所での記事を待たれよ.
$\ring$を環とし,$\module$を左$\ring$-加群とする.このとき次が成立する.
- $\module$が有限次元であることと,$\module$の任意の部分加群が本質的有限生成であることは同値である.
- $\module$が有限次元であるならば,$\module$の部分加群$N$は有限次元である.
- $\module$が有限次元であるならば,$\module$の閉部分加群$N$による剰余$M/N$は有限次元である.
- $\module$が有限次元であるならば,$\module$の本質的拡大$L$は有限次元である.
ここで閉という用語が現れたが,これについては詳細を述べるには特異加群の概念を導入する必要がある.この一般論の紹介は別記事でまとめるべき分量があり,証明を諦めざるを得ない.次の命題は比較的用意すべき道具が少ないので証明してしまおう.
$\ring$を環とし,$\module$を左$\ring$-加群とする.このとき次が成立する.
- $\submod$を$\module$の部分加群とするとき,$\submod$および$\module/\submod$が有限次元ならば$\module$は有限次元である.
- $\module$が有限次元であるならば,$\module$の本質的拡大$L$は有限次元である.
二つ目は本質的拡大の定義に注意すれば容易であるから,一つ目を示そう.$\module$の可算独立部分加群系$\XX$を任意にとり,$\XX$の元を$\omega$で添え字付けて$\XX=\set{\submod_n}{n\in\omega}$.このとき先ず次を示そう:十分大きな$N$について,$\submod\cap\biguplus_{n>N}\submod_n=\zeromod$が成立する.実際,もしこれが成り立たないと仮定すると,次のように$\submod$の可算独立部分加群系が再帰的に構成でき,$\submod$の有限次元性に矛盾する:
先ずステップ$0$のときは,仮定より$\submod\cap\biguplus_{n\leq0}\submod_n$が零加群でないことに注意しこの加群の非零元$m_0$を取り,$m_0\in\submod\cap\biguplus_{n=0}^{n_1}\submod_n$なる$n_1$を取っておく.次にステップ$1$のときは,仮定より$\submod\cap\biguplus_{n\leq n_1+1}\submod_n$が零加群でないことに注意しこの加群の非零元$m_1$を取り,$m_1\in\submod\cap\biguplus_{n=n_1+1}^{n_2}\submod_n$なる$n_2$を取っておく.この操作は再帰的に続けることができ,$0< n_1< n_2<\cdots$なる正の整数の列が構成できる.このとき$X_i\colon=\submod\cap\biguplus_{n=n_i+1}^{n_{i+1}}$と置くと,$m_i\in X_i$が成立するので非零であり,集合$\set{X_i}{i\in\omega}$が$\submod$の可算独立部分加群系である.
よって$\submod\cap\biguplus_{n>N}\submod_n=\zeromod$なる正の整数$N$を取る.このとき$\module$から$\module/\submod$への標準的射影を$\biguplus_{n>N}\submod_n=\zeromod$に制限すると単射であり,よって$\module/\submod$の有限次元性より$\set{\submod_n}{n>N}$なる$\module$の部分集合系は有限個を除いて零加群であることが分かる.この個数を$m$と置けば$\XX$の非零部分加群は$m+n+1$で抑えられ,特に有限である.
$\ring$を環とし,$\module_1$,$\module_2$を左$\ring$-加群とする.このとき次が成立する.
- $\module_1$,$\module_2$が有限次元であることと直和$\module_1\oplus\module_2$が有限次元であることとは同値である.
この命題は有限次元加群が拡大で閉じていることと,部分で閉じていることとから従う.
$\ring$を環とるとき,正則左加群$\ring$が有限次元であることと有限生成射影左$\ring$-加群が有限次元であることとは同値である.
この命題は直和と直和因子について有限次元性が閉じていることとから従う.
$\ring_1$,$\ring_2$を環とるとき,$\ring_1$と$\ring_2$が森田同値ならば,$\ring_1$の正則左加群としての有限次元性と$\ring_2$の正則左加群としての有限次元性とは同値である.
この命題は先の特徴づけより従う.
$\ring$を環とし,$n$を正の整数とする.このとき$\ring$の正則左加群としての有限次元性と$\Matring{\ring}{n}$の正則左加群としての有限次元性とは同値である.
$\ring$と$\Matring{\ring}{n}$とは森田同値であるから,有限次元性が森田同値不変量たることより従う.
有限次元加群と閉部分加群(おはなし)
前節では有限次元加群の基本的な性質を紹介したが,剰余に関する性質を述べる時点で閉を仮定していた.有限次元加群と閉部分加群との関係は実はより深く,次のような特徴づけが知られている.
$\ring$を環とし,$\module$を左$\ring$-加群とする.このとき次は同値である.
- $\module$は有限次元である.
- $\module$は閉部分加群に関して昇鎖条件を満たす.
- $\module$は閉部分加群に関して降鎖条件を満たす.
この事実からもNoether性やArtin性の一般化であることが分かるし,閉部分加群の為す束の性質自体が興味深い対象であることが分かるが,ここではこれ以上触れない.
有限次元加群と一様加群(おはなし)
「有限次元加群」というからには加群に対して定義される何らかの量が有限であることとして特徴づけられて然るべきであるし,その量が有限次元線型空間の場合はHamel次元と一致していて欲しいものである.そのために有限次元性を定義する際に用いていた独立部分加群系の言葉を用いて「最小単位」を定義し,その最小単位の組み合わせが何らかの不変量になっているかを考察するという方法を考えてみよう.
$\ring$を環とし,$\module$を左$\ring$-加群とする.このとき$\module$が一様加群であるとは,
- $\module$の独立部分加群系の濃度は高々$1$である.
を満たすことである.より明示的に書けば「$\module$の非零部分加群$\submod_1$,$\submod_2$について,$\submod_1\cap\submod_2\not=\zeromod$が成立する」となり,これは「$\module$の非零部分加群は本質的部分加群である」と同値である.
既に見た通り$\mathbb{Z}$-加群としての$\mathbb{Q}$は一様加群であるし,整域上の非零イデアルは一様加群である.これは独立部分加群系が最も簡単なものしか取れないという意味で,この文脈での最小単位と考えられる.実際,次の命題が示すようにある意味で一様加群の個数が加群の大きさをはかる指標足りうる.
$\ring$を環とし,$\module$を左$\ring$-加群とする.更に一様部分加群$\submod_i$(ただし$i=1,\ldots,n$)が
$$\text{$\biguplus_{i=1}^n\submod_i$は$\module$の本質的部分加群である.}$$
を満たすと仮定する.このとき独立部分加群系$\XX$の濃度は高々$n$である.
$n$に関する数学的帰納法で示す.$n=0$のときは$\zeromod=\biguplus_{i=1}^n\submod_i$であり,零加群が本質的部分加群であるならば$\module$は零加群であるのでよい.$n=1$のときは,一様部分加群$A_1$が本質的部分加群であるから$\module$は一様加群であり,よって定義より独立部分加群系の濃度は高々$1$である.
$n>1$のときについて,$n$未満での成立を仮定する.いま$\module$は一様加群の有限直和の本質的拡大であるから,特に有限次元であることに注意する.$\X{1}\uplus\cdots\uplus\X{n+1}$なる$\module$の部分加群$\X{i}$について,$\X{i}=\zeromod$なる$i$が存在すれば示すことは何もない.よって$\X{1}\uplus\cdots\uplus\X{n+1}$なる$\module$の部分加群$\X{i}$であって$\X{i}\not=\zeromod$なる$i$が存在しない場合を考えよう.このとき$\X{}\colon=\X{1}\oplus\cdots\X{n}$について内部直和の定義より$\X{}\cap\X{n+1}=\zeromod$であり,$\X{n+1}$は零加群でない場合を考えているから$\X{}$は$\module$の本質的部分加群ではない.よって特に,$(\X{}\cap\submod_1)\uplus\cdots\uplus(\X{}\cap\submod_n)$は$\module$の本質的部分加群ではく,添え字を付けなおすことにより$\X{}\cap\submod_n$が$\submod_n$の本質的部分加群でないと仮定してよい.ここで$\submod_n$の一様性に注意すると$\X{}$は$\submod_n$と零元以外で交わらない.
入射包絡は本質的拡大の差が潰れること,入射包絡と直和とが交換することとに注意すると,$\module$の入射包絡$\injenv{\module}$について
$$\injenv{\module}\cong\injenv{\submod_1\uplus\cdots\uplus\submod_n}\cong\injenv{\submod_1\uplus\cdots\uplus\submod_{n-1}}\oplus\injenv{\submod_n}$$
が分かる(以下ではこの同型を通して三つを同一視する).また$\submod_n$が$\injenv{\submod_n}$の本質的部分加群であることより$\X{}\cap\injenv{\submod_n}=\zeromod$も成立する(ただし$\X{}$は入射包絡の構造射$\map{\iota}{\module}{\injenv{\module}}$に沿って埋め込んだものと同一視し,$\injenv{\submod_n}$も適切に$\injenv{\module}$の部分と同一視した.もちろん曵引と思っても構わないが,ここではより素朴に議論している).よって単射$\X{}\hookrightarrow\module\hookrightarrow\injenv{\module}$は$\injenv{\submod_1\uplus\cdots\uplus\submod_{n-1}}$を経由することが分かるが,これは帰納法の仮定に矛盾する.
この命題の仮定「$\submod_i$は一様加群である」「$\biguplus_{i=1}^n\submod_i$は$\module$の本質的部分加群である.」について,斯かる本質的部分加群が存在することは有限次元性と同値であることが次より分かる.ただし(そんなに難しくはないものの)次の補題を仮定する.
$\ring$を環とし,$\module$を左$\ring$-加群とする.このとき$\module$が有限次元ならば,$\module$の部分加群$\submod$に対してこれに含まれれる一様部分加群が存在する.
$\ring$を環とし,$\module$を左$\ring$-加群とする.このとき次は同値である.
- $\module$は有限次元である.
- $\module$は有限個の一様部分加群の直和の本質的拡大である.
(2)ならば(1)は一様加群の有限次元性と,有限次元加群が直和で閉じていることと,有限次元加群が本質的拡大で閉じていることとから従うので,既に示している.
(1)ならば(2)について,一様部分加群からなる独立部分加群系の中で極大なもの$\XX$を取る.このとき先の補題に注意すると,部分加群からなる独立部分加群系の中でも極大であり,よって内部直和$\biguplus\XX$は$\module$の本質的部分加群である(もしそうでなければ補部分加群が非零であり,それに含まれる一様部分加群を$\XX$に加えることで真に大きな極大部分加群系が構成できる).ここで有限次元性の定義より,$\XX$は有限集合であるから$\XX$が(2)の条件を満たす.
ここまでで,有限次元加群$\module$は本質的拡大の差を除けば有限個の一様部分加群によって組み上げることができ,この個数は$\module$にのみ依存することが示された.ここまでの観察を元に次のように一様次元を定義しよう.
$\ring$を環とし,$\module$を左$\ring$-加群とする.このとき
$$\sup{\set{\kappa\in\CN}{\text{$\module$の一様部分加群からなる独立部分加群系であって濃度が$\kappa$のものが存在する}}}$$
なる濃度を一様次元といい,$\udim{\module}$と書く.一様次元が$\omega$未満であることを一様次元有限という.
一様次元のことをGoldie次元やGoldie階数ともいう.一様次元有限と有限次元性は同値であるから,一様次元は有限次元性をより定量的にした概念であり,精密化といえる.
結び
以上で有限次元性が加群に対して定義され,大まかにどういった概念であるかを観察してきた.結びではこのあとはどのように理論展開が為されるかを少し紹介しておこう.まずHamel次元と一様次元とが一致し,Hamle次元に関する次元公式が一様次元についても成り立つことを確かめるのが基本的である.更に一様次元に関する議論は比較的精密に行えるため,正則左加群が有限次元ならば多項式環をとっても有限次元であることが確かめられる(全行列環を取る操作で有限次元性が保たれることに比べて証明は大変である).更に正則左加群が有限次元かつ右零化イデアルに関する昇鎖条件を満たす環としてGoldie環が定義され,次のGoldieの定理に至る.
$\ring$を環とするとき,次は同値である.
- $\ring$は半単純な左全商環を持つ.
- $\ring$は半素左Goldie環である.
- 右特異イデアルが自明であり,かつ本質的左イデアルの為す順序集合が単項左イデアルの為す順序集合と共終である.
$\ring$を環とするとき,次は同値である.
- $\ring$は単純Artinな左全商環を持つ.
- $\ring$は素左Goldie環である.
これらの主張は「古典的な非可換環論の金字塔的な結果」と称され,まさに非可換Noether環のイデアル論の基礎として確固たる地位を築いている.これらの理論の上に多くの理論が打ち立てられ,特別な加群たちの構造や,ひいては環の構造が調べられている.少しでも興味を持たれた方がいらっしゃれば是非とも次に挙げる参考文献を参照されることをお勧めしたく,手に取っていただける方が一人でもいれば大変うれしい限りである.
参考文献
本稿を書く上で直接的に参考にした文献,間接的に影響を与えている文献,参考文献をそれぞれ紹介します.
[1] K. R. Goodearl. Ring Theory -- Nonsingular Rings and Modules.
[2] 岩永恭雄,佐藤眞久.環と加群のホモロジー代数的理論.
[3] J. C. McConnell, J. C. Robson. Noncommutative Noetherian rings.
[4] サクラマス.非可換環の局所化.
環付サクラ空間
本稿の大まかな流れは[1]に依った.Goodearlは非可換Noether環論の有名な研究者の一人であり,本書は特異加群という視点で重要な結果をコンパクトにまとめている良書だと思う.[2]はより基本的な話題を扱っており,一部気になる点はあるものの環論の二冊目として最適だと思う.[3]は[2]を読んだ後により本格的に非可換Noether環のイデアル論を勉強する際に役に立つ辞書である.80年代前後に知られていた結果の多くが書かれており,かなり大部であるため適宜飛ばしつつ読みたいところを読むといいと思う.[4]は僕がB2のときに[2]を参考にして非可換環の局所化について某所で発表した際の資料であり,半素左Noether環は半単純な左全商環を持つことが証明されている他,幾つかの基本的な話題に触れている.このあたりの技術的な部分を含めて興味がある場合は,ウェブサイトで公開しているため参照されるとよいと思う.