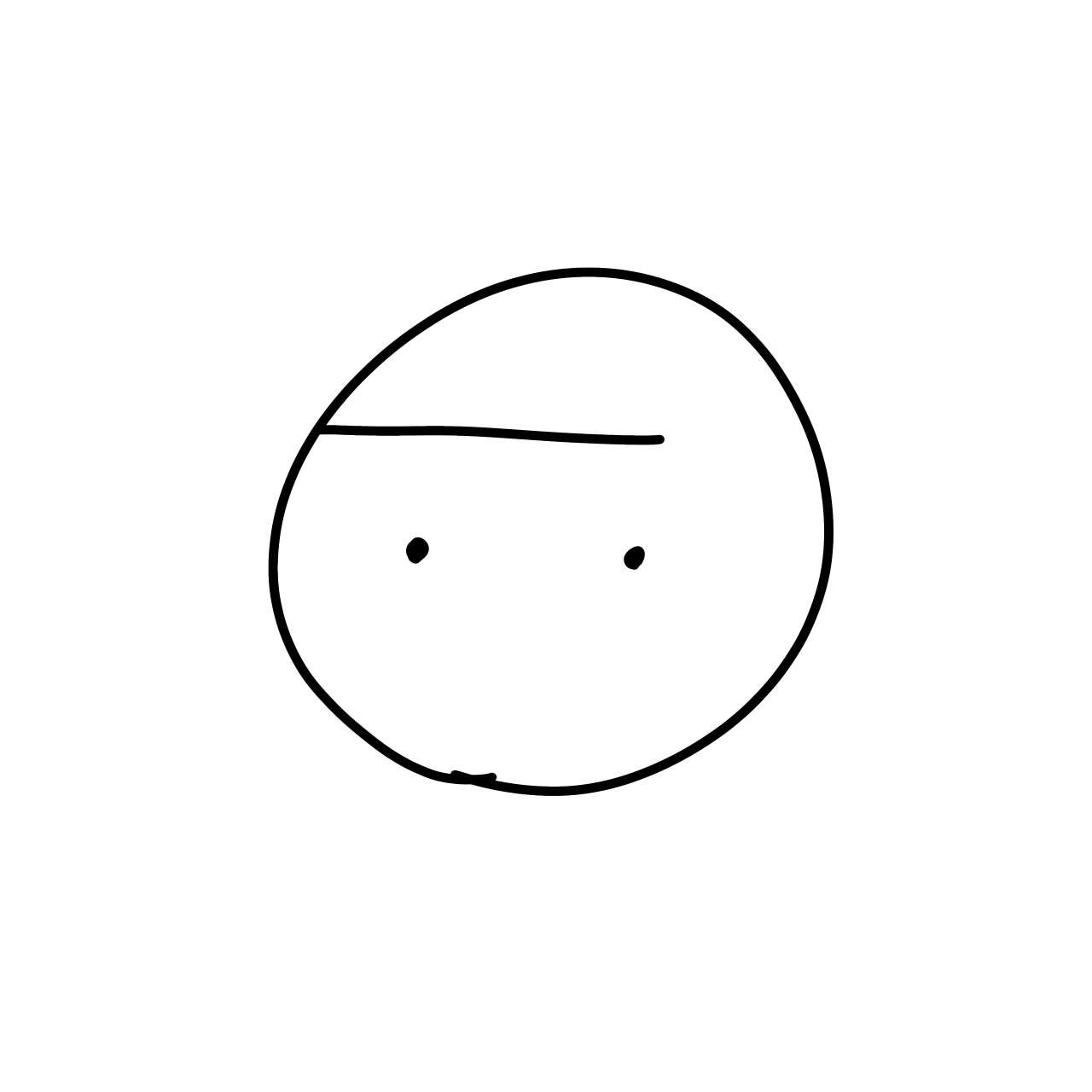モノイド環と準加算
導入
累乗は乗算を有限回繰り返したものである:
$$
x^y = \underbrace{x \cdot \cdots \cdot x}_{y \ \mathrm{times}}.
$$
また,乗算も加算を有限回繰り返したものである:
$$
x \cdot y = \underbrace{x + \cdots + x}_{y \ \mathrm{times}}.
$$
では,同様にして有限回繰り返すことで加算となるような演算(これを準加算という)は定義できるだろうか?
$$
x + y = \underbrace{x \oplus \cdots \oplus x}_{y \ \mathrm{times}}.
$$
準加算の概念はbutchi氏によって2016年に提唱された.その後様々なアイディアをもとに研究が進められていたが,現在は「整数上(特に自然数上)ではうまく定義できない」という結論に至っている.
本記事では,ある環に対してその加算よりも低レベルな演算をもつ代数構造としてモノイド環を導入し,演算がどのように備わっているかを考察する.
なお,演算は常に二項演算を表すものとする.また,上記のようにある演算$\gamma$が別の演算$\delta$を繰り返すことによって得られる場合,$\delta$は$\gamma$の下のレベルの演算であるという.例えば,整数環において$+$は$\cdot$の下のレベルの演算である.下のレベルであるかどうかについて,結合法則や可換法則などは考えない.
モノイド環
$M$をモノイド,$A$を環とする.このとき,
$$
A[M] := \left\{ \sum_{\mathrm{finite}} a_im_i \ \middle| \ a_i\in A, m_i \in M\right\}
$$
とする.この$A[M]$を$M$の$A$上のモノイド環という.
モノイド環の元はモノイドの元と環の元の形式的線形和であり,必ずしもなにか意味のある数になるとは限らない.
モノイド環は実際に環になっている:$f = \sum a_i m_i,g = \sum b_i m_i \in A[M]$に対して,
\begin{align}
f + g &= \sum_i (a_i + b_i)m_i\\
f\cdot g &= \sum_{i,j} \left(\sum_{k+l = i+j} a_k b_l\right)m_im_j
\end{align}
と演算が入っているが,$M$がモノイドであることから結合法則が成り立ち,分配法則が成り立つことも分かる(要計算).
今,$+$という演算は$A$および$A[M]$の和を表した.
モノイド環は半群環として一般化され,実際に半群に対しても同様に定義することができるが,本記事では最終的に構成された環が単位的可換環であるものを主に取り扱うため,ここではモノイド環を使用した.
$\nn$を自然数全体の集合(ただし$0\not\in\nn$),$\zz$を整数全体の集合とする.このとき$\nn$は通常の積に関してモノイドをなし,整数全体は通常の和と積に関して環となる.ここで
$$ \zz[\nn] = \left\{\sum_{\mathrm{finite}} a_in_i \ \middle| \ a_i \in \zz, n_i \in \nn\right\} \simeq \zz $$
となる.実際に$\phi: \zz[\nn] \to \zz$を$f = \sum a_in_i\in \zz[\nn]$に対して
$$
\phi(f) = \sum a_i n_i
$$
($n_i \in \zz$だと考える)と定義すると,これは環準同型である.
Claim: $\phi$は全単射である:
$\because)$(単射) $f \in \ker \phi$に対して
$$
\phi(f) = \sum a_i n_i = 0
$$
であるとき,すべての$i$で$a_i = 0$となる($\because 0 \not\in \nn$).したがって$f = 0$となり$\ker\phi=0$つまり$\phi$は単射となる.
(全射) 任意の$n\in\zz$に対し,$n \geq 0$であるならば$n = n\cdot1$となるので$\phi(1\cdot n) = n$である.また$n < 0$ならば$n = -1 \cdot -n$であるので$\phi(-1\cdot -n) = n$となり,$\phi$は全射である.
以上より$\phi$によって同型が定まる.
さて,この例は実は加算は乗算の下のレベルの演算であることを表している.
もともと$\nn$には乗算という単一の演算しか備わっていなかったが,そのモノイド環$\zz[\nn]$をあたえることによって加算という下のレベルの演算が新たに備わった.同型である$\zz$における積は$\nn$にもともとあった積だと考えることができる.
$$ \begin{array}{c|ccc} \mathrm{level} & \zz[\nn] \simeq \zz & & \nn \\ \hline 1 & \cdot_{\zz}& \leftarrow & \cdot_{\nn} \\ \hline 0 & +_{\zz} & & \varnothing \end{array} $$
そこに新しく$+$という演算が加わっており,実際に下のレベルの演算になっている.このようにして,あるモノイドが与えられたときにその$\zz$上のモノイド環を構成することによって,その下のレベルの演算をもつ代数構造を与えることができる.
$M$が可換モノイドである$\Leftrightarrow$$A[M]$は可換環である.
($\Rightarrow$) 積の定義より明らか.
($\Leftarrow$) 積を演算とするモノイドとして$M \subseteq A[M]$より成り立つ.$\square$
下段環
ここで,ある単位的可換環$A$について考える.$A$は和に関してアーベル群であり,また可換モノイドであるので,その$\zz$上のモノイド環を考えることができる.
単位的可換環$A$について
$$
L(A) := \zz[A]
$$
とし,これを$A$の自由下段環という.また,$L(A)$の剰余環を$A$の下段環という.
$\zz$を加算に関するモノイドと考えた上で$L(\zz)$について考える.新たに備わった演算を$\oplus$と$\odot$とする.
$$ \begin{array}{c|ccc} \mathrm{level} & L(\zz) & & \zz \\ \hline 1 & & & \cdot \\ \hline 0 & \odot & \sim & + \\ \hline -1 & \oplus& \end{array} $$
ただし$L(\zz)$の乗算$\odot$は$\zz$の加算$+$を$L(\zz)$に拡張したものである.
これではあまりにも形式的すぎるので,
$$
T := \left\{\underbrace{0\oplus\cdots\oplus0}_{2^n}\ominus n \ \middle| \ n \geq 0\right\}
$$
として下段環$B = L(\zz)/(T)$について考える.上式における$0$はより正確に書くと$1\cdot0$のことである.これは係数環としての$\zz$から$1$を,モノイドとしての$\zz$から$0$をそれぞれ取ってきたものの形式和である.$\ominus$は$\oplus$の逆演算であり,$B$は$L(\zz)$を
$$
0 \oplus 0 = 1
$$
より正確には
$$
(1\cdot0) \oplus (1\cdot0) = 1\cdot1
$$
などの関係式で剰余したものと考えることができる.この場合$1\oplus1$を計算してみると,
\begin{align}
1\oplus1&= 0\oplus0\oplus0\oplus0\\
&= 1\cdot2 \quad (= 2 \in \zz)
\end{align}
となっている.また,$1\odot1$は
\begin{align}
1\odot1&= (1\cdot1)\odot(1\cdot1)\\
&=(1\cdot1)\cdot(1+1)\\
&=1\cdot2 \quad(\ = 2 \in \zz)
\end{align}
より,
$$
0\oplus0\oplus0\oplus0 = 1\odot1 = 1 + 1 = 2
$$
となっているとみることができ,もともとあった加算$+$よりも下のレベルの演算$\oplus$が定義されていると考えることができる.
上の例では$L(\zz)$における線形結合の$\cdot$と,元から$\zz$に備わっている乗算$\cdot$の記号を濫用した.どれがどの$\cdot$かを正しく理解することは読者への課題とする.
より具体的な例をもう一つ提示する.$\ff_2$の下段環$C$を以下のように定める:
$$
C = L(\ff_2)/(0\oplus0\oplus0, 1\ominus(0\oplus0)).
$$
$C$の元は$0$と$1$の$\zz$上の線形結合でかけるはずであるが,実際には元は3つしかない.なぜならば,
\begin{align}
0 \cdot 0 &= 0 \cdot 1 \\
1 \cdot 0 & \\
2 \cdot 0 &= 0 \oplus 0 = 1\cdot1\\
3 \cdot 0 &= 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0\cdot0\\
2 \cdot 1 &= 1 \oplus 1 = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0\\
&= 1\cdot 0 \\
3 \cdot 1 &= 1 \oplus 1 \oplus 1\\
&= 0\oplus0\oplus0\oplus0\oplus0\oplus0 \\
&= 0\cdot0
\end{align}
となり,$0\cdot0, 1\cdot0, 2\cdot0$の3つだけとなる.
ここで,$f:C\to\ff_3$を
$$
f(0\cdot0) = 0, f(1\cdot0) = 1, f(2\cdot0) = 2
$$
と定めると,これは環の同型写像となり,つまり$C\simeq\ff_3$となる.このようにして$\ff_2$の下段環として$\ff_3$を考えることができるのである.
さて,ここで$\ff_3$の演算を見てみる.
\begin{equation} \begin{array}{c|ccc} + & 0 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0\\ 2 & 2 & 0 & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{c|ccc} \cdot & 0 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2\\ 2 & 0 & 2 & 1 \end{array} \end{equation}
このうち乗算の演算表に着目すると,単元群$\ff_3^\times$の部分は$\ff_2$の加算の演算表と同じになっていることが分かる.
\begin{equation} \begin{array}{c|cc} \cdot_{\ff_3} & 1 & 2 \\ \hline 1 & 1 & 2\\ 2 & 2 & 1 \end{array} \simeq \begin{array}{c|cc} +_{\ff_2} & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0 \end{array} \end{equation}
つまり,$\ff_3$の乗算を$\ff_2$の加算だと思うことができるということである.
\begin{equation} \begin{array}{c|cc} \mathrm{level} & \ff_2 & \ff_3 \\ \hline 1 & \cdot_{\ff_2} & \\ \hline 0 & +_{\ff_2} & \cdot_{\ff_3} \\ \hline -1 & & +_{\ff_3} \end{array} \end{equation}
これを定式化して構成したものが$C$である.
なお,下段環を構成することにより下のレベルの演算を定義することが出来たが,もとのモノイドの元にその演算を適用するとモノイドからはみ出してしまうことがある.
上記の$B$に関しては
$$
0\oplus0\oplus0
$$
に対応する$\zz$の元は存在せず,これで$B$の元を1つ表している.また上記の$C$に関しては$1\cdot0 \in C$は$0 \in \ff_2$と,$2\cdot0 \in C$は$1\in \ff_2$とそれぞれ対応しているが,$0\cdot0$に対応する$\ff_2$の元は存在しない.
\begin{equation} \begin{array}{c|ccc} \mathrm{level} & \ff_2 & & \ff_3 \\ \hline 1 & \cdot & & \\ \hline 0 & + & & \odot \\ \hline -1 & \underline{\oplus} & \dashleftarrow & \oplus \end{array} \end{equation}
実際に新しく定義した加算$\oplus$を$\ff_2$に引き戻して,$0\oplus1$を計算してみると,
\begin{align} 0\oplus1 &= (1\cdot0)\oplus(2\cdot0)\\ &= 0\cdot0 \not\in \ff_2 \end{align}
となり,$\ff_2$からはみ出してしまう.
つまり,低レベルな演算を定義する際にはある程度集合を拡大する必要がある.これは累乗を行う際に結合法則が成り立たなくなることなどに近い.