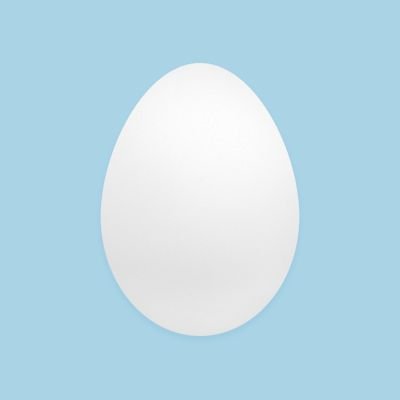大類昌俊氏の理論におけるノルム空間Xのある性質の不成立について
本記事の目的は, 大類昌俊氏 (Xアカウント:大類X1, 大類X2)のnote大類記事アーカイブの議論が誤っていることを証明することです.
大類の理論大類記事アーカイブが不成立であること
さて, 大類記事アーカイブの議論は大きく分けて前半と後半の2段階に分けられます:
- 大類氏が独自に定義したノルム空間$X$の性質に関する議論 (補題0, 1, 2, 3, 4)
- ノルム空間$X$の性質を用いたNavier-Stokes方程式の「初等的弱解」に関する議論 (補題5, 6, 7, 8, 9, 10)
このうち本記事では前半部分の議論が誤っていることを示します (なお後半部分の議論は前半部分に本質的に依存しています).
まず本記事で用いる記号の定義をまとめておきます.
- $\N$は非負の整数全体の集合とする.
- $I \coloneqq (0, 1)$とする.
- 関数$f \in C^0(I)$と指数$1 \leq p \leq \infty$に対し, その$L^p$ノルムを
\begin{equation} \norm{f}_{L^p} \coloneqq \begin{dcases} \left( \int_{0}^{1} \abs{f(x)}^p \, dx \right)^{1/p} , & 1 \leq p < \infty, \\ \sup_{x \in I} \abs{f(x)} , & p = \infty \end{dcases} \end{equation}
で定義する.
-関数$f \in C^m(I)$と$m \in \N$, $1 \leq p \leq \infty$に対し, 斉次Sobolevノルム$\norm{ f }_{\dot{W}^{m, p}}$と非斉次Sobolevノルム$\norm{ f }_{{W}^{m, p}}$をそれぞれ
\begin{align}
\norm{ f }_{\dot{W}^{m, p}} &\coloneqq \norm{f^{(m)}}_{L^p}, \\
\norm{ f }_{W^{m, p}} &\coloneqq \norm{f}_{L^p} + \norm{f^{(m)}}_{L^p}
\end{align}
で定義する. ただし$f^{(m)}$は$f$の$m$階微分である.
- 集合$S$を
\begin{equation} S \coloneqq [0, \infty)^\N = \set{(s_m)_{m \in \N}}{\forall m \in \N, s_m \in [0, \infty)} \end{equation}
で定義する. すなわち$S$とは非負実数列全体の集合である. - 非負実数列$s = (s_m)_{m \in \N} \in S$, 指数$1 \leq p, q \leq \infty$, 関数$f \in C^\infty(I)$に対し, その$X^{p}_s$ノルムを
\begin{equation} \norm{f}_{X^p_s} \coloneqq \sum_{m \in \N} s_m \norm{ f }_{\dot{W}^{m, p}} \end{equation}
で定義する.
特に, \begin{equation} \tag{*1} \label{eq:*} s_m = \begin{dcases} \sum_{n = 5}^{\infty} \dfrac{1}{(n!)^4 \cdot 2^n} , & m = 0 ,\\ 0 , & 1 \leq m \leq 4 , \\ \dfrac{1}{(m!)^4 \cdot 2^m} , & m \geq 5 \end{dcases} \end{equation}
で与えられた$s = (s_m)_{m \in \N} \in S$に対応する$X^2_s$ノルムのことを単に$X$ノルムと呼び, $\norm{\, \cdot \,}_X$と表す.
- 大類記事アーカイブ では$4$次元時空$\R \times \R^3$の有界部分集合$\Omega$を定義域とする関数のなす空間を考えているが, 本記事では簡単のため$1$次元化した.
- 大類記事アーカイブ では$W^{m, 1}(\Omega) \cap W^{m, 2}(\Omega)$のノルムを考えているが, $\Omega$が有界領域なのでこれは$W^{m, 2}(\Omega)$のノルムと同値である.
- 数列$s = (s_m)_{m \in \N} \in S$が
\begin{equation} s_0 = \sum_{m=1}^{\infty} s_m \end{equation}
を満たす場合, ${X}^p_s$ノルムは
\begin{equation} \norm{f}_{X^p_s} = \sum_{m \in \N} s_m \norm{ f }_{\dot{W}^{m, p}} = \sum_{m = 1}^{\infty} s_m (\norm{f}_{L^p} + \norm{ f }_{\dot{W}^{m, p}}) = \sum_{m = 1}^{\infty} s_m \norm{ f }_{{W}^{m, p}} \end{equation}
とも表せる. 特に, $s$が式\eqref{eq:*}で与えられる場合の$X^2_s$ノルムは大類記事アーカイブにおける$X$ノルムと一致する. - 大類記事 における$X$ノルムの定義は変更されることがある. 例えば2025年4月23日版 (アーカイブ大類記事アーカイブ旧) における$X$ノルムは
\begin{equation} s_m = \begin{dcases} \sum_{n \in \N} \dfrac{1}{(n!)^5} , & m = 0 ,\\ 0 , & 1 \leq m \leq 4 , \\ \dfrac{1}{(m!)^5} , & m \geq 5 \end{dcases} \end{equation}
に対応する$X^2_s$ノルムとして定義されている. 以前に大類氏がmathlogに投稿していた記事 (アーカイブ大類mathlogアーカイブ20231020) も含めると, sのとり方には少なくとも4種類以上のバリエーションがある.
このような変更が行われるたびに都度反例を提示するのは手間なので, 本記事では一般化した$X^p_s$ノルムを考えることにした.
大類記事アーカイブ の補題1, 2, 3によれば, 次が成り立ちます:
$X$ノルム, すなわち$s$が式\eqref{eq:*}で与えられる場合の$X^2_s$ノルムについて, 以下の性質$(1), (2), (3)$が全て成り立つ:
$(1)$ 条件$0 < \norm{f}_{X} < \infty$を満たす$f \in C^\infty(I)$が存在する.
$(2)$ ある定数$C_1 > 0$が存在し, 任意の$f, g \in C^\infty(I)$に対し$\norm{f g}_{X} \leq C_1 \norm{f}_{X} \norm{g}_{X}$が成り立つ.
$(3)$ ある定数$C_2 > 0$が存在し, 任意の$f \in C^\infty(I)$に対し$\norm{f'}_{X} \leq C_2 \norm{f}_{X}$が成り立つ.
しかしこれは誤りです. 本記事では, 次の定理1が成り立つことを示します.
各$s \in S$に対し, 以下の性質$({1}), ({2}), ({3})$のうち少なくともひとつは不成立である:
$({1})$ ある関数$f \in C^\infty(I)$と$1 \leq p \leq \infty$が存在し, $0 < \norm{f}_{ X^p_s} < \infty$が成り立つ.
$({2})$ ある定数$C_1 > 0$と$1 \leq p \leq \infty$が存在し, 任意の$f, g \in C^\infty(I)$に対し$\norm{f g}_{ X^p_s} \leq C_1 \norm{f}_{ X^p_s} \norm{g}_{ X^p_s}$が成り立つ.
$({3})$ ある定数$C_2 > 0$と$1 \leq p \leq \infty$が存在し, 任意の$f \in C^\infty(I)$に対し$\norm{f'}_{ X^p_s} \leq C_2 \norm{f}_{ X^p_s}$が成り立つ.
以下の議論では, 次で定義する関数族を利用します.
関数族$\{ e_r \}_{r \geq 0} \subset C^\infty(I)$を
\begin{equation}
e_r(x) \coloneqq e^{i r x}
\end{equation}
で定義する.
この関数族の性質を調べましょう. まず$e_r$の$X^p_s$ノルムを計算します.
任意の$1 \leq p \leq \infty, s \in S, r \geq 0$に対し,
\begin{equation}
\norm{e_r}_{X^p_s} = \sum_{m \in \N} s_m r^m
\end{equation}
が成り立つ.
関数$e_r$の$m$階微分は$e_r^{(m)} = (ir)^m e_r$である. また, $\abs{e_r(x)} = 1$より, 任意の$1 \leq p \leq \infty$に対し
\begin{equation}
\norm{ e_r }_{L^p} = 1
\end{equation}
が成り立つ. よって$e_r$の$\dot{W}^{m, p}$ノルムは
\begin{equation}
\norm{ e_r }_{\dot{W}^{m, p}} = \norm{e_r^{(m)}}_{L^p} = r^m \norm{ e_r }_{L^p} = r^m
\end{equation}
であり, また${X}^p_s$ノルムは
\begin{equation}
\norm{ e_r }_{X^p_s} = \sum_{m \in \N} s_m \norm{ e_r }_{\dot{W}^{m, p}} = \sum_{m \in \N} s_m r^m
\end{equation}
である.
命題2より, 次の命題3が成り立つことが分かります.
各$s \in S$に対し, 以下の性質$( A), ( B), ( C), ( D)$のうちいずれかただひとつが成り立つ:
$( A)$ 任意の$1 \leq p \leq \infty$と$r > 0$に対し, $\norm{e_r}_{X^p_s} = 0$が成り立つ.
$( B)$ 任意の$1 \leq p \leq \infty$と$r > 0$に対し, $\norm{e_r}_{X^p_s} = \infty$が成り立つ.
$( C)$ ある$R > 0$が存在し, 任意の$1 \leq p \leq \infty$と$r > 0$に対し$0 < r < R \implies 0 < \norm{e_r}_{X^p_s} < \infty$と$R < r< \infty \implies \norm{e_r}_{X^p_s} = \infty$が成り立つ.
$( D)$ 任意の$1 \leq p \leq \infty$と$r > 0$に対し, $0 < \norm{e_r}_{X^p_s} < \infty$である.
大類記事アーカイブの$X$ノルムの場合は性質$( D)$が成り立っている.
命題3はべき級数の収束半径に関する基本的な事実の単なる言い換えなので, 証明は割愛します.
次に, 定理1の3つの性質$( 1), ( 2), ( 3)$と命題3の4つの性質$( A), ( B), ( C), ( D)$の関係を調べていきます.
性質$( 1)$が成り立つための必要十分条件は, 性質$( A)$が成り立たないことである.
性質$( A)$が成り立つと仮定する.
このとき任意の$m \in \N$に対して$s_m = 0$であり, よって任意の$f \in C^\infty(I)$と$1 \leq p \leq \infty$に対して$\norm{f}_{ X^p_s} = 0$が成り立つ.
よって性質$( 1)$は成り立たない.
逆に, 性質$(A)$が成り立たないとすると, $s_{m_0} \ne 0$なる$m_0 \in \N$をとることができる.
この$m_0 \in \N$を用いて, $f \in C^\infty(I)$として$f(x) = x^{m_0}$をとる. また, $1 \leq p \leq \infty$は任意に固定する.
このとき, $0 \leq m \leq m_0$ならば$0 < \norm{f}_{\dot W^{m, p}} < \infty$かつ$m \geq m_0 + 1$ならば$\norm{f}_{\dot W^{m, p}} = 0$であるから
\begin{equation}
0 < s_{m_0} \norm{f}_{\dot W^{{m_0}, p}} \leq \sum_{m \in \N} s_m \norm{ f }_{\dot{W}^{m, p}} = \sum_{m=0}^{m_0} s_m \norm{ f }_{\dot{W}^{m, p}} < \infty
\end{equation}
となる. よって性質$( 1)$が成り立つ.
性質$( 3)$が成り立つための必要条件は, 性質$( D)$が成り立たないことである.
大類記事アーカイブの$X$ノルムの場合は性質$( D)$が成り立っているので, 性質$( 3)$は成り立たない.
性質$( D)$が成り立つと仮定する. このとき, $e_r$の微分が$e_r' = ir e_r$であることから, 任意の$r > 0$と$1 \leq p \leq \infty$に対し
\begin{equation}
0 < \norm{e_r'}_{ X^p_s} = r \norm{e_r}_{ X^p_s} < \infty
\end{equation}
が成り立つ. よって, 任意に固定した定数$C_2 > 0$と$1 \leq p \leq \infty$に対し, $r = 2C_2$とすれば
\begin{equation}
\norm{e_r'}_{ X^p_s} = 2C_2 \norm{e_r}_{ X^p_s} > C_2 \norm{e_r}_{ X^p_s}
\end{equation}
が成り立つ. ゆえに性質$( 3)$は成り立たない.
命題4, 5の証明は簡単でしたが, 次の命題6の証明は少し準備が必要です.
性質$( 2)$が成り立つための必要条件は, 性質$( B), (C)$がどちらも成り立たないことである.
命題6を証明するために関数族をもうひとつ新たに導入します.
関数族$\{ P_k \}_{k \in \N} \subset C^\infty(I)$を
\begin{equation}
P_k(x) \coloneqq x^k
\end{equation}
で定義する.
この関数族の$X^p_s$ノルムを評価します.
任意の$1 \leq p \leq \infty, s \in S, k \in \N$に対し,
\begin{equation}
k! \cdot s_k \leq \norm{ P_k }_{X^p_s} < \infty
\end{equation}
が成り立つ.
有限性$\norm{ P_k }_{X^p_s} < \infty$の証明は命題4の後半の議論で既に示されている.
下からの評価を示す. 関数$P_k$の$k$階微分は
\begin{equation}
P_k^{(k)}(x)
= k!
\end{equation}
であるから, 任意の$1 \leq p \leq \infty$に対し$P_k$の$\dot{W}^{k, p}$ノルムは
\begin{equation}
\norm{ P_k }_{\dot{W}^{k, p}} = k!
\end{equation}
である. したがって$X^p_s$ノルムは下から
\begin{equation}
\norm{ P_k }_{X^p_s} = \sum_{m \in \N} s_m \norm{P_k}_{\dot{W}^{m, p}} \geq k! \cdot s_k
\end{equation}
と評価できる.
命題7を用いて, 命題6を示します.
性質$( 2)$が成り立つと仮定する.
このとき, $P_k = (P_1)^k$に注意すると, ある$C_1 > 0$と$1 \leq p \leq \infty$が存在して任意の$k \in \N$に対し
\begin{equation}
\norm{ P_k }_{X^p_s} \leq (C_1 \norm{P_1}_{X^p_s})^k
\end{equation}
が成り立つことが分かる. 以下そのような$C_1$と$p$をそれぞれ適当に固定する. このとき, 命題7より, 任意の$k \in \N$に対し
\begin{equation}
k! \cdot s_{k} \leq (C_1 \norm{P_1}_{X_s^p})^k < \infty
\end{equation}
が成り立つ. よって命題2より, 任意の$r > 0$に対し
\begin{equation}
\norm{e_r}_{X^p_s} = \sum_{m \in \N} s_m r^m \leq \sum_{m \in \N} \frac{1}{m!} (r C_1 \norm{P_1}_{{X}^p_s})^m = \exp(r C_1 \norm{P_1}_{{X}^p_s}) < \infty
\end{equation}
となる. ゆえに性質$( B), (C)$はどちらも成り立たない.
最後に, 命題3, 4, 5, 6を合わせて定理1を示します.
性質$(1), (2)$がともに成り立つと仮定する. このとき命題4, 6より性質$(A), (B), (C)$はいずれも成り立たない.
よって命題3より性質$(D)$が成り立つ. したがって命題5より性質$( 3)$は成り立たない.
大類の理論の現状 (2025年5月29日現在)
2025年5月29日現在におけるnote大類記事の最新版である2025年5月27日版大類記事アーカイブ20250527の問題点について簡単に整理しておきます.
『補題3』
本記事でここまで扱ってきた2025年5月3日版のnote大類記事アーカイブにおける補題3は, 次のような主張でした.
ある定数$C_2 > 0$が存在して, 任意の$u \in X$に対し
\begin{equation} \tag{*2} \label{eq:*2}
\norm{u'}_{X} \leq C_2 \norm{u}_X
\end{equation}
が成り立つ.
本記事の命題3, 5によってこの主張は不成立であることが分かり, したがって大類記事アーカイブの議論は誤りです.
一方, 2025年5月27日版大類記事アーカイブ20250527では補題3の主張が次のように変更されています
定数$C_2, M >0$をそれぞれ適当に固定し, ノルム空間$X$の部分集合$S$を
\begin{equation}
S \coloneqq \set{u \in X}{ \norm{u}_X \leq M , \, \norm{u'}_X \leq C_2 \norm{u}_X }
\end{equation}
で定義する. このとき, 任意の$u \in S$に対し不等式$\eqref{eq:*2}$が成り立つ.
これはもちろん正しい主張なのですが, 自明な主張なので数学的には無意味です.
実際, $u \in S$を示すには現状では$\norm{u}_X \leq M$と$\norm{u'}_{X} \leq C_2 \norm{u}_X$を示すしかなく, 補題3を利用しようとしても「$\eqref{eq:*2}$を示すために$\eqref{eq:*2}$を示す」という議論にしかなりません (もし集合$S$を不等式$\eqref{eq:*2}$を用いない形で特徴づけできるなら話は別ですが, そのような考察は一切行われていません).
現在のnote大類記事アーカイブ20250527では補題3が複数回用いられているものの, そのために必要な$u \in S$は (仮定から自明な場合を除いて) 一切証明されていないので, 実質的には根拠なく「不等式$\eqref{eq:*2}$は成り立つ」と主張しているだけで証明として成立していません.
なお, 以前の大類記事アーカイブにおける補題3の (誤った) 証明では$X$ノルムの定義を利用した (誤った) 評価が行われており, この補題3こそが$X$ノルムをSobolevノルムの無限和で定義した理由であったと推測されます.
一方, 現在の大類記事アーカイブ20250527における補題3は$X$ノルムの定義がなんであろうと自明に正しく, $X$ノルムをSobolevノルムの無限和で定義すべき理由がどこにあるのかは不明です.
『補題2』
本記事では詳細には立ち入りませんが, 大類記事アーカイブの補題2の証明の誤りが市民氏によって以前に指摘されています (ポスト補題2の証明).
2025年5月27日版大類記事アーカイブ20250527では問題の箇所に『指数関数のマクローリン展開の証明と同じ要領』なる文言が追記されていますが, その具体的な意味については説明されていません. 問題の箇所の主張そのものは指数関数ともMaclaurin展開とも全く無関係なため, 何を主張しているのか理解困難です.
『バナッハの不動点定理と似た方法』
2025年5月3日版大類記事アーカイブでは, Navier--Stokes方程式の弱解を得るためにBanachの不動点定理と呼ばれる有名な定理が用いられています.
その主張は次の通りです:
$(S, d)$を空でない完備距離空間とする. また, $\Phi : S \to S$を縮小写像とする. すなわち, 写像$\Phi : S \to S$が次の条件を満たすことを仮定する:
\begin{equation}
\exists L < 1, \, \forall (u, v) \in S^2, \, d(\Phi[u], \Phi[v]) \leq L d(u, v) .
\end{equation}
このとき, $\Phi[u] = u$を満たす$u \in S$がただひとつ存在する.
この定理は実際の偏微分方程式論においてもよく用いられるものです.
写像$\Phi$は (定義域と値域を無視すれば形式的には) 解きたい方程式から自動的に決まるので, $\Phi : S \to S$が縮小写像となるような完備距離空間$S$を設定することが本質的です.
大類記事アーカイブでは, 次の2つを根拠としてBanachの不動点定理で解の存在を示そうとしていました:
- 十分に小さい定数$M>0$に対し, ノルム空間$X$の部分距離空間$S$を$S \coloneqq \set{u \in X}{\norm{u}_X \leq M}$で定める. このとき$S$は完備である.
- 関数$u \in S$に対し, $\Phi : S \to S$を$$\Phi[u] \coloneqq \int_{\R \times \R^3} E(s, y) \chi_\Omega(t-s, x-y) ( Pf(t-s, x-y) - P( (u_n \cdot \nabla) u_n )(t-s, x-y) ) \, ds \, dy$$で定める. このとき$\Phi$は縮小写像である. すなわち, 次が成り立つ: $$\exists L < 1, \, \forall (u, v) \in S^2, \, \norm{ \Phi[u] - \Phi[v] }_X \leq L \norm{u - v}_X.$$
この設定では$S$が完備距離空間であることは (ノルム空間$X$の完備性を認めれば) 容易に示せる一方で, $\Phi : S \to S$がwell-definedであることや縮小写像であることの証明は誤った補題3に依存しており, したがって証明が成立していないという状況でした.
一方, 2025年5月27日版大類記事アーカイブ20250527では次のような設定になっています:
- 十分に小さい定数$C_2, M>0$に対し, ノルム空間$X$の部分距離空間$S$を$S \coloneqq \set{u \in X}{ \norm{u}_X \leq M , \, \norm{u'}_X \leq C_2 \norm{u}_X }$で定める.
- 関数$u \in S$に対し, $\Phi : S \to X$を$$\Phi[u] \coloneqq \int_{\R \times \R^3} E(s, y) \chi_\Omega(t-s, x-y) ( Pf(t-s, x-y) - P( (u_n \cdot \nabla) u_n )(t-s, x-y) ) \, ds \, dy$$で定める. このとき$\Phi$は$$\exists L < 1, \, \forall (u, v) \in S^2, \, (u-v \in S \implies \norm{ \Phi[u] - \Phi[v] }_X \leq L \norm{u - v}_X)$$を満たす.
大類記事アーカイブ20250527では$S$が完備であるかどうかについては何も言及されておらず, また$\Phi$も$S$上の縮小写像ではなくなっています ($\Phi : S \to S$ではなく$\Phi : S \to X$となっていること, また$\Phi$の縮小性に相当する主張に$u-v \in S$という追加の仮定があることに注意). したがってBanachの不動点定理は適用できません. このことは大類氏も認識しているようであり, 大類記事アーカイブ20250527ではBanachの不動点定理そのものを使うのではなく『バナッハの不動点定理と似た方法で証明する』ことになっています. しかしながら, その『似た方法』とは一体何なのかという肝心の部分については証明どころか主張すらほとんど説明がありません. もし本当に$S$の完備性も$\Phi$の縮小性もいらない不動点定理の証明に成功したのであれば, ぜひともその主張と証明を公開してほしいものです.
なお, 私見ですが, 大類記事アーカイブ20250527及び大類氏のXでのポスト大類ポストBanachの内容を考慮すると, 『バナッハの不動点定理と似た方法』の証明は間違っている可能性が高いと推測します. これはあくまで推測なのでここでは理由は割愛します. 興味がある方はこちらのポストsomeoneポストBanach1, someoneポストBanach2をご覧ください. 最後に, someoneポストBanach1を投稿した直後に筆者のXアカウントは大類氏からブロックされたことを申し添えておきます.
更新履歴
- 2025年5月29日 第3版
- 大類記事の現在の状況についてのまとめを追記した.
- 2025年5月6日 第2版
- 第2版では, 内容を
\begin{equation} \norm{f}_{X^p_s} \coloneqq \sum_{m \in \N} s_m \norm{ f }_{\dot{W}^{m, p}} \end{equation}
で定義した$X^p_s$ノルム $(1 \leq p \leq \infty)$ に関する議論に一般化した. 証明自体は初版 ($p = 1$の場合) とほとんど同じである. - 初版では定義1の直後の注意で『大類記事アーカイブ では$W^{m, 1}(\Omega) \cap W^{m, 2}(\Omega)$のノルムを考えているが, $\Omega$が有界領域なのでこれは$W^{m, \color{red}{1}}(\Omega)$のノルムと同値である』と述べている. これは誤りであり, $W^{m, \color{red}{1}}(\Omega)$ではなく$W^{m, \color{red}{2}}(\Omega)$が正しい.
- 初版における命題4の証明は誤っている. 実際, 証明前半の『性質(A)が成り立つと仮定する. ~よって性質(1)は成り立たない』と後半の「逆に, 性質(1)が成り立つとすると, ~性質(A)は成り立たない」はどちらも$( 1)\implies\lnot ( A)$の証明になってしまっている (てりゃ氏による指摘ポストてりゃ指摘ポスト).
第2版では, 証明の後半部分を$\lnot (1) \implies (A)$の証明に訂正した.
-その他, 誤字脱字等の軽微な誤りを修正した.
- 第2版では, 内容を
- 2025年5月5日 初版