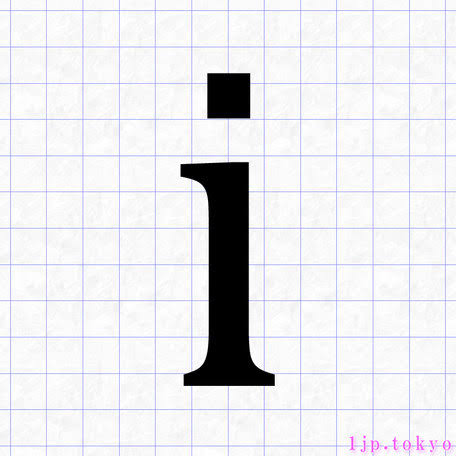グリーン・タオの定理5 ハイパーグラフ除去補題の証明①
こんにちは,itouです.
前回は
ハイパーグラフ除去補題
$\Rightarrow$多次元コーナー定理
$\Rightarrow$有限版多次元セメレディの定理
を確認しました.今回からついにハイパーグラフ除去補題の証明に入ります.
その大筋は
正則化補題+数え上げ補題
$\Rightarrow$ハイパーグラフ除去補題
です.つまり,2つの補題:正則化補題,数え上げ補題を用いてハイパーグラフ除去補題を証明します.
ハイパーグラフ除去補題を示すために,まずハイパーグラフ除去補題を別の道具を使って翻訳します.
道具とは以下です.
道具:
加法族,$L^2$空間,条件付き期待値作用素,食い違い距離
せっかくハイパーグラフを理解したのにまた新しい道具が出てきます.とは言え,加法族は有限集合に対するものしか扱いませんし,ここでの期待値は相加平均にすぎません.今回はこれらの道具を紹介していきます.
定義&補題
前半
全部で20個ぐらいあります.本書とは少し順番が違います.サクサク行きましょう.
$X$を空でない集合とする.$X$上で定義された関数$f:X\rightarrow \mathbb R$と空でない有限部分集合$a\subset X$に対し,$f$の$A$における期待値を$\mathbb E(f|A)$,または変数付きで$\mathbb E(f(a)|a\in A)$と表し,
\begin{align} \mathbb E(f|A)=\mathbb E(f(a)|a\in A)=\frac{1}{\sharp A}\sum_{a\in A}f(a) \end{align}
と定義する.
$A,B$を空でない有限集合,$f:B\rightarrow \mathbb R$を$B$上で定義された関数とし,写像$\Phi:A\rightarrow B$は一様被覆であるとする.このとき,
\begin{align}
\mathbb E(f\circ\Phi|A)=\mathbb E(f|B)
\end{align}
が成り立つ.ここで,任意の$b\in B$に対して$\sharp \Phi^{-1}(\{b\})=\frac{\sharp A}{\sharp B}$は一様被覆であるという.
期待値といっていますが相加平均とってるだけですね.一様被覆とは,全射な関数$\Phi:A\rightarrow B$において$A$の元のうちちょうど$ \frac{\sharp A}{\sharp B}$個だけが同じ行き先だということです.
$X$を集合とする.$\mathscr P$が$X$の分割であるとは,
(1)$\mathscr P \subset \mathfrak B(X)\backslash \{\varnothing\}$
(2)$A,B\in \mathscr P,A\ne B\Rightarrow A\cap B =\varnothing$
(3)$X=\bigcup _{A\in\mathscr P }$
が成り立つときをいう.
集合の分割の正式な定義がこれです.
分割をより細かくしたものを細分といいます.
$\mathscr P,\mathscr L$をともに$X$の分割とする.$\mathscr P$が$\mathscr L$の細分であるとは,任意の$A \in\mathscr P$に対して,ある$B\in\mathscr L$が存在して,$A\subset B$が成り立つことをいう.
さて,分割に対応する概念である加法族を導入します.
$V$を有限集合とする.
(1)$V$の部分集合族$\mathcal B\subset\mathfrak B(V) $が$V$上の加法族であるとは,
\begin{align} \qquad &(a)\varnothing \in \mathcal B\\ &(b)A,B\in \mathcal B\Rightarrow A\cup B \in \mathcal B\\ &(c)A\in \mathcal B \Rightarrow V\backslash A\in \mathcal B\\ \end{align}
が成り立つことをいう.
(2)は後述.
(3)$V$の部分集合族$\mathcal F \subset \mathfrak B(V)$に対して,$\mathcal F$を含むような$V$上の加法族のうち包含関係に関して最小であるものを,$\mathcal F$が生成する$V$上の加法族とよぶ.
(4)も後述.
(5)$V\ne \varnothing$とし,$\mathcal B$を$V$上の加法族とする.$\mathcal B \backslash \{\varnothing\}$における包含関係に関する極小元を,$\mathcal B$のアトムという.$\mathcal B$のアトム全体の集合を$\rm{Atom}(\mathcal B)$と表す.
ちなみに$A,B\in \mathcal B$のとき,$A\backslash B=(A^C\cup B)^{C}\in\mathcal B$です.
なお$A\cap B=(A^C\cup B^C)^C$より$A\cap B\in\mathcal B$.
$V=\{1,2,3,4\}$とします.$V$上の加法族をいくつか並べてみます.
\begin{align}
&\{\varnothing,\{1,2,3,4\} \}\\
&\{\varnothing,\{1\},\{2,3,4\},\{1,2,3,4\} \}\\
&\{\varnothing,\{1,2\},\{3,4\},\{1,2,3,4\} \}\\
&\{\varnothing,\{2,3\},\{1,4\},\{1,2,3,4\} \}\\
&\{\varnothing,\{1\},\{2\},\{1,2\},\{3,4\},\{2,3,4\},\{1,3,4\},\{1,2,3,4\} \}\\
\end{align}
すべて$\varnothing,V$が含まれています.
$\varnothing$と$\mathfrak B(V)$の元をいくつか取ってきて,和集合をとる演算$\cup$と補集合をとる演算$(\cdot)^{C}$に関して閉じているようにしたのが加法族です.はじめに取ってきた$\mathfrak B(V)$の元$\mathcal F$から加法族ができたので,これを$\mathcal F$が生成する$V$上加法族といいます.同じ加法族を生成するような集合$\mathcal F$は複数ありえます.
さらに,上の例においてアトム全体の集合を順に列挙します.
\begin{align}
&\{\{1,2,3,4\} \}\\
&\{\{1\},\{2,3,4\}\}\\
&\{\{1,2\},\{3,4\} \}\\
&\{\{2,3\},\{1,4\} \}\\
&\{\{1\},\{2\},\{3,4\}\}\\
\end{align}
アトム全体の集合は$V$の分割となっています.これが加法族を考える理由です.
上の例で確かめたことは以下のように表現されます.
$\mathcal B$を$V$上の加法族とする.
(1)各$x\in V$に対して,$x$が属する$\mathcal B$のアトムが一意的に定まる.
(2)任意の$y\in \mathcal B(x)$にたいして,$\mathcal B(x)=\mathcal B(y) $が成立.ただし,$x$が属する$\mathcal B$のアトムを$\mathcal B(x)$と表す.
$\mathcal B$を$V$上の加法族とする.このとき,任意の$B\in \mathcal B$は,ある部分集合$\mathscr A\subset \rm{Atom}(\mathcal B)$を用いて,$B=\bigcup_{A\in \mathscr A}A$と表される.このような$\mathscr A $は一意的に定まる.
$\mathscr P$を$V$の分割とする.このとき,$\mathscr P=\rm{Atom}(\mathcal B)$が成り立つような$V$上の加法族$\mathcal B$が一意的に存在する.
加法族のイメージがつかめたでしょうか.分割と加法族は1対1対応するというのが重要です.さらに,細分と部分加法族が1対1対応します.
$\mathcal B,\mathcal B'$がともに$V$上の加法族であり,$\mathcal B \subset \mathcal B'$であるとき,$\mathcal B$は$\mathcal B'$の部分加法族であるという.
(4)$\mathcal B_1,\mathcal B_2$がともに$V$上の加法族であるとき,$\mathcal B_1 \cup \mathcal B_2$が生成する$V$上の加法族を$ \mathcal B_1\lor\mathcal B_2$と表す.同様に,$V$上の加法族の列$(\mathcal B_i)_{i \in I}$に対して,$\bigcup_{i \in I}\mathcal B_i$が生成する$V$上の加法族を$\bigvee_{i\in I} \mathcal B_i$と表す.
例1に出てきた2つの加法族
\begin{align}
&\{\varnothing,\{1,2\},\{3,4\},\{1,2,3,4\} \}\\
&\{\varnothing,\{1\},\{2\},\{1,2\},\{3,4\},\{2,3,4\},\{1,3,4\},\{1,2,3,4\} \}\\
\end{align}
において,上の加法族は下の加法族の部分加法族です.
それぞれのアトム全体の集合は
\begin{align}
&\{\{1,2\},\{3,4\} \}\\
&\{\{1\},\{2\},\{3,4\}\}\\
\end{align}
でした.下の分割が上の分割の細分になっています.
\begin{align}
&\mathcal B_1=\{\varnothing,\{1\},\{2,3,4\},\{1,2,3,4\} \}\\
&\mathcal B_2=\{\varnothing,\{2,3\},\{1,4\},\{1,2,3,4\} \}\\
\end{align}
とすると,$\mathcal B_1 \cup \mathcal B_2$は
\begin{align}
&\mathcal B_1 \cup \mathcal B_2=\{\varnothing,\{1\},\{2,3\},\{1,4\},\{2,3,4\},\{1,2,3,4\} \}\\
\end{align}
であり,$\mathcal B_1 \vee \mathcal B_2$は
\begin{align}
&\mathcal B_1 \vee \mathcal B_2=\{\varnothing,\{1\},\{4\},\{2,3\},\{1,4\},\{1,2,3\},\{2,3,4\},\{1,2,3,4\} \}\\
\end{align}
となります.$\rm{Atom}(\mathcal B_1),\rm{Atom}(\mathcal B_2),\rm{Atom}(\mathcal B_1 \vee \mathcal B_2)$はそれぞれ,
\begin{align}
&\{\{1\},\{2,3,4\} \}\\
&\{\{2,3\},\{1,4\} \}\\
&\{\{1\},\{2,3\},\{4\} \}\\
\end{align}
です.2つの$\rm{Atom}$の分割の切れ目を引き継いでいる(それぞれの細分になっている)ことが分かります.
上の例で確認したことが以下の補題4です.
(1)$\mathcal B,\mathcal B'$を$V$上の加法族とする.このとき,$\mathcal B$が$\mathcal B'$の部分加法族であることは,$\rm{Atom}(\mathcal B')$が$\rm{Atom}(\mathcal B)$の細分になることに同値.
(2)$V$上の加法族$ \mathcal B_1,\mathcal B_2$に対して,
\begin{align}
\rm{Atom}(\mathcal B_1 \vee\mathcal B_2)=\{A\cap B:A\in \rm{Atom}(\mathcal B_1),B\in\rm{Atom}(\mathcal B_2),A\cap B\ne \varnothing\}
\end{align}
が成り立ち,$\rm{Atom}(\mathcal B_1 \vee\mathcal B_2)$の元$A\cap B$は一意的である.
さて,加法族に対して複雑度という量を定義します.
$\mathcal B$を$v$上の加法族とする.$\mathcal F\subset \mathfrak B(V)$であって,$\mathcal F$が生成する$V$上の加法族が$\mathcal B $となるものを考えるとき,$\sharp \mathcal F$として取り得る最小値
を$\mathcal B $の複雑度といい,$\rm{cpx}(\mathcal B)$と表す.とくに,$\rm{cpx}(\{\varnothing,V\})=0$である.
$V=\{1,2,3,4\}$のとき
$\text{Atom}(\mathcal B)=\{\{1\},\{2\},\{3\},\{4\}\}$なる$\mathcal B$(つまり$2^V$)の複雑度は,
$\mathcal F=\{\{1,2\},\{1,3\}\}$が$\mathcal B$を生成するので
$\sharp \mathcal F=2$.
$V=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$,$\text{Atom}(\mathcal B)=\{\{1\},\{2\},\{3\},\{4\},\{5\},\{6\},\{7\},\{8\}\}$なる$\mathcal B$(つまり$2^V$)の複雑度は,
$\mathcal F=\{\{1,2,3,4\},\{1,2,5,6\},\{1,3,5,7\}\}$が$\mathcal B$を生成するので
$\sharp \mathcal F=3$.
\begin{align}
\text{cpx}(\mathcal B)=\lceil\log_2(\text{Atom}(\mathcal B)) \rceil
\end{align}
が成立するだろうか
$\mathcal B_1,\mathcal B_2,\mathcal B$を$V$上の加法族とする.このとき,
(1)$ \rm{cpx}(\mathcal B_1 \vee\mathcal B_2)\leq \rm{cpx}(\mathcal B_1)+\rm{cpx}(\mathcal B_2)$
(2)$\sharp \mathcal B=2^{\sharp \rm{Atom}(\mathcal B)}\leq2^{2^{\rm{cpx}(\mathcal B)}}$
ある加法族を生成するような集合$\mathcal F$のうち,もっとも要素が少ないものを取ってきて,その要素の個数を複雑度といいます.つまり,「材料が少ない」加法族ほど複雑度が小さいです.
休憩
ここまで一気に駆け抜けてきました.簡単なものを片付けておきます.
考えている集合$A$に$x$が入っているなら1,入っていないなら0を返す関数を特性関数といいます.
集合$A,B,(A\subset B)$に対し,特性関数$\mathbf 1_A:B\rightarrow \mathbb R$を
\begin{equation}
\mathbf1_A(x)=
\left\{ \,
\begin{aligned}
& 1 \quad (x\in A) \\
& 0 \quad(x\in B\backslash A)\\
\end{aligned}
\right.
\end{equation}
とする.
$V$上の加法族$\mathcal B$と関数$f:V\rightarrow \mathbb R$に対して,
\begin{align}
\sum_{A\in \rm{Atom}(\mathcal B)}\mathbb E(f\cdot \mathbf 1_A|V)=\mathbb E(f|V)
\end{align}
定義通り計算するとわかります.
さて,ここから後半戦です.
後半
まず関数からなる空間を用意します.
$L^2(V,\mathbb R)$を定義域が$V$で終域が$\mathbb R$であるような関数全体からなり,内積が$ \langle f,g \rangle =\mathbb E(fg|V)$で定まる実内積空間であるとする.つまり,$L^2(V,\mathbb R)$は$\mathbb R$ベクトル空間であり,内積について,次の性質が成り立つ.
(1)任意の$f\in L^2(V,\mathbb R)$に対して,$ \langle f,f \rangle \geq 0$であり,$ \langle f,f \rangle=0\Leftrightarrow f=0$.
(2)任意の$f,g\in L^2(V,\mathbb R)$に対して,$\langle f,g \rangle=\langle g,f \rangle$.
(3)任意の$\lambda,\mu \in \mathbb R,f,f',g\in L^2(V,\mathbb R)$に対して,$\langle \lambda f+\mu f',g \rangle=\lambda\langle f,g \rangle+\mu\langle f',g \rangle $.
$f\in L^2(V,\mathbb R)$のノルム$\| f \| \geq 0$であり,$\|f\|=\sqrt{\langle f,f \rangle}$で定義する.このとき,ノルムについて,次の性質が成り立つ.
(1)任意の$f\in L^2(V,\mathbb R)$に対して,$\|f\| \geq 0$であり,$ \|f\| =0\Leftrightarrow f=0$.
(2)任意の$\lambda \in \mathbb R,f\in L^2(V,\mathbb R)$に対して,$\|\lambda f\|=\lambda \|f\|$.
(3)任意の$f,g\in L^2(V,\mathbb R)$に対して,$|\langle f,f \rangle|\leq \|f\|\|g\|$.(コーシー・シュワルツの不等式)
$L^2(V,\mathbb R)$の部分空間$W$に対し,$W$の直行補空間$W^{\bot}$を
\begin{align}
W^{\bot}=\{f\in L^2(V,\mathbb R):\forall g\in W,\langle f,g \rangle =0\}
\end{align}
と定義する.
関数たちの集まりに期待値で距離を入れた空間を扱っていきます.
$\mathcal B$を$V$上の加法族とする.$f\in L^2(V,\mathbb R)$が$\mathcal B$可測関数であるとは,任意の$A\in \rm{\rm{Atom}}(\mathcal B)$に対して$f|_A$が定数関数であるときをいう.$\mathcal B$可測関数全体のなす$L^2(V,\mathbb R)$の部分空間を$\mathcal M(\mathcal B)$と表す.
$f\in L^2(V,\mathbb R)$の中でも性質がいいものを$\mathcal B$可測関数と名付けておきます.
$\mathcal B$を$V$上の加法族とする.このとき,条件付き期待値作用素$\mathbb(\cdot|\mathcal B):L^2(V,\mathbb R)\rightarrow M(\mathcal B)$を$f\in L^2(V,\mathbb R)$に対して関数$\mathbb E(f|\mathcal B):V\rightarrow \mathbb R$を
\begin{align}
\mathbb E(f|\mathcal B)(x)=\mathbb E(f|\mathcal B(x))
\end{align}
と定めることによって定義する.
つまり$\mathbb E(f|A)$を$f,A$を「変数」にもち,関数を返す写像として考えていきます.うれしいことに,$\mathbb E(f|A)$について以下の性質が成立します.
$a,b\in \mathbb R,f,g\in L^2(V,\mathbb R)$とする.以下の(1)~(3)が成立する.
(1)線形性:$\mathbb E(af+bg|\mathcal B)=a\mathbb E(f|\mathcal B)+b\mathbb E(g|\mathcal B)$
(2)冪等性:$\mathbb E(\mathbb E(f|\mathcal B)|\mathcal B)=\mathbb E(f|\mathcal B)$
(3)自己随伴性:$\langle \mathbb E(f|\mathcal B),g \rangle=\langle f,\mathbb E(g|\mathcal B) \rangle$
線形はいいでしょう.冪等という言葉は聞きなじみがないですが,$f$に$\mathbb E(f|A)$を何度作用しても1度作用するのと同じという意味です.自己随伴はノルムに関する性質です.
直行補空間について以下の通りです.( 直行補空間の性質|高校数学の美しい物語 も参照のこと.)
$\mathcal B$を$V$上の加法族とし,$f\in L^2(V,\mathbb R)$とする.このとき,
\begin{align}
f\in \mathcal M(\mathcal B)^{\bot}
\Longleftrightarrow \mathbb E(f|\mathcal B)=0
\end{align}
が成り立つ.
$\mathcal B$を$V$上の加法族とし,$f\in L^2(V,\mathbb R)$は
\begin{align}
f=g+h,\ g\in \mathcal M(\mathcal B),\ h\in \mathcal M(\mathcal B)^{\bot}
\end{align}
と一意的に表示できる.
$\mathcal M(\mathcal B),\mathcal M(\mathcal B)^{\bot}$があれば$L^2(V,\mathbb R)$の元をすべて表現できます.
$\mathcal B'$を$V$上の加法族,$\mathcal B$を$\mathcal B'$の部分加法族とする.$f\in L^2(V,\mathbb R)$に対して,
\begin{align}
\mathbb E(\mathbb E(f|\mathcal B')\mathcal B)=\mathbb E(f|\mathcal B)
\end{align}
が成り立つ.
ノルムに関して以下が成立します.
$\mathcal B'$を$V$上の加法族,$\mathcal B$を$\mathcal B'$の部分加法族とする.このとき,$f\in L^2(V,\mathbb E)$に対して,
\begin{align}
\|\mathbb E(f|\mathcal B')\|^2=\|\mathbb E(f|\mathcal B)\|^2+\|\mathbb E(f|\mathcal B')-\mathbb E(f|\mathcal B)\|^2
\end{align}
面白いですね.このノルムがかなり性質がいいというのがよく分かります.
最後に重要な概念を定義しておきます.これは第6章にも出てきます.
$\mathcal F \subset \mathfrak B(V)$を,$V\in \mathcal F$を満たす$V$の部分集合族とする.このとき,$f,f'\in L^2(V,\mathbb R)$の$\mathcal F$に関する食い違い距離$d_{\mathcal F}(f,f')$を
\begin{align} d_{\mathcal F}(f,f')=\max_{A\in \mathcal F}|\langle f-f',\mathbf 1_A\rangle|=\max_{A\in \mathcal F}|\mathbb E((f-f')\cdot\mathbf 1_A|V)| \end{align}
距離といっていますが,擬距離という距離の公理を弱めたものを満たす概念です.
もし$\{\{x\}\in\mathfrak P(V):x\in V\}\subset \mathcal F$であるなら,$A=\{x\}$のときに
\begin{align}
\sum_{v\in V}(f-f')(v)\cdot\mathbf1_A(v)=(f-f')(x)\cdot 1=0
\end{align}
より
$f(x)=f'(x)$であり,$x\in V$は任意なので
$f\equiv f'$です.逆も成立するので,この場合は食い違い距離は距離となっています.
感想
つかれました.
謝辞
誤植等指摘よろしくお願いいたします.