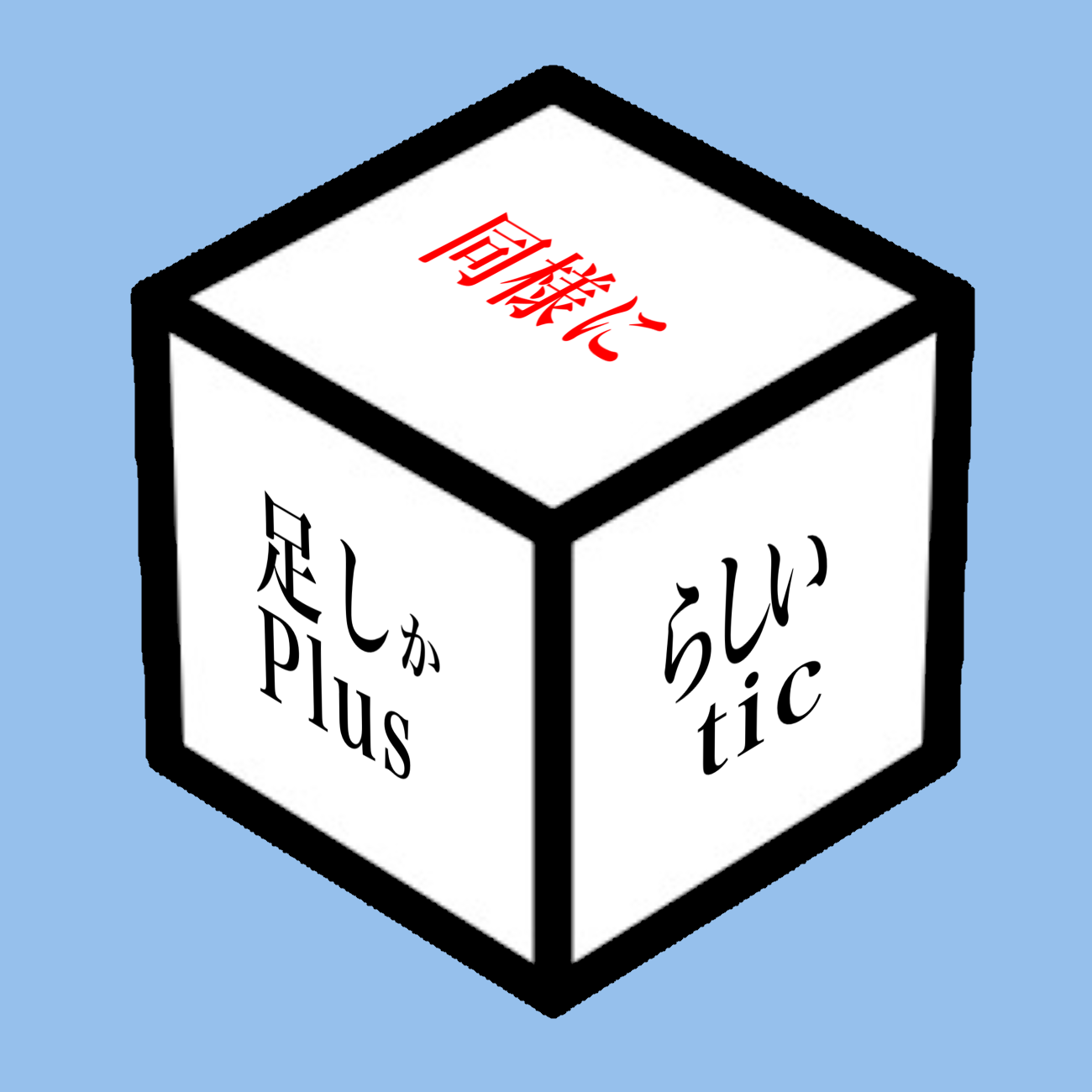加法と乗法が有限生成な体
注意!!結構雑に書いてます。不正確、分かり難い所もあると思います。すみません。
可換環$A$の任意の元$a,b\in A$に対してこれが互いに素であるとは、ある$u,v\in A$が存在して$au+bv=1$となること。
これは整数において通常の素因数を用いる定義と一致します。
扱うにはこっちの方が都合がいいのでこちらを定義とします。イデアルの互いに素もあるのですが、ここでは元の場合のみ使うことにします。
可換環$A$の任意の元$a,b,c\in A$に対して$a$と$b$,$a$と$c$が互いに素ならば$a$と$bc$も互いに素である。
$u,v,w,x\in A$が存在して、$au+bv=aw+cx=1$となるとする。
$1=au+bv=au+bv(aw+cx)=a(u+btw)+bcvx$
可換環$A$の任意の元$a,b,c\in A$に対して$a$と$b$が互いに素で$a$が$bc$を割り切るなら、$a$は$c$を割り切る。
$u,v\in A$が存在して、$au+bv=1$となるとする。
$c=(au+bv)c=acu+bcv$
仮定より$a$は$bc$を割り切るので$a$は$c$も割り切る。
可換整域$A$の任意の非零元$a\in A\backslash A ^×$に対して$e,d\in \mathbb{Z}_{≧0}$を取ったとき$a^e$が$a^d$を割り切るなら$e≦d$
$a^e$が$a^d$を割り切るので$b\in A$を用いて$a^eb=a^d$と書ける。$e≧d+1$だと仮定すると$a^da^{e-d}b=a^d$で$a_d≠0$なので整域性より$a^{e-d}b=1$である。$e-d≧1$なので$a(a^{e-d-1}b)=1$と書けるが、これは$a\not\in A ^×$に矛盾する。
可換整域$A$の任意の非零な元$a_1…,a_k\in A\backslash A ^×$に対して$i≠j$としたとき$a_i$と$a_j$が互いに素とする。$e_1…,e_k,d_1…,d_k\in \mathbb{Z}_{≧0}$に対して$a_1^{e_1}…a_k^{e_k}=a_1^{d_1}…a_k^{d_k}$が成り立つとき、$e_1=d_1…,e_k=d_k$
$1≦i≦k$を取ったとき、$a^0=1$や命題1を繰り返し用いることで、$a_i^{e_i}$と$ \prod_{j≠i} a_j^{d_j}$が互いに素になることが分かる。
よって命題2より$a_i^{e_i}$は$a_i^{d_i}$を割り切るので命題3より$e_i≦d_i$が言える。同様に$e_i≧d_i$も言えるので$e_i=d_i$が言える。
辞書式順序を用いて帰納的に証明した方が綺麗かもしれません。
体でない可換整域$A$乗法群が有限のとき、非自明なイデアル$I$に対して$〈1+I〉$は非有限生成である。
$〈〉$は分数体の乗法群の部分群として中身が生成する群です。
非零元$a\in A\backslash A^×$を取る。
このとき$1+a\prod_{s\not \in A ^×\backslash \{1\}}(s-1)$は0でも単元でもない。もし0と等しいと仮定すると$1=-a\prod_{s\not \in A ^×\backslash \{1\}}(s-1)$となり$a$が単位元でないことに矛盾する。もし1と等しいと仮定すると$0=a\prod_{s\not \in A ^×\backslash \{1\}}(s-1)$となるがこれは整域性に矛盾する。もし$t\not \in A ^×\backslash \{1\}$と等しいとすると$t-1=a\prod_{s\not \in A ^×\backslash \{1\}}(s-1)$であり、$1=a\prod_{s\not \in A ^×\backslash \{1,t\}}(s-1)$となるがこれは$a$が単位元でないことに矛盾する。
非零元$i\in I$を取ったとき$I$が非自明なイデアルであるのでこれは単元ではなく、$i_1=i\prod_{s\not \in A ^×\backslash \{1\}}(s-1)$,$i_{n+1}=1+i_1…i_n\in 1+I$を定義したとき先程の議論から$i_n$は非零元かつ非単元である。また$n≠m$に対して$i_n$と$i_m$は互いに素である。
$〈i_1…,i_n…〉$において$\{i_1…,i_n…\}$が基底になることを示す。
ある$e_1…,e_k\in \mathbb{Z}$に対して$1=i_1^{e_1}…i_k^{e_k}$とする。$i_1^{|e_1|}…i_k^{|e_k |}=i_1^{e_1+|e_1|}…i_k^{e_k+|e_1|}$と書けるが、命題4より$0=e_1…=e_k$となる。
もっといい証明があると思います。
系として次の命題が導けます。
- $n\in\mathbb{Z}\backslash(0)$に対して$〈1+n\mathbb{Z}〉$は非有限生成。
- $K$を有限体とする。$〈1+xK[x]〉$は非有限生成。
この系から次が言えます。
- 加法群が有限生成な体は有限体
- 乗法群が有限生成な体は有限体
(1)
(標数0の場合)
有理数体の加法群が非有限生成であることを示せばよい。
$\mathbb Q/\mathbb Z$の任意の元は有限位数であるが$\mathbb Q/\mathbb Z$は無限集合であるので$\mathbb Q$は非有限生成である。
(標数$p$の場合)
$K$を標数$p$で加法群が有限生成な体とすると$pK=0$なので$K$の任意の元は有限位数であり、有限生成性より$K$は有限体である。
(2)
(標数0の場合)
有理数体の乗法群が有限生成でないことを示せばよい。
例えば$〈2\mathbb Z+1〉\subset \mathbb Q^×$は有限生成ではないので$\mathbb Q^×$も有限生成ではない。
(標数$p$の場合)
$K$を標数$p$で加法群が有限生成な体とすると、$K^×$が有限位数の元しか持たないならば乗法群の有限生成性より$K$は有限体。$K^×$が非有限な位数の元$x\in K$を持つと仮定すると、これは$\mathbb F_p$上既約であり、よって$〈1+x\mathbb F_p[x]〉\subset K^×$も有限生成ではないので$K^×$も有限生成でない。
つまり加法や乗法の有限生成というものは完全に一致してくれるということです。
ところで体の拡大について、ベクトル空間(加法)としての有限生成と
代数としての有限生成性
は一致してくれます。これは加法乗法の場合と似ている気がします。
代数というものに乗法的な意味合いがあるとか解釈して、この2つを上手く関連づけられないでしょうか。一元体という概念があるらしいですが、これと繋がりを見れないのでしょうか。