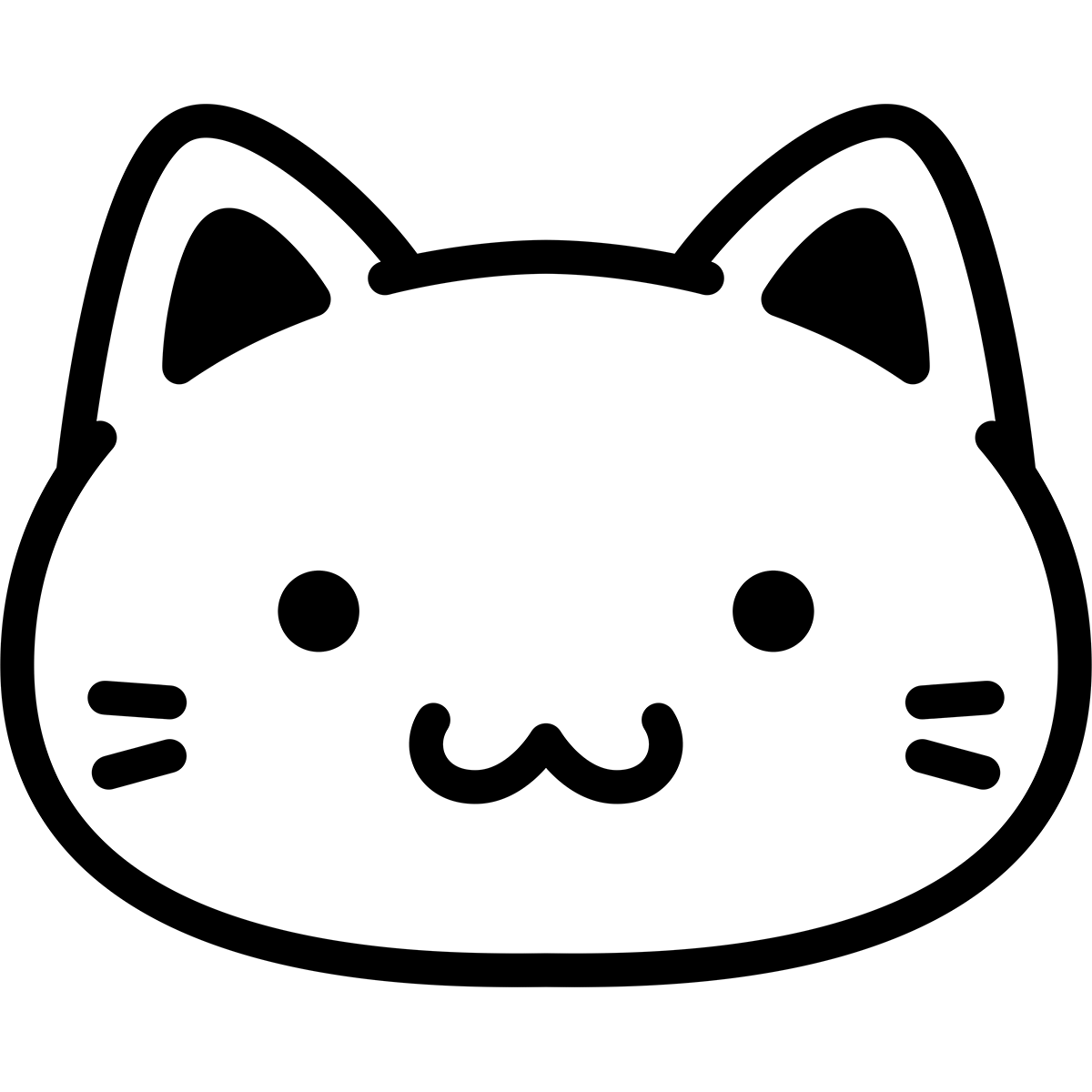直交多項式と超幾何関数(3)〜直交多項式と三項間漸化式・核多項式〜
第三回目となる本記事では、
直交多項式が満たす重要な特徴の1つである、
三項間漸化式について書くことにする。
また、
三項間漸化式と結びつく核多項式について、
前回のモーメント法の証明内にも顔を出していたことから
この記事では併せて紹介することにする。 #長文になりすみません
前回の復習
前回は、直交多項式を定義した。本記事における定義は次のようであった。
$\mathbb{R}$上のベクトル空間$\mathbb{R}[x]$(多項式環)を考える。
適当な区間$[a,b]$(実数全区間でも良い)の上の重み関数$w(x)$は
* 任意の$j\ge0$に対し$\mu_j:=\displaystyle \int_a^b x^jw(x)dx$は有限の値を取り、かつ$\mu_0>0$
という条件を満たすことを仮定する。
この時$\mathbb{R}[x]$の2つの多項式$f, g$に対して次の内積
\begin{align*}
\langle f, g\rangle := \int_a^b f(x)g(x)w(x)dx
\end{align*}
を考えるとこれは内積の定義を満たし、この内積で内積空間になる。
シュミットの直交化法を行うことで、$\mathbb{R}[x]$の基底$\{P_n(x)\}_{n=0}^\infty$であって
- $P_n(x)$は$n$次多項式
- 任意の$m\neq n$に対し$\langle P_m(x), P_n(x)\rangle=0$
- 任意の$n$に対し$\langle P_n(x), P_n(x)\rangle\neq0$
を満たすものを取ってくることができる。
この多項式列$\{P_n(x)\}_{n=0}^\infty$を重み関数$w(x)$に関する区間$(a, b)$上の直交多項式列という。
すなわち直交多項式とは、ある重み関数に関する内積を考え、その上で多項式環というベクトル空間を(次数に沿って)直交化した基底である、と定めた。
具体的な例はチェビシェフ多項式があり、
- 区間 $(-1, 1)$上の重み関数$w(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\Rightarrow$ 第一種チェビシェフ多項式 $T_n(x)$ - 区間 $(-1, 1)$上の重み関数$w(x)=\sqrt{1-x^2}$
$\Rightarrow$ 第二種チェビシェフ多項式 $U_n(x)$
が与えられていた。しかしシュミットの直交化法に従って係数を決めるのは一般的には難しい、というところで記事が終えられていた。
今回は、チェビシェフ多項式が満たした
\begin{align*}
T_{n+2}(x)-2xT_{n-1}(x)+T_n(x)&=0, \,\, T_0(x)=1, \,\, T_1(x)=x \\
U_{n+2}(x)-2xU_{n-1}(x)+U_n(x)&=0, \,\, U_0(x)=1, \,\, U_1(x)=2x
\end{align*}
のような三項間漸化式が一般的に導かれることを示そうと思う。
直交多項式の満たす三項間漸化式
さて、早速
本記事の主定理に入ろうと思う。
ここで記号の定義だが、多項式の空間上のモーメント作用素$\mathscr{L}$を次で定める。
\begin{align*}
\mathscr{L}[f(x)]
=\int_a^bf(x)\mu(x)dx
=\sum_k a_k\mu_k \quad (\text{ただし $f(x)=\sum_k a_kx^k$ とおいた})
\end{align*}
これは内積の記号を用いて書くと$\langle 1, \,f(x)\rangle$に等しい。
簡便のために以下この記号を用いることにする。
次が従う。
上で与えられた直交多項式列$P_n(x)=\sum_{k=0}^n a_k^{(n)}x^k$と、それに付随する内積$\langle *, * \rangle$に対して、以下の三項間漸化式が成立する。
\begin{align*}
P_{n+1}(x)=
\left(\frac{a_{n+1}^{(n+1)}}{a_n^{(n)}}x
-\frac{a_{n+1}^{(n+1)}}{a_n^{(n)}}
\frac{\mathscr{L}[xP_n^2(x)]}{\mathscr{L}[P_n^2(x)]}
\right)P_n(x)
-\frac{a_{n+1}^{(n+1)}a_{n-1}^{(n-1)}}{(a_{n}^{(n)})^2}
\frac{\mathscr{L}[P_n^2(x)]}{\mathscr{L}[P_{n-1}^2(x)]}
P_{n-1}(x)
\end{align*}
すなわち、各$P_n(x)$を最高次係数$a_n^{(n)}$で割って最高次係数を$1$の多項式$\widetilde{P}_n(x)$にする(モニック多項式)と、次のように書ける:
\begin{align*}
\widetilde{P}_{n+1}(x)=
\left(x-\frac{\mathscr{L}[x\widetilde{P}_n^2(x)]}
{\mathscr{L}[\widetilde{P}_n^2(x)]}
\right)\widetilde{P}_n(x)
-\frac{\mathscr{L}[\widetilde{P}_n^2(x)]}
{\mathscr{L}[\widetilde{P}_{n-1}^2(x)]}
\widetilde{P}_{n-1}(x)
\end{align*}
ただしこの時初項は$\widetilde{P}_0(x)=1$と$\widetilde{P}_1(x)=x-\frac{\mathscr{L}[x]}{\mathscr{L}[1]}=x+\frac{a_0^{(1)}}{a_1^{(1)}}$
note: この三項間漸化式を扱う際には、以下モニックにしたものを中心に考える。
また、$n$の添字はこれで扱う(チェビシェフで導入したものとはズレてる)
その際の注意としては、最高次係数で割るとモーメントの値がその分ズレることである。
すなわち
\begin{align*}
\frac{\mathscr{L}[\widetilde{P}_n^2(x)]}
{\mathscr{L}[\widetilde{P}_{n-1}^2(x)]}
\widetilde{P}_{n-1}(x)
&=
\frac{\mathscr{L}[(a_n^{(n)})^{-1}P_n^2(x)]}
{\mathscr{L}[(a_{n-1}^{(n-1)})^{-1}P_{n-1}^2(x)]}
\frac{P_{n-1}(x)}{(a_{n-1}^{(n-1)})^{-1}} \\
&=
\frac{(a_{n-1}^{(n-1)})^2}{a_n^{(n)}}
\frac{\mathscr{L}[P_n^2(x)]}
{\mathscr{L}[P_{n-1}^2(x)]}
P_{n-1}(x)
\end{align*}
などの変形により、非モニックの場合の漸化式の整合性は確かめられるだろう。
note: 結局一般項のモーメントが必要じゃねーかって苦情は、もう少し待ってほしい。
(その主張は正しい:一般項は他の手段で求める)
note: 任意の$k$に対し$\mathscr{L}[P_k^2]=1$という正規化条件を課すと、
\begin{align*}
\widetilde{P}_{n+1}(x)=
\left\{x-\mathscr{L}[xP_n^2(x)]\right\}\widetilde{P}_n(x)
-\widetilde{P}_{n-1}(x)
\end{align*}
とさらに綺麗な形の漸化式を得るが、今はここまでは仮定しない。 #正規化は強い
大事なことは、「すべての」直交多項式列に対して、
$P_{n+1}(x)=(\text{$x$ の $1$ 次式})P_n(x)-(\text{$x$ に依らない数})P_{n-1}(x)$
の形の三項間漸化式が成り立つ、ということである。
#$n$には依っていいよ
上の注意から、$P_n(x)$はモニックの場合を示す。(一般の場合は係数で割るだけ)
多項式$xP_n(x)$を考える。これはモニックな$n+1$次多項式。
$\{P_k(x)\}_{k=0}^{n+1}$は直交多項式列であるので$n+1$次以下の多項式の空間を張る、という事実を思い出すと、この基底に関して展開ができる。
\begin{align*}
xP_n(x)
=\sum_{k=0}^{n+1}a_{n,k}P_k(x)
\end{align*}
そこで各$P_l(x)$(ただし$0\le l\le n+1$)との内積を取ると、
\begin{align*}
\langle xP_n(x), P_l(x)\rangle
&=\sum_{k=0}^{n+1}a_{n,k}\langle P_k(x), P_l(x)\rangle \\
&=\sum_{k=0}^{n+1}a_{n,k}\mathscr{L}[P_k^2(x)]\delta_{k,l} \quad (\text{直交性}) \\
&=a_{n,l}\mathscr{L}[P_l^2(x)]
\end{align*}
となるので、展開係数$a_{n,k}$の明示式$\displaystyle a_{n,k} = \frac{\langle xP_n(x), P_k(x)\rangle}{\mathscr{L}[P_k^2(x)]}$を得る。
ここで内積の定義から
\begin{align*}
\langle xP_n(x), P_k(x)\rangle
=\langle xP_k(x), P_n(x)\rangle
\end{align*}
と交換ができて、$xP_k(x)$は$k+1$次式だから、直交性より$k$が$n-2$以下のときにこの展開係数$a_{n,k}=0$であることがわかる。
したがって、次の形の三項間漸化式が従うことがわかる。
\begin{align*}
&xP_n(x)=P_{n+1}(x)+a_{n,n}P_n(x)+a_{n,n-1}P_{n-1}(x) \\
&\Leftrightarrow
P_{n+1}(x)-(x-a_{n,n})P_n(x)+a_{n,n-1}P_{n-1}(x)=0
\end{align*}
さらに展開係数の明示式から、漸化式の係数を計算できる。
\begin{align*}
a_{n,n}
&=\frac{\langle xP_n(x), P_n(x)\rangle}
{\mathscr{L}[P_n^2(x)]}
=\frac{{\mathscr{L}[xP_n^2(x)]}}{{\mathscr{L}[P_n^2(x)]}} \\
a_{n,n-1}
&=\frac{\langle xP_n(x), P_{n-1}(x)\rangle}
{\mathscr{L}[P_{n-1}^2(x)]}
\end{align*}
さて、最後の項の分子$\langle xP_n(x), P_{n-1}(x)\rangle$をもう少し綺麗な形にしたい。
そのために、今求めた漸化式の$n$を$1$下げて
\begin{align*}
xP_{n-1}(x)=P_n(x)+a_{n-1,n-1}P_{n-1}(x)+a_{n-1,n-2}P_{n-2}(x)
\end{align*}
を得る。以上より
\begin{align*}
\langle xP_n(x), P_{n-1}(x)\rangle
&=\langle xP_{n-1}(x), P_n(x)\rangle \quad (\text{内積の交換}) \\
&=\langle P_n(x)+a_{n-1,n-1}P_{n-1}(x)+a_{n-1,n-2}P_{n-2}(x), \, P_n(x)\rangle \\
&=\langle P_n(x), \, P_n(x)\rangle \quad (\text{直交性}) \\
&=\mathscr{L}[P_n^2(x)]
\end{align*}
がわかり、$\displaystyle a_{n,n-1}
=\frac{\mathscr{L}[P_n^2(x)]}{\mathscr{L}[P_{n-1}^2(x)]}$の式も導出することができた。
最後の文に関しては、$\langle P_0(x), P_1(x)\rangle=0$を考えると$\frac{\mathscr{L}[x]}{\mathscr{L}[1]}=\frac{a_0^{(1)}}{a_1^{(1)}}$が従う。
ここに関しては中括弧の中に$n=0$を代入したものと一致しているということがミソである。(証明終わり)
後半は内積の値を整理していただけなので、実質証明前半が肝であった。
直交性でズバズバ消えて、3項間だけ残った、そんな感じである。
チェビシェフ多項式で確認
さて、チェビシェフ多項式においては、前々回の記事(1)で
直交性を示した定理(定理3)から、長さが計算できていた。
復習すると
\begin{align*}
\int_{-1}^1 T_i(x)T_j(x)\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}
&=\begin{cases}
\pi & (i=j=0) \\
\frac{\pi}{2}\delta_{ij} & (\text{それ以外})
\end{cases} \\
\int_{-1}^1 U_i(x)U_j(x)\sqrt{1-x^2}dx
&=\frac{\pi}{2}\delta_{ij}
\end{align*}
などとなっていた。そこで今の三項間漸化式のところに当てはめる。
面倒なので、$T_0$は考えないことにする。($n\ge1$とする)
すると$\mathscr{L}[T_i^2(x)]=\mathscr{L}[U_i^2(x)]=\frac{\pi}{2}$となる。
あとは$\mathscr{L}[xT_i^2(x)]$や$\mathscr{L}[xU_i^2(x)]$を計算すれば良い。
しかし、$xT_i^2(x)$や$xU_i^2(x)$は奇関数なので(ここ大事!)
これらのモーメントは$0$になることがわかる。
そして最後に、$T_n(x)$や$U_n(x)$の最高次係数がそれぞれ$2^{n-1}, 2^n$であったので
上の定理を使うと、たとえば$T_n(x)$の場合の漸化式が$n\ge2$で
\begin{align*}
T_{n+1}(x)
&=
\left(\frac{2^n}{2^{n-1}}x
-\frac{2^n}{2^{n-1}}\frac{0}{\pi/2}
\right)T_n(x)
-\frac{2^n\cdot 2^{n-2}}{(2^{n-1})^2}\frac{\pi/2}{\pi/2}
T_{n-1}(x) \\
&=
2xT_n(x)-T_{n-1}(x)
\end{align*}
と求められることがわかる。第二種$U_n(x)$に関しても同様。
なお、上で述べた$xT_i^2(x)$のモーメントが消えるという話は
次のような形で定式化・概念化なされている。
対称な直交多項式
対称(symmetric)という言葉がある。
この言葉は様々な場面で様々な意味に用いられるのだが、
直交多項式においては次のような定義である。
直交多項式が対称であるとは、全ての奇数次のモーメントが消えていることを指す。
式で書くならば、
任意の$k\ge0$に対し$\mu_{2k+1}(=\mathscr{L}[P_{2k+1}(x)^2])=0$が成り立つことである。
すぐわかるように、上の条件は次と同値である。
- $P_n(x)$は$n$が偶数の時に偶関数、奇数の時に奇関数
- 漸化式の$P_n(x)$の係数である$x$の1次式に定数項がない
チェビシェフ多項式やそれに類似する多項式列(数回後の記事の予定)などで成り立つ特徴である。
さて、今までは直交多項式から三項間漸化式を導くことを考えていたが、
逆に三項間漸化式の方から直交多項式を定義することができる。
三項間漸化式による直交多項式の定義
Jean Favard (1902-1965)の名前がつけられている定理。
ただし彼以前にスティルチェスなどにより何回か発見されていたようである。
主張は以下のようである。
$\{c_n\}_{n=0}^\infty$と$\{\lambda_n\}_{n=0}^\infty$を複素数列、そして$P_n(x)$を次で定められる$n$次多項式列とする。
\begin{align*}
\left\{
\begin{aligned}
&P_{n+1}(x)=(x-c_n)P_n(x)-\lambda_nP_{n-1}(x) \\
&P_0(x)=1, \quad P_1(x)=x-c_0
\end{aligned}
\right.
\end{align*}
この時以下を満たすモーメント作用素$\mathscr{L}$が一意的に存在する。
\begin{align*}
\mathscr{L}[1]=\lambda_0, \quad
\mathscr{L}[P_m(x)P_n(x)]=0 \quad (m\neq n)
\end{align*}
note: 添字はあえて1つずらした
note: 直交多項式列になるためには、任意の$n$で$\lambda_n\neq0$の条件が必要。
一般に
$P_{n+1}(x)=(\text{$x$ の $1$ 次式})P_n(x)-(\text{$x$ に依らない数})P_{n-1}(x)$
の形の数列に対し、$x$の$1$次の係数は$P_n(x)$の最高次係数に関わる項である。
$P_n(x)$をそれの$n$乗とかで割ってあげると「$x$の$1$次の係数=$1$」にすることができ、上のFavardの定理から直交多項式を定める内積=モーメント作用素を定めることができる。
しかもその内積は一意的なので、直交多項式を逆に三項間漸化式の方から定めることが可能というわけである。
・まず最初に$n$次のモーメント$\mathscr{L}[x^n]=\mu_n$を作る。
$n=0$の時は仮定から$\mu_0=\lambda_0$ととる。
次に$n=1$の時は、$P_1(x)=x-c_0$なので
\begin{align*}
0&=\mathscr{L}[P_0(x)P_1(x)] \\
&=\mathscr{L}[x-c_0] \\
&=\mathscr{L}[x]-c_0\mathscr{L}[1] \\
&=\mu_1-c_0\mu_0 \\
\end{align*}
が直交性から従う。ゆえに$\mu_1=c_0\mu_0=c_0\lambda_0$とすべき。
同様に、帰納的に$\mu_{n+1}$を定めることを考えると
\begin{align*}
0&=\mathscr{L}[P_0(x)P_{n+1}(x)] \\
&=\mathscr{L}[P_{n+1}(x)] \\
&=\mathscr{L}\left[\sum_{k=0}^{n+1}a_kx^k\right] \quad (\text{$a_k$ は $\{c_n\}$ と $\{\lambda_n\}$ から作れる係数。ただし $a_{n+1}=1$})\\
&=\mathscr{L}[x^{n+1}]-\sum_{k=0}^na_k\mathscr{L}[x^k]
\end{align*}
が従うので、$\mathscr{L}[x^{n+1}]=\sum_{k=0}^na_k\mu_k$とすべきである。
・次はこのように定めた線形汎函数$\mathscr{L}$が直交性を満たすことを示す。
$P_m(x)=\sum_{k=0}^ma_kx^k$とおき、さらに$m< n$とする。
この時
\begin{align*}
\mathscr{L}[P_m(x)P_n(x)]
&=\mathscr{L}\left[\sum_{k=0}^ma_kx^kP_n(x)\right] \\
&=\sum_{k=0}^ma_k\mathscr{L}[x^kP_n(x)]
\end{align*}
であるので、各$0\le k\le m(< n)$なる$k$について$\mathscr{L}[x^kP_n(x)]=0$を示す。
$k=0$のとき、任意の$n\ge1$に対して$\mathscr{L}[P_n(x)]=0$であることは、上の$\mathscr{L}$の作り方からそうであった。
次に漸化式から
\begin{align*}
xP_n(x)=P_{n+1}(x)+c_nP_n(x)+\lambda_nP_{n-1}(x)
\end{align*}
と書けており、この式に$x^{k-1}$を掛け$\mathscr{L}$を作用させると
\begin{align*}
\mathscr{L}[x^kP_n(x)]
&=\mathscr{L}[x^{k-1}P_{n+1}(x)]
+c_n\mathscr{L}[x^{k-1}P_n(x)]
+\lambda_n\mathscr{L}[x^{k-1}P_{n-1}(x)] \\
&=0 \quad (\text{$k$ に関する帰納法の仮定より})
\end{align*}
がわかる。
以上より直交性$\mathscr{L}[P_m(x)P_n(x)]=0$が示された。(証明終わり)
ということで、これで三項間漸化式が直交多項式そのものを表していることの証明ができたことになる。
三項間漸化式には他にも興味深い性質があるので紹介する。
三項間漸化式の性質
まずは Christoffel–Darboux の公式。
Elwin Bruno Christoffel (1829-1900)、Jean Gaston Darboux (1842-1917) は
ともに名が他分野でよく知られているだろう。
前者は一般相対性理論などリーマン幾何のクリストッフェル記号、
後者はリーマン積分におけるダルブーの定理など。
さて定理の主張を述べる。
$P_n(x)$はmonic型の漸化式を満たす($\Leftrightarrow$ 任意の$P_n(x)$がmonicの)直交多項式とする。
このとき
\begin{align*}
\sum_{k=0}^n
\frac{P_k(x)P_k(y)}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_k}
=\frac{1}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_n}
\frac{P_{n+1}(x)P_n(y)-P_n(x)P_{n+1}(y)}{x-y}
\end{align*}
特に$y\to x$の極限を取ると、次が従う。
上の定理と同じ条件で次が従う。
\begin{align*}
\sum_{k=0}^n
\frac{P_k(x)^2}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_k}
=\frac{P_{n+1}'(x)P_n(x)-P_n'(x)P_{n+1}(x)}
{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_n}
\end{align*}
これが何と関連しているのかは、次の記事に回そうと思う。
とりあえず今は上の Christoffel–Darboux の公式の証明をする。
直交多項式のモニック型三項間漸化式
\begin{align*}
xP_k(x)=P_{k+1}(x)+c_kP_k(x)+\lambda_kP_{k-1}(x)
\end{align*}
の両辺に$P_k(y)$を掛けて、次を得る。
\begin{align*}
xP_k(x)P_k(y)
=P_{k+1}(x)P_k(y)+c_kP_k(x)P_k(y)+\lambda_kP_{k-1}(x)P_k(y)
\tag{1}
\end{align*}
(1)式の両辺で変数$x$と$y$を入れ替えたものが(2)式である。
\begin{align*}
yP_k(y)P_k(x)
=P_{k+1}(y)P_k(x)+c_kP_k(y)P_k(x)+\lambda_kP_{k-1}(y)P_k(x)
\tag{2}
\end{align*}
(1)から(2)式を引くと、次のようになる。
\begin{align*}
&(x-y)P_k(x)P_k(y) \\
&\quad=
(P_{k+1}(x)P_k(y)-P_{k+1}(y)P_k(x))
+\lambda_k(P_{k-1}(x)P_k(y)-P_{k-1}(y)P_k(x))
\end{align*}
以下簡略のため$u_k(x,y)=P_{k+1}(x)P_k(y)-P_{k+1}(y)P_k(x)$とおく。
すると上の式は
\begin{align*}
(x-y)P_k(x)P_k(y)=u_k(x,y)-\lambda_ku_{k-1}(x,y)
\end{align*}
と書き表せる。
$x-y$と$\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_k$の両方で割って
\begin{align*}
\frac{P_k(x)P_k(y)}{\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_k}
=\frac{1}{x-y}\left\{
\frac{u_k(x,y)}{\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_k}
-\frac{u_{k-1}(x,y)}{\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_{k-1}}
\right\}
\end{align*}
である。そして和を取ることで右辺の途中項が消えていき
\begin{align*}
\sum_{k=0}^n
\frac{P_k(x)P_k(y)}{\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_k}
&=\frac{1}{x-y}
\frac{u_n(x,y)}{\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n}
\end{align*}
がわかり、Christoffel–Darboux の公式が示された。(証明終わり)
ちなみに$\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_k$という値は、今のmonicの場合には$\mathcal{L}[P_k(x)^2]$と書き表すことができるので、正規化されているとこの分母も消えてしまう。
すると正規化された Christoffel–Darboux の公式が
\begin{align*}
\sum_{k=0}^nP_k(x)P_k(y)
=\frac{P_{n+1}(x)P_n(y)-P_n(x)P_{n+1}(y)}{x-y}
\end{align*}
などとさらに簡単な形で書き表される。
正規化されているかどうかに関わらず
左辺は大事な関数であり、前記事(2)の証明中でも出てきたので、定義しておく。
核多項式
直交多項式$\{P_n(x)\}$に対し、その核多項式$K_n(x, y)$を
\begin{align*}
K_n(x, y)=\sum_{k=0}^n
\frac{P_k(x)P_k(y)}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_k}
=\sum_{k=0}^n
\frac{P_k(x)P_k(y)}{\mathcal{L}[P_k(x)^2]}
\end{align*}
で定める。
note: 複素数上に定義された直交多項式だと共役が必要。(そもそも内積自体)
note: 各基底$P_n(x)$の長さの1/2乗で調整した直交多項式$p_n(x)$を
\begin{align*}
p_n(x)=\frac{P_n(x)}
{(\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_k)^{\frac{1}{2}}}
\end{align*}
として書くことがよくある。この記法の下では核多項式は
\begin{align*}
K_n(x, y)=\sum_{k=0}^np_k(x)p_k(y)
\end{align*}
として(正規化仮定抜きに)綺麗に書き表すことができている。
核多項式については幾つか面白い性質が知られている。
核多項式$K_n(x, y)$と、$n$次以下のすべての多項式$f(x)$に対し、以下の式が成り立つ。
\begin{align*}
\mathcal{L}[f(x)K_n(x, y)]=f(y)
\end{align*}
これは前記事(2)のモーメント法での証明内に、ほぼ似た記述がある。
多項式$f(x)$を直交多項式$\{P_n(x)\}$で展開するときの係数を
\begin{align*}
f(x)=\sum_{k=0}^Nc_kP_k(x)
\end{align*}
とおくと($N\le n$に注意)、左辺は
\begin{align*}
\mathcal{L}[f(x)K_n(x, y)]
&=
\int_a^b
\left\{\sum_{k=0}^Nc_kP_k(x)\right\}
\left\{\sum_{l=0}^n
\frac{P_l(x)P_l(y)}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_l}\right\}
w(x)dx \\
&=
\sum_{l=0}^n
\frac{P_l(y)}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_l}
\sum_{k=0}^Nc_k
\int_a^b P_k(x)P_l(x)w(x)dx \\
&=
\sum_{l=0}^n
\frac{P_l(y)}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_l}
\sum_{k=0}^Nc_k
\mathcal{L}[P_k(x)^2]\delta_{kl}
\quad (\text{直交性より}) \\
&=
\sum_{l=0}^N
\frac{P_l(y)}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_l}
c_l\mathcal{L}[P_l(x)^2]
\quad (\text{和を取る範囲は $N$ 以下になる}) \\
&=
\sum_{l=0}^Nc_lP_l(y)
=f(y)
\end{align*}
のように変形ができる。(証明終わり)
$P_n(x)$を直交多項式とし、実数の定数$\kappa$を一つ固定する。
ただし重要な仮定をおく:任意の$n$に対して$P_n(\kappa)\neq0$
この時次のようにしてモニック直交多項式列$\{P_n^*(\kappa; x)\}$が定義できる。
\begin{align*}
P_n^*(\kappa; x)
&:=P_n(\kappa)^{-1}
\frac{P_n(\kappa)P_{n+1}(x)-P_{n+1}(\kappa)P_n(x)}{x-\kappa} \\
&=
\frac{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_n}{P_n(\kappa)}K_n(\kappa, x)
\end{align*}
ただしこの直交多項式に関するモーメントは次のように書ける。
\begin{align*}
\mathcal{L}_\kappa^*[x^n]
&:=\mathcal{L}[x^{n+1}]-\kappa\mathcal{L}[x^n]
=\int_a^bx^n(x-\kappa)w(x)dx
\end{align*}
別の言い方をすれば、$\{P_n^*(\kappa; x)\}$は重さ$w_\kappa^*(x):=(x-\kappa)w(x)$に関する直交多項式列である。
なおこのモーメントに対する基底の長さは
\begin{align*}
\mathcal{L}_\kappa^*[P_n^*(\kappa; x)^2]
=-\frac{P_{n+1}(\kappa)}{P_n(\kappa)}
\mathcal{L}[P_n(x)^2]
\end{align*}
のようにも表示がある。
このように定められた$\{P_n^*(\kappa; x)\}$を$K$-パラメーター$\kappa$の核直交多項式 (kernel orthogonal polynomial) と言う。
重み関数$w(x)$に$x$の1次式を掛ける、という特徴づけは今後また別の場所で出てくる。
ともあれ、既存の直交多項式列から別の直交多項式列を生み出す手段が見つかった。
Question: $\mathcal{L}_\kappa^*[xP_n^*(\kappa; x)^2]$は元の$\mathcal{L}$で書き表せるのか?→これが出来れば三項間漸化式
→多分あまり綺麗には書けなさそう
さて、上の定理の証明を述べる。
上のように定義した多項式$P_n^*(\kappa; x)$がモニック多項式になることは明らか。
(因数定理を考えて分数は割れていて多項式になる、最高次係数は割って調節してある)
その次の$P_n^*(\kappa; x)$の書き換えは、Christoffel–Darboux の公式から従う。
よって、以下示すべきことは次の2つである:
- $\mathcal{L}_\kappa^*$のモーメントで直交多項式になる
- $\mathcal{L}_\kappa^*[P_n^*(\kappa; x)^2]$の値の計算
これは同時に示せる。以下$m\le n$とすると
\begin{align*}
\mathcal{L}_\kappa^*[x^mP_n^*(\kappa; x)]
&=\mathcal{L}[(x-\kappa)x^mP_n^*(\kappa; x)] \\
&=\mathcal{L}\left[(x-\kappa)x^m
P_n(\kappa)^{-1}
\frac{P_n(\kappa)P_{n+1}(x)-P_{n+1}(\kappa)P_n(x)}{x-\kappa}\right] \\
&=P_n(\kappa)^{-1}
\mathcal{L}[x^m\{P_n(\kappa)P_{n+1}(x)-P_{n+1}(\kappa)P_n(x)\}] \\
&=
\mathcal{L}[x^mP_{n+1}(x)]
-\frac{P_{n+1}(\kappa)}{P_n(\kappa)}\mathcal{L}[x^mP_n(x)] \\
&=
-\frac{P_{n+1}(\kappa)}{P_n(\kappa)}\mathcal{L}[P_n(x)^2]\delta_{mn} \quad (\text{直交性、$P_n(x)$: モニックに注意})
\end{align*}
となることから、直交性が示され、
さらに長さの2乗についても値を確かめることができた。(証明終わり)
まとめ
今回はややボリュームが増えてしまったが
まず1つめに
直交多項式に付随する三項間漸化式、逆に三項間漸化式から直交多項式系の内積を作れること、
これらを見ることで
直交多項式と三項間漸化式がほぼ同じものを与えていることを見た。
次に、三項間漸化式の系でChristoffel–Darboux の公式を与えた。
これは核多項式の値が綺麗に計算できる主張で
それにちなんで
核多項式に関する再生性とそこから派生する核直交多項式についての
定義と性質を与えた。
次の記事からは
この核多項式に関わる、
より大切な性質を述べていこうと思う。