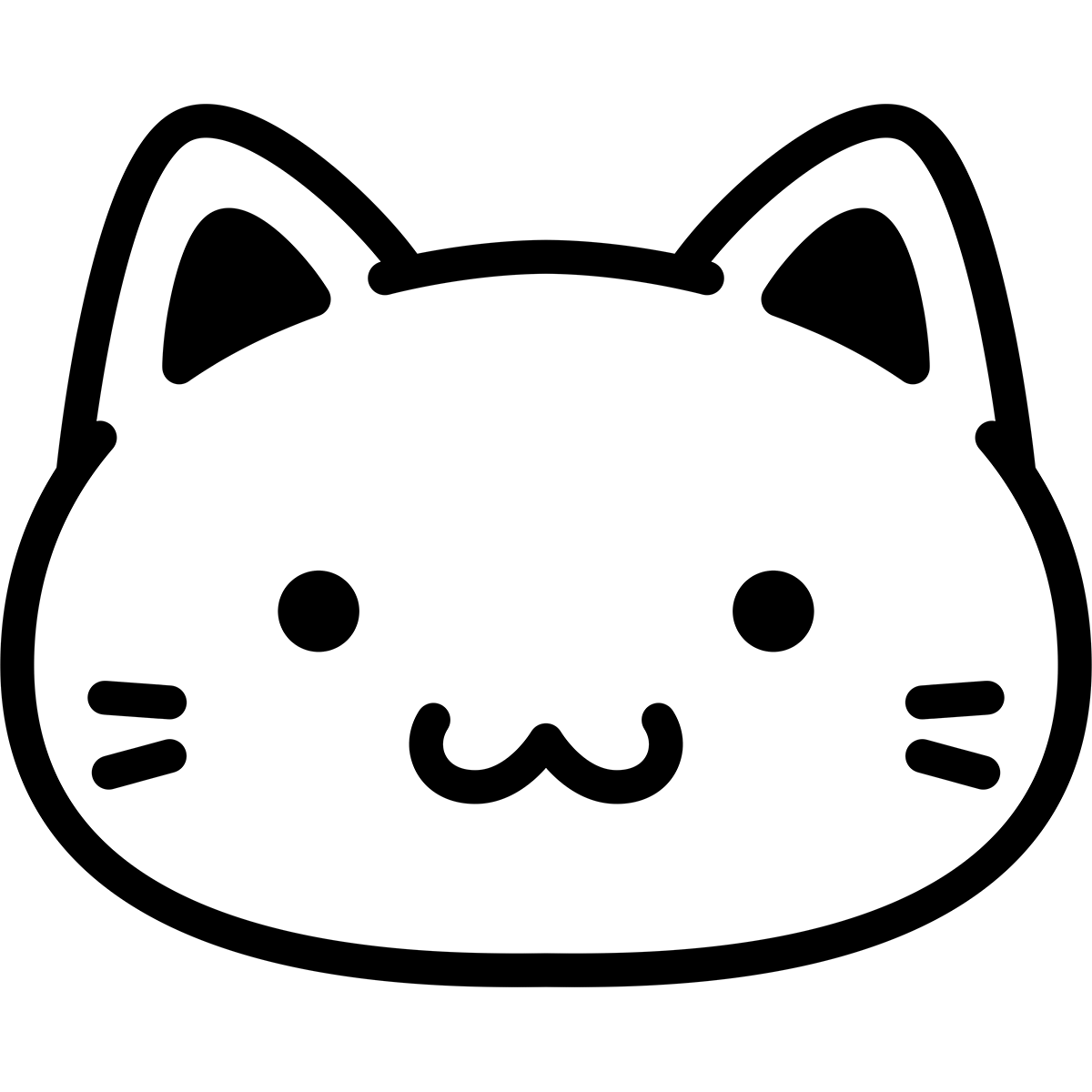直交多項式と超幾何関数(4)〜直交多項式の零点・ガウス求積法〜
第四回目の今回は、
直交多項式の零点と、それに付随した話題であるガウス求積法について述べようと思う。
残念ながら現在のところ与えている直交多項式の例が、チェビシェフ多項式しかなく
(ここの順番はすごく迷うところではあったが)
でも他の直交多項式は零点の計算ができる方が珍しく、
これでいっか。そんな感じである。
チェビシェフ多項式の零点
第一種・第二種チェビシェフ多項式は、次の形で与えられるものであった。
第一種・第二種チェビシェフ多項式$\{T_n(x)\}, \{U_n(x)\}$は次で特徴づけられている。
\begin{align*}
\cos n\theta = T_n(\cos\theta), \quad
\sin (n+1)\theta = U_n(\cos\theta)\sin\theta
\end{align*}
多項式の零点を調べるにあたり、この式が1番使いやすい。
例えば第一種の場合は
\begin{align*}
T_n(x)= 0 \Leftrightarrow
\cos n\theta = 0 \Leftrightarrow
\theta = \frac{\pi}{2n}, \frac{3\pi}{2n}, \cdots, \frac{(2n-1)\pi}{2n}
\Leftrightarrow
x = \cos\frac{\pi}{2n}, \cos\frac{3\pi}{2n}, \cdots, \cos\frac{(2n-1)\pi}{2n}
\end{align*}
などと、三角関数の表示を用いることで零点が書き表せた。
同様に第二種の場合も調べておくと
\begin{align*}
U_n(x) = 0 \Leftrightarrow
\sin(n+1)\theta=0,\,\, \sin\theta\neq0 \Leftrightarrow
\theta = \frac{\pi}{n+1}, \frac{2\pi}{n+1}, \cdots, \frac{n\pi}{n+1}
\Leftrightarrow
x = \cos\frac{\pi}{n+1}, \cos\frac{2\pi}{n+1}, \cdots, \cos\frac{n\pi}{n+1}
\end{align*}
と書き下すことができた。
すなわち、因数定理により、次の積表示を持つと言い換えることができる。
第一種・第二種チェビシェフ多項式$\{T_n(x)\}, \{U_n(x)\}$は次のように実係数で因数分解できる。
\begin{align*}
T_n(x)=2^{n-1}\prod_{k=1}^n
\left(x - \cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right), \quad
U_n(x)=2^n\prod_{k=1}^n
\left(x - \cos\frac{k\pi}{n+1}\right)
\end{align*}
さてこの積表示が大事、と言うよりかは、各$n$番目の多項式の零点分布が大事である。
$n$番目の多項式$T_n(x), U_n(x)$の零点のうち、小さい方から$i$番目の値を$x_{n, i}^T,\, x_{n, i}^U$とおく。
すなわち、上の議論からそれぞれの値は明示的に
\begin{align*}
x_{n, i}^T = \cos\frac{(2n+1-2i)\pi}{2n}, \quad
x_{n, i}^U = \cos\frac{(n+1-i)\pi}{n+1}
\end{align*}
と書くことができる。
(関数$\cos$は単調減少なので、添え字が逆転することに注意)
これらの零点分布は、ともに重要な性質 $x_{n+1,i} < x_{n,i} < x_{n+1, i+1}$ を満たす。
チェビシェフ不等式の場合は、全ての零点の値が求まっているので、具体的に計算で示せる。
(その際に関数$\cos$の単調減少性から、偏角の逆向きの不等号を示すことに注意)
まずは第一種のとき。$x_{n+1,i} < x_{n,i} < x_{n+1, i+1}$を示すために偏角の逆向きの不等式
\begin{align*}
\frac{(2n+1-2i)\pi}{2(n+1)}<\frac{(2n+1-2i)\pi}{2n}<\frac{(2n+3-2i)\pi}{2(n+1)}
\end{align*}
を示せば良い。左側の不等式は明らかなので、右側の不等式を示す。
\begin{align*}
\frac{(2n+3-2i)\pi}{2(n+1)}-\frac{(2n+1-2i)\pi}{2n}
=\frac{(2i-1)\pi}{2n(n+1)}>0 \quad (\text{$i$ は $1$ 以上の自然数なので})
\end{align*}
となり、示すことができた。第二種についてもほぼ同じ。(証明終わり)
この性質が言うことは、$n+1$番目の多項式の零点$n+1$個の間に
$n$番目の多項式の零点$n$個がちょうど一つずつ入ることである。
あと、この零点の分布の幅についても考えてみる。
すなわち、小さい方から1番目の零点$x_{n,1}$と、大きい方から1番目の零点$x_{n,n}$について
例えば第一種の場合は
\begin{align*}
x_{n,1}^T = \cos\frac{(2n-1)\pi}{2n}, \quad
x_{n,n}^T = \cos\frac{\pi}{2n}
\end{align*}
となるので、左端$x_{n,1}^T$は$n$に関して単調減少、$\cos\pi=-1$に収束、
右端$x_{n,n}^T$は$n$に関して単調増加、$\cos0=1$に収束、となることがわかる。
この区間$[-1,\,\,1]$は、重み関数$w(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$の定義域と一致することに注意。
一般的な直交多項式の零点
さて、以上見た性質が、一般的な直交多項式に対して成立することを示す。
まずはじめに、先は当たり前すぎて触れなかったが、次のことを示さねばならない。
$\{P_n(x)\}$を直交多項式とする。
このとき、全ての$n$に対して$P_n(x)$は重解を持たない。
チェビシェフ多項式の場合は、全ての解が明示的に書き表されていたが、
そのような直交多項式は特別なもので
一般的には解くことさえままならない。より一般的に示すしかない。
実は一般には成り立たない。言葉を導入する。
$E$は実数の部分集合とする。($\pm\infty$を含めても良い)
モーメント関数$\mathcal{L}$が$E$上で正定値(positive-definite)であるとは
任意の「① $E$全体で$0$以上で ② 恒等的に$0$と等しくはない」実多項式$f(x)$に対し
$\mathcal{L}[f(x)]>0$となることである。
例えばチェビシェフ多項式の場合、重み関数 $w(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$もしくは$\sqrt{1-x^2}$は区間$(-1, 1)$の上で正であることを思うと、この区間の上で非負な非零多項式$f(x)$のモーメントが正になることは明らかであろう。
ここで注意すべきは、$n\ge1$に対する基底$T_n(x)$や$U_n(x)$はそのモーメントが$0$になるように作られている:これら関数は区間内で常に$0$以上などとはならない。
さて重要な定理をいくつか述べる。
$\mathcal{L}$を区間$I$上で正定値なモーメント関数、$\{P_n(x)\}$をそれに付随する直交多項式とする。
この時$n\ge1$に対し$P_n(x)$の零点は$n$個全てが実数かつ互いに異なり、そして$n$個全てが区間$I$の内部に入る。
これは一般的に零点の値を求められない直交多項式に対して、その存在を言っている。
まず各々の基底$P_n(x)$のモーメント$\mathcal{L}[P_n(x)]$は($n\ge1$で)$0$になるようにしていたことから、必ずこの区間内で正負が入れ替わる点が存在する。すなわち零点は一つ以上存在する。
次に$x_1, x_2, \cdots, x_m$を区間$I$に属する重複度奇数の零点全てとする。
このとき
$\rho(x)=(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_m)$
とおき、多項式$\rho(x)P_n(x)$を考える。
この多項式は重複度奇数の零点がなく、区間$I$で符号が同じである。
非負か非正だが、非正ならば$\rho(x)$の係数を$-1$倍することで$\rho(x)P_n(x)\ge0$とできる。
するとモーメント関数の正定値性の仮定から$\mathcal{L}[\rho(x)P_n(x)]>0$となる。
しかし仮に$\rho$の次数$m$が$n$未満だとこれは直交多項式の仮定に反する。
以上より$P_n(x)$は$n$個の重複度1の零点を$I$の中に持つことがわかった。(証明終わり)
以下$n$次直交多項式$P_n(x)$の零点$n$個を、小さい順に$x_{n,1}^P< x_{n,2}^P<\cdots< x_{n,n}^P$とおく。
このとき上のチェビシェフ多項式の例にあったように、次が成り立つ。
直交多項式$P_n(x)$の零点$x_{n,i}^P$(ただし$1\le i\le n$)に対し
不等式$x_{n+1,i}^P < x_{n,i}^P < x_{n+1, i+1}^P$が満たされている。
これの証明には、三項間漸化式から導いた合流型Christoffel–Darbouxの公式を使う。
合流型Christoffel–Darbouxの公式は次のようなものであった。
\begin{align*}
\sum_{k=0}^n
\frac{P_k(x)^2}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_k}
=\frac{P_{n+1}'(x)P_n(x)-P_n'(x)P_{n+1}(x)}
{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_n}
\end{align*}
特にここから不等式$P_{n+1}'(x)P_n(x)-P_n'(x)P_{n+1}(x)>0$が従う。
($\lambda_i$は正であり、かつ$P_0=1$なので左辺は0にはならない。)
今の不等式に$P_{n+1}(x)$の$i$番目の零点$x_{n+1,i}^P$を代入すると
$P_{n+1}'(x_{n+1,i}^P)P_n(x_{n+1,i}^P)>0$がわかる。
同様にして$P_{n+1}'(x_{n+1,i+1}^P)P_n(x_{n+1,i+1}^P)>0$も従う。
隣接する単根であることから$P_{n+1}'(x_{n+1,i}^P)$と$P_{n+1}'(x_{n+1,i+1}^P)$の符号は異なり
そのことから$P_n(x_{n+1,i}^P)$と$P_n(x_{n+1,i+1}^P)$の符号も異なる。
以上から$x_{n+1,i}^P$と$x_{n+1,i+1}^P$の間に少なくとも1つ$P_n(x)$の零点があり
零点の個数を比較することで$x_{n+1,i}^P < x_{n,i}^P < x_{n+1, i+1}^P$を得る。(証明終わり)
ということで、この分離定理が一般の場合にも証明できたことになる。
さて上の定理より
数列$\{x_{n,i}^P\}_{n=i}^\infty$は単調減少列であり、逆に数列$\{x_{n,n-i+1}^P\}_{n=i}^\infty$は単調増加列である。
次の2つの数を定める。($\pm\infty$の可能性も含めて存在)
\begin{align*}
\xi_i = \lim_{n\to\infty}x_{n,i}^P, \quad
\eta_i = \lim_{n\to\infty}x_{n,n-i+1}^P
\end{align*}
それぞれ小さい方から$i$番目の零点の極限、大きい方から$i$番目の零点の極限を表している。
区間$(\xi_1, \eta_1)$は(全ての零点を含む最小区間だが)大事な概念となってくる。
ガウス求積法
(心の声:本当はルジャンドル多項式を定義するのが先の気もするがまぁいいや)
必要ならばその時に説明をつけるスタンスで。
何をしたいかと言えば、区間$[a, b]$上の関数の積分
$\displaystyle \int_a^bf(x)dx$を少ない回数の計算で近似したい、というモチベーションがある。
そもそも
そもそも、実関数の積分なんぞできる方がかなり少ないものである。
それに加えて、電卓を含めた数値計算では実際に被積分関数を求める、というのは比較的高度なので
うまく近似して定積分の値を求めたい。そういう感じである。
零点を求めたい(二分法、ニュートン法、その他高速アルゴリズム)ときの例はよく知られているだろう。
それと似たような動機には違いない。
ラグランジュの補間多項式
ある関数を多項式で近似(補間=interpolate)するのもまた重要な数値計算の研究課題である。
以下$t_1, t_2, \cdots, t_n$を互いに異なる$n$個の実数とし、
$(t_i, y_i)$という$n$個の点を通る$n-1$次以下の多項式を計算することを考える。($y_i$は任意実数)
例えば二次関数の問題で
Question: そのグラフが$(x, y)=(-1, 7), (2, 4), (3, 11)$の3点を通る二次関数を求めよ。
などといった問題は高校数学の基礎でよく現れるものであるが、より次数の高い場合だと思えばよい。
上の例の問題だと、例えば
$y=ax^2+bx+c$とおくのが主流です、と教わるに違いない。
すると3点を通る情報から
\begin{align*}
\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}
=
\begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ 11 \end{pmatrix}
\end{align*}
といった三変数の連立一次方程式を解く必要が出てくる。
この方法は、まだ3変数だからマシだけど、逆行列をかける(=連立方程式を解く)のがかなり面倒。
一般的に$(t_i, y_i)$という$n$個の点を通る、という状況ならば、出てくる$n$次正方行列は
\begin{align*}
\begin{pmatrix}
t_1^{n-1} & t_1^{n-2} & \cdots & 1 \\
t_2^{n-1} & t_2^{n-2} & \cdots & 1 \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
t_n^{n-1} & t_n^{n-2} & \cdots & 1
\end{pmatrix}
\end{align*}
のような行列(いわゆるVandermondeの行列)の逆行列を考える必要があるわけで。
実はこのVandermondeの行列の逆行列はそれなりに綺麗に書けるのです!
という話をするのが、まさにラグランジュ補間多項式に他ならない。
ではラグランジュ補間多項式とはどのようなものであるのか。
上の$\{t_i\}$に対し、まずこれら全てを零点に持つ多項式
$F(x)=\displaystyle \prod_{i=1}^n(x-t_i)$を考える。これは$n$次多項式。
ここで示すべきは、任意の$k$($1\le k\le n$)に対し、$F'(t_k)$の値が消えていないことである。
実際、積の微分法を使うことで
\begin{align*}
\frac{d}{dx}\prod_{i=1}^n(x-t_i)
=\sum_{j=1}^n\prod_{\substack{i=1 \\ i\neq j}}^n(x-t_i)
\end{align*}
となっているので、ここに$x=t_k$を代入すると$j=k$のところの和だけが残り$\prod_{i\neq k}(t_k-t_i)$が微分係数$F'(t_k)$である。
$\{t_i\}$たちは互いに異なる数としていたので、この$F'(t_k)$は$0$ではないことが従う。
そこで
\begin{align*}
l_k(x):=\frac{F(x)}{F'(t_k)(x-t_k)}
=\frac{F(x)}{\prod_{i\neq k}(t_k-t_i)\cdot(x-t_k)}
\end{align*}
とおく。これは$n-1$次の多項式であり、$t_k$での値が$1$で、それ以外の$t_i$では消えている。
この関数を線型結合させることで、
\begin{align*}
L_n(x)=\sum_{i=1}^ny_il_i(x)
\end{align*}
関数$L_n(x)$を$L_n(t_i)=y_i$を満たすように作ってくることができた。
先の二次関数の例だと
\begin{align*}
f(x)=7\frac{(x-2)(x-3)}{(-1-2)(-1-3)}
+4\frac{(x+1)(x-3)}{(2+1)(2-3)}
+11\frac{(x+1)(x-2)}{(3+1)(3-2)}
=2x^2-3x+2
\end{align*}
と計算ができるわけである。 #こっちの方が計算しんどい?笑
・・・それで
このラグランジュ補間多項式が直交多項式の零点とどう関わってくるかについて。
$\mathcal{L}$を直交多項式$\{P_n(x)\}$の正定値モーメントとする。
また各$P_n(x)$の零点を上と同様に$x_{n,1}^P,\, x_{n,2}^P,\, \cdots,\, x_{n,n}^P$とおく。($n\ge1$)
このときある定数$\{A_{n,k}^P\}_{1\le k\le n}$が存在して、
任意の$2n-1$次以下の多項式$f(x)$に対して次のことが成り立つようにできる。
- $\displaystyle\mathcal{L}[f(x)]=\sum_{k=1}^nA_{n,k}^Pf(x_{n,k}^P)$と書くことができる。
- $\{A_{n,k}^P\}_{1\le k\le n}$は全て正で、足すと$\mu_0=\mathcal{L}[1]$に等しい。
なかなか恐ろしい定理がやってきた。
零点の情報と、高々$n$個の定数で、$2n-1$次多項式までのモーメントを表せてしまう。
note: この定数$\{A_{n,k}^P\}_{1\le k\le n}$は実は一意的であり、Christoffel数と呼ぶことにする。
ラグランジュの補間多項式を用いて、
任意の$1\le k\le n$で$L(x_{n,k}^P)=f(x_{n,k}^P)$となるような$n-1$次以下の多項式$L$を構成できる。
$Q(x)=f(x)-L(x)$とおくと、この$Q(x)$は全ての$x_{n,k}^P$で消える$2n-1$次以下の多項式である。
すなわち、この$Q(x)$は$P_n(x)$を因子に持つことがわかり
$Q(x)=R(x)P_n(x)$なる多項式$R$が存在する。($R$は$0$かもしれない)
$R$の次数は高々$(2n-1)-n=n-1$以下であることに注意する。
すると$f(x)$のモーメントは
\begin{align*}
\mathcal{L}[f(x)]
&=\mathcal{L}[L(x)+Q(x)] \\
&=\mathcal{L}[L(x)]+\mathcal{L}[R(x)P_n(x)] \\
&=\mathcal{L}[L(x)] \quad (\text{直交性より}) \\
&=\mathcal{L}\left[\sum_{k=1}^nf(x_{n,k}^P)l_k(x)\right] \quad (\text{ラグランジュ補間多項式の定義})\\
&=\sum_{k=1}^nf(x_{n,k}^P)\mathcal{L}[l_k(x)]
\end{align*}
したがって題意の式に合うように$A_{n,k}^P$を$A_{n,k}^P:=\mathcal{L}[l_k(x)]$とおく。
なお、ここで注意として$l_k(x)$は当然($n-1$次式だし)$n$に依存している。式で書くと
\begin{align*}
l_k(x)=\frac{P_n(x)}{\prod_{i\neq k}(x_{n,i}^P-x_{n,k}^P)\cdot(x-x_{n,k}^P)}
\end{align*}
のように定められたものであった。
作り方から$\sum_{k=1}^nl_k(x)=1$である。実際任意の零点で1を返す多項式であるからである。
このことより$\sum_{k=1}^nA_{n,k}^P=\mathcal{L}[1]$が従う。
さらに、各$A_{n,k}^P$が正であることは次のように示される。
以下$m$は$1\le m\le n$を満たす任意の数とする。
多項式$f(x)$を$f(x)=l_m(x)^2$として定める。
これは上で書いたとおり$2(n-1)$次式で、すなわちこの定理の仮定を満たす。
また、正定値性の仮定から$\mathcal{L}[f(x)]=\mathcal{L}[l_m(x)^2]>0$であることに注意する。
ゆえに
\begin{align*}
0<\mathcal{L}[l_m(x)^2]
=\sum_{k=1}^nA_{n,k}^Pl_m(x_{n,k}^P)^2
=A_{n,m}^P
\end{align*}
が従い、全てのモーメントが正であることが示された。(証明終わり)
このChristoffel数については以下のようにも書けることがわかる;
上の定理で定めた$A_{n,k}^P$に対して、次の2式が成立する。
なお三項間漸化式の係数$\lambda_i$と、核多項式に付随する正規化直交多項式$p_n(x)$は前回の記事の通りとする。
- \begin{align*} A_{n,k}^P=-\frac{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_n} {P_{n+1}(x_{n,k}^P)P_n'(x_{n,k}^P)} \end{align*}
- \begin{align*} A_{n,k}^P=\left(\sum_{i=0}^np_i^2(x_{n,k}^P)\right)^{-1} \end{align*}
まず(1)を示す。すなわち、上の定理4で書き下した
\begin{align*}
A_{n,k}^P=\mathcal{L}\left[\frac{P_n(x)}{\prod_{i\neq k}(x_{n,i}^P-x_{n,k}^P)\cdot(x-x_{n,k}^P)}\right]
\end{align*}
が(1)の右辺と等しいことを主張する必要がある。
これを変形していくと
\begin{align*}
A_{n,k}^P
&=\mathcal{L}\left[\frac{P_n(x)}{\prod_{i\neq k}(x_{n,i}^P-x_{n,k}^P)\cdot(x-x_{n,k}^P)}\right] \\
&=\frac{1}{\prod_{i\neq k}(x_{n,i}^P-x_{n,k}^P)}
\mathcal{L}\left[\frac{P_n(x)}{x-x_{n,k}^P}\right] \\
&=\frac{1}{P_n'(x_{n,k}^P)}
\mathcal{L}\left[\frac{P_n(x)}{x-x_{n,k}^P}\right] \tag{1}
\end{align*}
となる。
ここでChristoffel–Darbouxの公式を、$y=x_{n,k}^P$として用いると
\begin{align*}
\sum_{i=0}^n\frac{P_i(x)P_i(x_{n,k}^P)}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_i}
&=\frac{1}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_n}
\frac{P_{n+1}(x)P_n(x_{n,k}^P)-P_n(x)P_{n+1}(x_{n,k}^P)}{x-x_{n,k}^P} \\
&=-\frac{P_{n+1}(x_{n,k}^P)}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_n}
\frac{P_n(x)}{x-x_{n,k}^P}
\end{align*}
の式が得られる。このことから
\begin{align*}
\mathcal{L}\left[\frac{P_n(x)}{x-x_{n,k}^P}\right]
&=
\mathcal{L}\left[
-\frac{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_n}{P_{n+1}(x_{n,k}^P)}
\sum_{i=0}^n\frac{P_i(x)P_i(x_{n,k}^P)}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_i}
\right] \\
&=
-\frac{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_n}{P_{n+1}(x_{n,k}^P)}
\sum_{i=0}^n
\frac{P_i(x_{n,k}^P)}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_i}\mathcal{L}[P_i(x)] \tag{2}
\end{align*}
がわかる。
さらに直交性から
$\mathcal{L}[P_i(x)]=\mathcal{L}[1\cdot P_i(x)]=0$
が任意の$i\ge1$に対して成立していることに注意すると
\begin{align*}
\sum_{i=0}^n
\frac{P_i(x_{n,k}^P)}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_i}\mathcal{L}[P_i(x)]
=\frac{P_0(x_{n,k}^P)}{\lambda_0}\mathcal{L}[P_0(x)]
=\frac{1}{\lambda_0}\cdot\mu_0=1 \tag{3}
\end{align*}
が従う。
以上式番号(1)から(3)の式を組み合わせることで
\begin{align*}
A_{n,k}^P
=-\frac{1}{P_n'(x_{n,k}^P)}
\frac{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_n}{P_{n+1}(x_{n,k}^P)}
\end{align*}
を得る。これで一つ目が示された。
(2)は(1)から簡単に示される。
前回の記事で示した、合流型Christoffel–Darbouxの公式(の左辺)を$p_n(x)$で書き直すと
\begin{align*}
\sum_{k=0}^np_k(x)^2
=\frac{P_{n+1}'(x)P_n(x)-P_n'(x)P_{n+1}(x)}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_n}
\end{align*}
がわかる。この式に$x=x_{n,k}^P$を代入すると
\begin{align*}
\sum_{i=0}^np_i(x_{n,k}^P)^2
=-\frac{P_{n+1}(x_{n,k}^P)P_n'(x_{n,k}^P)}{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_n}
\end{align*}
となることから、(1)と(2)の式は等価であることが分かった。(証明終わり)
チェビシェフ多項式における計算例
ここで安定の流れではあるが、Christoffel数$A_{n,k}^P$をチェビシェフ多項式において計算してみる。
上の系を含めると、3通りの同値な式で計算できることがわかったが
一番explicitに計算できると思われる
$\displaystyle A_{n,k}^P=-\frac{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_n}
{P_{n+1}(x_{n,k}^P)P_n'(x_{n,k}^P)}$の式を使って計算することを考える。
・・・としたいが、ややこしいのはチェビシェフ多項式はモニック化されていないことで
最高次係数の分の寄与を考慮する必要がある。
となるが、
\begin{align*}
\mathcal{L}[f(x)]=\sum_{k=1}^nA_{n,k}^Pf(x_{n,k}^P)
\end{align*}
の式を見ると、$P_n(x)$の最高次係数はChristoffel数に影響しない。
$\Rightarrow$チェビシェフ多項式の方をモニック化しても同じ結論を得る。
第一チェビシェフ多項式の場合
さてモニック化された第一種チェビシェフ多項式$\widetilde{T}_n(x)=2^{-n+1}T_n(x)$ (この式は$n\ge1$、初項は変えない) は
三項間漸化式
\begin{align*}
\widetilde{T}_{n+2}(x)=\begin{cases}
x\widetilde{T}_{n+1}(x)-\frac{1}{2}\widetilde{T}_n(x) & (n=0) \\
x\widetilde{T}_{n+1}(x)-\frac{1}{4}\widetilde{T}_n(x) & (n\ge1)
\end{cases},
\quad \widetilde{T}_0(x)=1, \quad \widetilde{T}_1(x)=x
\end{align*}
によって定められる数列となっている。
この場合$i\ge2$で$\lambda_i=\frac{1}{4}$であり、$\lambda_1=\frac{1}{2}$に注意する。
また、0次モーメントは$\lambda_0=\pi$であった。
以上より分子は$\displaystyle \lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_n=\frac{\pi}{4^{n-1}\cdot2}$と計算できる。
次に分母の計算であるが、三角関数の形に帰着させて計算するのも恐ろしいので
直接$T_{n+1}(x)T_n'(x)$を$T_n(x)$で割った余りを考えたい。
ここで$T_n'(x)=nU_{n-1}(x)$だったことを思い出すと
\begin{align*}
T_{n+1}(x)T_n'(x)
&=nT_{n+1}(x)U_{n-1}(x) \\
&=n\cos(n+1)\theta\, \cdot \frac{\sin n\theta}{\sin\theta} \quad (x=\cos\theta \text{と置換した}) \\
&=\frac{n}{2}\frac{\sin(2n+1)\theta-\sin\theta}{\sin\theta} \quad (\text{積和の公式}) \\
&=\frac{n}{2}\frac{\sin(2n+1)\theta+\sin\theta}{\sin\theta}-n \quad (\text{トリッキーな式変形}) \\
&=\frac{n}{2}\frac{2\sin(n+1)\theta\cos n\theta}{\sin\theta}-n \quad (\text{和積の公式}) \\
&=nT_n(x)U_n(x)-n \quad (x=\cos\theta)
\end{align*}
と変形ができるので(!)、これにより$T_{n+1}(x)T_n'(x)$を$T_n(x)$で割った余りが$-n$だとわかる。
よってモニック化をすると、$T_{n+1}(x)T_n(x)$の最高次係数は$2^{2n-1}$なので
$\widetilde{T}_{n+1}(x)\widetilde{T}_n'(x)$を$\widetilde{T}_n(x)$で割った余りが$\displaystyle -\frac{n}{2^{2n-1}}$であることがわかる。
以上よりChristoffel数は
\begin{align*}
A_{n,k}^P
=-\frac{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_n}
{P_{n+1}(x_{n,k}^P)P_n'(x_{n,k}^P)}
=-\frac{\pi/(4^{n-1}\cdot2)}{-n/2^{2n-1}}=\frac{\pi}{n}
\end{align*}
と計算できた。特にこれは$k$には依存しない値である。
note: この値を$n$個足すと$\mu_0=\mathcal{L}[1]=\pi$と一致することも確認できた。
第二チェビシェフ多項式の場合
実はこの場合は少し様子が違ってくる。
モニック化された第二チェビシェフ多項式の三項間漸化式は次のように書ける:
\begin{align*}
\widetilde{U}_{n+2}(x)=
x\widetilde{U}_{n+1}(x)-\frac{1}{4}\widetilde{U}_n(x),
\quad \widetilde{U}_0(x)=1, \quad \widetilde{U}_1(x)=x
\end{align*}
また0次のモーメントは$\displaystyle \lambda_0=\int_{-1}^1\sqrt{1-x^2}dx=\frac{\pi}{2}$と書ける。
これを踏まえることで、$\lambda_i$たちの積である分子の項は
\begin{align*}
\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_n=\frac{\pi}{2\cdot 4^n}=\frac{\pi}{2^{2n+1}}
\end{align*}
と書くことができる。
次は上同様にして、$U_{n+1}(x)U_n'(x)$を$U_n(x)$で割った余りを考えたいところである。
$U_n'(x)$の値は記事(1)の途中で同様に計算していたことを思い出すと
\begin{align*}
U_{n+1}(x)U_n'(x)
&=U_{n+1}(x)\frac{(n+1)T_{n+1}(x)-xU_n(x)}{x^2-1} \\
&=\frac{n+1}{x^2-1}U_{n+1}(x)T_{n+1}(x)-\frac{x}{x^2-1}U_{n+1}(x)U_n(x) \tag{4}
\end{align*}
ここで$U_{n+1}(x)T_{n+1}(x)$に対して上と同じような変形を考えると、
\begin{align*}
U_{n+1}(x)T_{n+1}(x)
&=
\frac{\sin(n+2)\theta}{\sin\theta}\cos(n+1)\theta \quad (x=\cos\theta) \\
&=
\frac{\{\sin(n+2)\theta\cos(n+1)\theta-\cos(n+2)\theta\sin(n+1)\theta\}+\cos(n+2)\theta\sin(n+1)\theta}{\sin\theta} \\
&=
\frac{\sin\theta+\cos(n+2)\theta\sin(n+1)\theta}{\sin\theta} \quad (\text{加法定理}) \\
&=
1+T_{n+2}(x)U_n(x) \tag{5}
\end{align*}
のように変形することが可能であり、(4)(5)式を併せると
\begin{align*}
U_{n+1}(x)U_n'(x)
&=\frac{n+1}{x^2-1}(1+T_{n+2}(x)U_n(x))-\frac{x}{x^2-1}U_{n+1}(x)U_n(x) \\
&=\frac{n+1}{x^2-1}
+U_n(x)\frac{(n+1)T_{n+2}(x)-xU_{n+1}(x)}{x^2-1}
\end{align*}
を得る。さてここに代入する$x_{n,k}^U$は当然$\pm1$ではないことを確認し、代入すると
\begin{align*}
U_{n+1}(x_{n,k}^U)U_n'(x_{n,k}^U)
&=\frac{n+1}{(x_{n,k}^U)^2-1} \\
&=\frac{n+1}{(\cos\frac{k\pi}{n+1})^2-1} \quad (x_{n,k}^U=\cos\frac{n+1-k}{n+1}\pi=-\cos\frac{k\pi}{n+1} \text{より})\\
&=-\frac{n+1}{\sin^2\frac{k\pi}{n+1}}
\end{align*}
が従う。さらに$U_{n+1}(x)U_n(x)$の最高次係数$2^{n+1}\cdot 2^n=2^{2n+1}$で割ることで
\begin{align*}
\widetilde{U}_{n+1}(x_{n,k}^U)\widetilde{U}_n'(x_{n,k}^U)
=-\frac{n+1}{2^{2n+1}\sin^2\frac{k\pi}{n+1}}
\end{align*}
となることがわかる。以上よりChristoffel数は
\begin{align*}
A_{n,k}^U
=-\frac{\displaystyle \frac{\pi}{2^{2n+1}}}{\displaystyle \left(-\frac{n+1}{2^{2n+1}\sin^2\frac{k\pi}{n+1}}\right)}
=\frac{\pi}{n+1}\sin^2\frac{k\pi}{n+1}
\end{align*}
のように求めることができて、こちらは$k$に依存する値である。
なお、$\displaystyle \sum_{k=1}^n\sin^2\frac{k\pi}{n+1}=\frac{n+1}{2}$より$A_{n,k}^U$の和が$\displaystyle \mathcal{L}[1]=\frac{\pi}{2}$になることも確認できる。
ガウスの求積法の応用
このガウスの求積法を用いて、直交多項式の零点に関する主張を得ることができる。
自然数$n, N$は$n>N\ge2$を満たすものとする。
この時、$P_N(x)$のどの2つの零点の間にも少なくとも1つ$P_n(x)$の零点が存在する。
note: $n=N+1$のときは、一つ前の分離定理(定理3)より$x_{N,i}^P < x_{N+1, i+1}^P < x_{N,i+1}^P$が従うので示されている。
ただこの定理3からは、$n\ge N+2$の場合については結論を得ることができない。
背理法で、ある$n>N$とある$1\le p< N$に対し、
$P_n(x)$は$x_{N, p}^P$と$x_{N, p+1}^P$の間に零点を持たない
ことを仮定する。
次の多項式$\rho(x)$を定める。
\begin{align*}
\rho(x):=\frac{P_N(x)}{(x-x_{N, p}^P)(x-x_{N, p+1}^P)}
\end{align*}
この$\rho(x)$は$N-2$次の多項式である。
また区間$(x_{N, p}^P,\, x_{N, p+1}^P)$の外では$\rho(x)$の分母は$0$以上であることから
$x\notin (x_{N, p}^P,\, x_{N, p+1}^P)$においては$\rho(x)P_N(x)\ge0$が従う。
さて定理4のガウスの求積法を使うと、$\rho(x)P_N(x)$の次数は$2N-2<2n-1$であることに注意して
\begin{align*}
\mathcal{L}[\rho(x)P_N(x)]
=\sum_{k=1}^nA_{n,k}^P\rho(x_{n,k}^P)P_N(x_{n,k}^P)
\end{align*}
となる。
上で示した事実:$x\notin (x_{N, p}^P,\, x_{N, p+1}^P)$において$\rho(x)P_N(x)\ge0$であること、から
この区間の外において$P_n(x)$の零点は存在しない。もしあったならば単根なので符号が変わるはずである。
また、この区間$(x_{N, p}^P,\, x_{N, p+1}^P)$においては背理法の仮定から存在しない。
以上より$P_N(x_{n,k}^P)$及び$\rho(x_{n,k}^P)$は$0$になることはなく
$A_{n,k}^P>0$であったことから、$\mathcal{L}[\rho(x)P_N(x)]>0$が従う。
しかしこれは$P_N(x)$の直交性の仮定に反する。(証明終わり)
まとめ
今回は、直交多項式の零点に焦点を当てて、
それら零点の分離性を中心に観察した。
その際にも、前回最後のChristoffel–Darbouxの公式が姿を現した。
次の回でも、Christoffel–Darbouxの公式のまた別の応用に焦点を当てたいと思う。