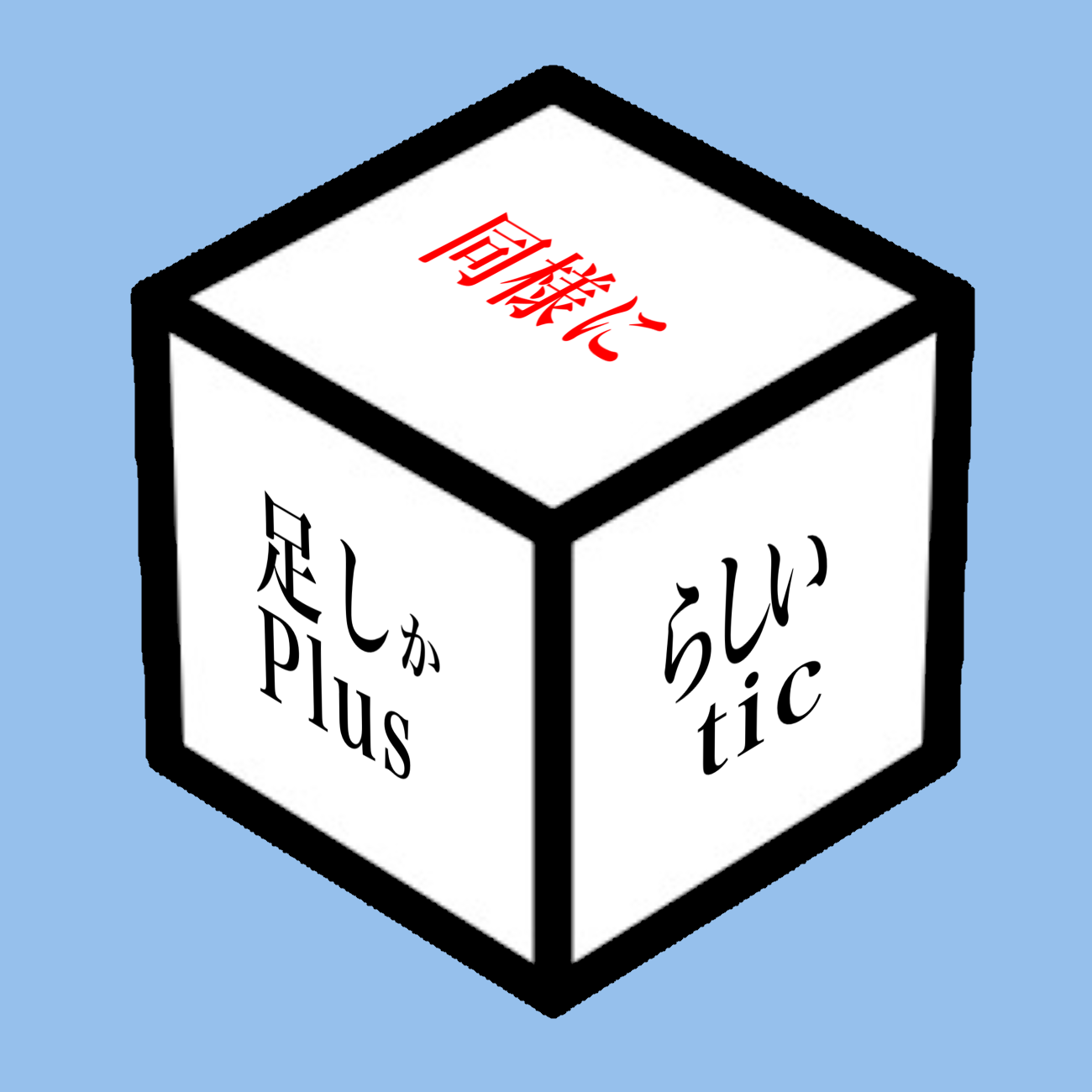ライプニッツの定理は二項定理から証明できる。
はじめに読んで欲しい
この記事は初心者が書いています。間違っているところや不十分な解説などがあるかもしれません。見つけた際は優しく、易しく教えて欲しいです。大目に、或いは暖かい目で見て頂けるとうれしいです。
また、この記事の内容は
こちら
を参考にしました。
この記事では、開区間$I\subset ℝ$や開領域$U\subset ℝ^2$上の$C^\infty $級関数がなすℝ代数を$C^\infty (I)$や$C^\infty (U)$と書いたり、$k$加群$N$の自己準同型環を$\mathrm{End}_k(N)$と書きます。二項係数は${n \choose k}$と表します。
二項定理とライプニッツの定理と補題
二項定理
$A$を環としたとき、$x,y∈A$が可換($xy=yx$)なら任意の非負整数$n$に対して$$(x+y)^n= \sum_{k=0}^{n} {n \choose k}x^ky^{n-k}$$
ライプニッツの定理
$f,g∈C^\infty (I)$なら任意の非負整数$n$に対して$$(\frac{d}{dx})^n(f(x)g(x))=\sum_{k=0}^{n} {n \choose k}(\frac{d}{dx})^kf(x)(\frac{d}{dx})^{n-k}g(x) $$
$k$乗のところとか二項係数とか見ると、やっぱり似ていますね。どちらとも帰納法を用いて似たように証明できますが、ここではその証明は書きません。 高校数学の美しい物語さん などを見るといいかもです(環じゃないですが証明は同様です)。
$U\subset ℝ^2$を開領域としたとき$F(y,z)∈C^\infty (U)$に対しいして$$\frac{∂}{∂y}\frac{∂}{∂z}F(y,z)=\frac{∂}{∂z}\frac{∂}{∂y}F(y,z)$$
ここではこの証明は書きません。証明は
数学の景色さん
などが分かりやすかったです(こっちの方が一般的に示されてます)。
さてシュワルツの定理は環の言葉を使うとこうも言えます。
$\frac{∂}{∂x},\frac{∂}{∂y}∈\mathrm{End}_ℝ(C^\infty (U))$と考えたとき、$\frac{∂}{∂x},\frac{∂}{∂y}$が可換(つまり$\frac{∂}{∂x}\frac{∂}{∂y}=\frac{∂}{∂y}\frac{∂}{∂x}$)である。
こう言う言い換えをする意味は、微分というのを環の元として二項定理を適用したいからです。可換なのでうれしいです。
さてもう一つ、必要なことを用意します。これはちゃんと証明します。
$I\subset ℝ$を開区間とったとき、$F(y,z)∈C^\infty (I×I)$にたいして
$$\frac{d}{dx}F(x,x)=\frac{∂}{∂y}F(x,x)+\frac{∂}{∂z}F(x,x)= (\frac{∂}{∂y}+\frac{∂}{∂z})F(x,x) $$
$\frac{∂}{∂y}$と$\frac{∂}{∂z}$はそれぞれ$F$の第一成分での偏微分と第二成分での偏微分を表しています。変数の書き方がキモいですが、誰かいい書き方知りませんか。
直接示す。任意に$x∈I$をとったとき、$I$が開区間であるから十分小さく$h$を取れば$x+h∈I$となる。
$$\frac{d}{dx}F(x,x)=\lim_{h \to 0}\frac{F(x+h,x+h)-F(x,x)}{h}=\lim_{h \to 0}\frac{F(x+h,x+h)-F(x+h,x)+F(x+h,x)-F(x,x)}{h}=\lim_{h \to 0}\frac{F(x+h,x+h)-F(x+h,x)}{h}+\frac{F(x+h,x)-F(x,x)}{h}=\frac{∂}{∂y}F(x,x)+\frac{∂}{∂z}F(x,x)=(\frac{∂}{∂y}+\frac{∂}{∂z})F(x,x)$$
よって命題は示された。
証明の仕方が積の微分公式のに似ています。ここでは$y=x,z=x$としていますはが、$y=φ(x),z=ψ(x)$とおいた時もそんな風なものがな成り立ち、これを二変数関数の合成関数の微分公式と言うそうです。
この補題もまた言い換えます。
$I$を開区間としたとき、$Δ:C^\infty (I×I)→C(I):F(y,z) \mapsto F(x,x)$というℝ線形写像を考えるとき、$\frac{d}{dx}Δ=Δ(\frac{∂}{∂y}+\frac{∂}{∂z})$
ここで出てくる$Δ$とは$I$から$I×I$への対角写像と$f∈C^\infty (I×I)$の合成です。この$Δ$を使って証明ライプニッツの定理を証明します。
ライプニッツの定理の証明と一般化
ではいよいよライプニッツの定理について証明しましょう。もう一度定理を書いておきます。
$f,g∈C^\infty (I)$なら任意の非負整数$n$に対して$$(\frac{d}{dx})^n(f(x)g(x))= \sum_{k=0}^{n} {n \choose k}(\frac{d}{dx})^kf(x)(\frac{d}{dx})^{n-k}g(x) $$
$f,g∈C^\infty (I)$に対して、$F(y,z)=f(y)g(z)$と定義する。すると補題2より、
$$ (\frac{d}{dx})^n(f(x)g(x))= (\frac{d}{dx})^nΔF(y,z)=Δ(\frac{∂}{∂y}+ \frac{∂}{∂z})^nF(y,z)$$
が言える。シュワルツの定理より$\frac{∂}{∂y}$と$\frac{∂}{∂z}$は$\mathrm{End}_ℝ(C^\infty (I))$の元として可換であり、よって$(\frac{∂}{∂y}+ \frac{∂}{∂z})^n$は二項定理で展開できる。
$$Δ(\frac{∂}{∂y}+ \frac{∂}{∂z})^nF(y,z)=Δ( \sum_{k=0}^{n} {n \choose k}(\frac{∂}{∂y})^k(\frac{∂}{∂z})^{n-k})F(y,z)=Δ( \sum_{k=0}^{n} {n \choose k}(\frac{∂}{∂y})^k(\frac{∂}{∂z})^{n-k}F(y,z))= \sum_{k=0}^{n} {n \choose k}(\frac{d}{dx})^kf(x)(\frac{d}{dx})^{n-k}g(x) $$
よって命題は示された。
書いてみると呆気無けないですね。呆気無いのでもう少し一般化してみます。
$k$を可換環として、$k$加群$N$に$Δ:N⊗_kN→N$という$k$加群の準同型が定まっているとする。
このとき$k$加群の準同型$D:N→N$が微分であるとは、任意の$a,b∈N$に対して$$D(Δ(a⊗b))=Δ(D(a)⊗b)+Δ(a⊗D(b))$$が成り立つことをいう。
$Δ:N⊗_kN→N$とは$N$に入る積を表しているので、$ab=Δ(a⊗b)$とかけば$D(ab)=D(a)b+aD(b)$と書けます。これは$C^\infty (I)$でも見た、積の微分公式と同じ形です。
ただ$C^\infty (I)$と違うのは、$N$に入るこの積は分配律(双線形性)のみ満たしていて、結合性や可換性、単位性も仮定されないことにあります。
この定義からすぐに、補題3の言い換えのような事実が言えます。
$D:N→N$が微分であるなら、$DΔ=Δ(D⊗\mathrm{id}_N+\mathrm{id}_N⊗D)$
テンソル積は底にある空間の直積に対応すると思います。$N$は$C^\infty (I)$に対応していて、$N⊗_kN$は$C^\infty (I×I)$に対応(同型ではない)していて、$D⊗\mathrm{id}_N$と$\mathrm{id}_N⊗D$はそれぞれ第一成分での偏微分と第二成分での偏微分に対応しています。テンソル積は積であると同時に多変数化でもあったわけです。そうすると、補題3で証明方法が積の微分公式の証明に似ていたことにも納得ができるような気がします。
また、$D⊗\mathrm{id}_N,\mathrm{id}_N⊗D∈\mathrm{End}_k(N⊗_kN)$と見た時、これはちゃんと可換になってくれます。よってここでも二項定理を考えることができます。
では、この一般化した微分の上でライプニッツの定理を証明します。
$a,b∈N$なら任意の非負整数$n$に対して$$D^n(ab)=\sum_{k=0}^{n} {n \choose k}D^k(a)D^{n-k}(b)$$
先程の議論に沿って証明する。
$$D^n(ab)=D^n(Δ(a⊗b))=Δ(D⊗\mathrm{id}_N+\mathrm{id}_N⊗D)^n(a⊗b)=Δ(\sum_{k=0}^{n} {n \choose k}(D⊗\mathrm{id}_N)^k(\mathrm{id}_N⊗D)^{n-k})(a⊗b)=\sum_{k=0}^{n} {n \choose k}D^k(a)D^{n-k}(b)$$
よって命題は示された。
証明できました。
ここで重要なのは$D⊗\mathrm{id}_N,\mathrm{id}_N⊗D$が可換ということなので、例えば微分$D$に$c∈k$という重さをつけて、$D(ab)=D(a)b+caD(b)$という式が成り立つとした時にも似たような公式が成り立ちます。これをどう使うかは知りません。二項定理自体も
nakanoさん
の記事などを参考に一般化できますが、これを使えば面白い結果が出でてくるんでしょうか。
これとは逆の試みで、ライプニッツの定理から二項定理を導こうってことが
Wikipediaの二項定理
に書いてありました。指数関数を用いて証明する内容ですが、指数関係の性質とかネイピア数の定義とかに二項定理って必要じゃないのかなって思います。いや、循環論法とか気にするような場面じゃないのかな。
おわりに
ここまで読んでくれてありがとうございました。間違いなどがあったら教えてくださいっ。